Customer Logins
Obtain the data you need to make the most informed decisions by accessing our extensive portfolio of information, analytics, and expertise. Sign in to the product or service center of your choice.
Customer LoginsOEM Highlights
CES 2026:毎年恒例の展示会が開幕、焦点は車載技術
Stephanie Brinley(アソシエイトディレクター)

Getty Images
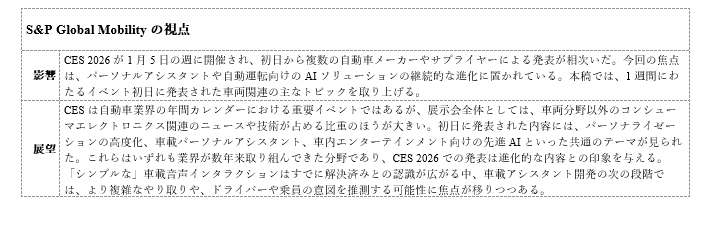
CES 2026が1月5日の週に開催され、初日から複数の自動車メーカーやサプライヤーによる発表が相次いだ。今回の焦点は、車載エンターテインメントを支えるAIソリューションの継続的な高度化に加え、新たに進化を続けるパーソナルアシスタントプログラムを通じた操作のパーソナライゼーション、ならびに自動運転分野に置かれている。
BMW:Neue KlasseとBMW iX3向けにAmazon Alexa+を採用
BMWがCES 2026で発表した内容は、すでに紹介されていたiX3とその機能をさらに発展させるものとなった。2026年後半から、米国およびドイツのiX3購入者を対象に、BMWは自動車メーカーとして初めて、AmazonのAIであるAlexa+のアーキテクチャを車両に統合する。CES 2026の会場では、そのデモンストレーションを体験できる。BMWによると、このシステムにより、車両機能や一般的な知識に関して、複数の質問を一つの文章で行うことが初めて可能になるという。Amazonのアカウントと連携することで、検索や音楽ストリーミングを含む各種コンテンツへのアクセスも容易になる。ただし、利用者は複数のAmazonアカウントを利用者が保有している必要があり、基本的なコネクティビティやデータ通信料に加え、追加のサブスクリプション料金が発生する可能性もある。
Amazon Alexa+システムでは、質問を行った後に、さらに追加の質問を重ねることも可能となる。BMWはその有効性を示す例として、利用者が「ねぇBMW、世界で最も有名な絵画は何で、どこにある?」と尋ねた後、システムの回答を受けて「そこに連れて行って」と続けることで、その作品が展示されている場所までのナビゲーションを取得できる点を挙げた。BMWは、「このインテリジェントな音声アシスタントは、このような対話的なやり取りを通じて、将来の音声コマンドにより正確に応答し、質問の意図を先読みすることも可能になる」と述べている。
Geely、車載AIにCerence xUIを採用
Cerenceは、Geely Autoが同社の次世代大規模言語モデル対応AIシステムであるCerence xUIを採用すると発表した。Geelyにおける最初の適用車種は、4月に投入予定のGeely Galaxy M9となる。Galaxy M9はCES 2026の展示車両にも含まれており、中国市場向けモデルであるが、Geelyは将来的に欧州市場への投入を目指している。Cerenceによると、このシステムはGeely AutoのフルドメインAI技術と、ハイブリッド型およびエージェント型AIに関するCerenceの知見を中核に据えたものだという。特筆すべき点は、このシステムが中国国外の市場を主な対象としていることである。Cerenceは声明で、本プロジェクトが「海外市場におけるローカライゼーション要件に対する深い知見」を活用するものだと説明している。Geely AutoはCerence xUIを用いて、複数意図の認識、画面上の内容に応じた操作を可能にする「Say What You See」機能、自然な質問や意図の理解といった音声インタラクション手法を導入し、地域ごとの言語的・文化的慣習により適合した車載体験を提供する方針である。両社は今後、Vehicle Control AgentやNavigation Agentなどの機能・性能の高度化に向けて、協業を継続していくとしている。
Cerenceは、このシステムが意図認識型の自然な対話を可能にするとしている。車載アシスタントは、より幅広いタスクに対して会話的かつ的確に応答できるほか、「窓を下げて、それから、評価が高くて無料WiFiと駐車場のあるコーヒーショップを探して」といった複雑な指示にも対応可能だという。また、複数の独立した音響ゾーンをサポートすることで、他の座席位置での会話による干渉を気にすることなく、乗員が車載アシスタントを利用できるとしている。
Lucid-Uber-Nuro、ライドヘイリング向けプロジェクトをアップデート
2025年後半にLucid、Uber、Nuroが、2026年にカリフォルニア州で開始予定のロボタクシープロジェクトを発表した。CES 2026では、米国での開始を予定しつつも将来的なグローバル展開を見据えた同ロボタクシーサービス向けの「量産意図車両(production intent vehicles)」が公開された。テクノロジー志向の強い環境での展示は、プロジェクト開発が着実に進んでいることを印象付けるものとなっている。
Nuroは2025年12月に自動運転車の公道走行試験を開始しており、CES 2026は同車両が一般公開される初の機会となった。共同声明によると、車両はLucid Gravity SUVで、Nuroが自動運転システムを提供し、Uberが車内の乗客体験を設計している。ロボタクシー仕様のGravityには、高解像度カメラ、ソリッドステートLiDARセンサー、レーダーを含むセンサーアレイが搭載されている。これらのセンサーは車体に統合されているほか、専用設計の低背型ルーフマウント・ハローにも組み込まれている。ルーフ上のハローには、乗客や周囲の人々に向けて情報を伝えるためのLEDが備えられており、乗客のイニシャルや運行ステータスなどを外部に表示する。Gravityの車内スクリーンには、ロボタクシーが認識している周囲の状況や走行予定ルートが表示され、歩行者の回避、信号での減速、車線変更、乗客の降車といった動作も可視化される。演算基盤にはNVIDIAのDrive AGX Thorが用いられ、リアルタイムAI処理とシステム統合を担っている。
Sony Honda MobilityがAfeela Prototype 2026を公開、2028年の量産を目指す
CES 2023以降、Sony Honda Mobility(SHM)は、自社のモビリティプロジェクトの進化を段階的に披露してきた。車両ブランドはAfeelaで、初期コンセプトの公開から技術アップデート、価格発表に至るまで情報が拡充されている。SonyとHondaは2022年に合弁事業を設立した。SHMは、「車両はドライバー中心の機械から、ユーザーの嗜好や感情を理解し、モビリティにおける空間と時間の価値を最大化するインテリジェントなパートナーへと進化する」との考えを示しており、Afeelaはこのビジョンを支える設計となっている。
2026年には、SHMは量産前モデルとなるAfeela 1を展示し、初回の納車が同年中にカリフォルニア州で開始される見通しであることを認めた。2027年にはアリゾナ州での販売も追加される計画で、日本向けの納車は2027年上半期に予定されている。車両に関する最近の動きとして、SHMはAfeela Studioのショールームを開設し、各地で展示イベントを開催してきた。これらのイベントには累計で10万人超が来場し、車内デモンストレーションは2万4,000件以上に上ったという。SHMによれば、試作生産は2025年第3四半期に開始されており、車両はHondaの米オハイオ州イーストリバティ工場で生産されている。さらに2026年第2四半期にはAfeela Studio and Delivery Hubを2ヵ所、カリフォルニア州のフリーモントとトーランスに開設予定である。Afeela Advanced Accessは、2025年1月に予約受付を開始した早期予約者向けの新たな体験プログラムで、試乗イベントは2026年後半に実施される計画となっている。
Afeela 1の量産前モデルと併せて、SHMは新たな車両となるAfeela Prototype 2026を公開した。Prototype 2026は「早ければ2028年」に量産化される予定で、公開された画像からは、全高を高めたセダンコンセプトであることがうかがえる。新たなプロトタイプはAfeela 1のデザイン要素を継承しており、より高いベルトラインとショルダーラインに合わせてフロントフェイスも高く設計されている。ルーフラインは、角張った従来型のSUVやCUVというより、SUVクーペに近い造形となっている。SHMはAfeela Prototype 2026の詳細について多くを明らかにしていないが、外観上はAfeela 1をベースとした派生モデルと位置付けられる。駆動系についてもAfeela 1と同様の仕様になるとみられる一方で、両モデルの量産時期には約2年の差があることから、機能や技術面ではさらなる進化が盛り込まれる可能性が高い。
SHMはまた、2024年にQualcommとの協業を認めたのに続き、次世代の電気電子アーキテクチャに、Qualcomm TechnologiesのSnapdragon Digital Chassisを将来的に採用する方針を明らかにした。SHMは「将来を見据えた視点で最先端のプラットフォームを継続的に採用することで、AIを中核とした次世代モビリティ体験の創出を目指す」としている。Afeelaの車両には、Vision-Language Modelを用いたAfeela Intelligent Driveによるレベル2+相当の先進運転支援機能が発売時に搭載される予定で、将来的にはレベル4を目指すが、具体的な時期は示されていない。車載パーソナルアシスタントであるAfeela Personal Agentには、自然な対話体験を実現するためにMicrosoft Azure OpenAI Serviceが活用される。さらに、Afeelaの共創プログラムでは、車載エンターテインメント開発に必要な情報が開発者に提供される。AfeelaはAndroidアプリケーションおよび車載インフォテインメント向けに、クラウドAPIと開発環境の構築を進めている。Afeelaは、「これにより、車内体験をさらに変革する、まったく新しいモビリティアプリケーションの開発が可能になる」としている。
展望と影響
CESは自動車業界の年間カレンダーにおける重要イベントではあるが、展示会全体としては、車両分野以外のコンシューマエレクトロニクス関連のニュースや技術が占める比重のほうが大きい。初日に発表された内容には、パーソナライゼーションの高度化、車載パーソナルアシスタント、車内エンターテインメント向けの先進AIといった共通のテーマが見られた。これらはいずれも業界が数年来取り組んできた分野であり、CES 2026での発表は進化的な内容との印象を与える。「シンプルな」車載音声インタラクションはすでに解決済みとの認識が広がる中、車載アシスタント開発の次の段階では、より複雑なやり取りや、ドライバーや乗員の意図を推測する可能性に焦点が移りつつある。
自動車メーカーやサプライヤーごとに、車両、技術、ブランドによって具体的な実装や展開には違いがあるものの、多くのメーカーはすでに車載アシスタントの第1世代ソリューションの導入を始めている。CES 2026で発表された進展内容は、こうした既存のソリューションを基盤とするものだ。車載パーソナルアシスタント技術や自然言語対応は、より広範に利用可能となりつつあり、CESはサプライヤーや自動車メーカーにとって、技術の進化や次の段階に向けた開発成果を披露する場を提供している。
CESはこれまで完成車の公開の場となることもあったが、2026年に関しては、新たな市販モデルを前面に打ち出す発表はおおむね控えられている。Mercedes-BenzはGLCを米国で初めて展示しているものの、車両自体はすでに公開済みであり、今回も技術面が主な焦点となっている。BMWによるAlexa+の発表も、2025年9月に公開されたiX3に関する理解をさらに深める内容となった。SHMが新たなプロトタイプを公開した動きも、これまでの同社の活動の延長線上にある。SHMは、将来的にレベル4の自動運転を実現し、移動中のエンターテインメント提供を主眼とした車両の開発を目標としており、従来型のモーターショーには参加してこなかった。Afeelaブランドは内向き、すなわち車内体験を重視したプロダクトであり、外観デザインや走行性能ではなく、コンテンツを通じて顧客を楽しませることを目指している。
Changan、タイ生産EVの欧州向け輸出を開始
Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)
Changanがタイのラヨーン工場で生産した乗用車の欧州向け輸出を開始した。Changanによると、タイから欧州への初回出荷はDeepal 05を含む500台で構成されている。中国の自動車メーカーである同社は、5月にタイでの生産を開始した。同工場では現在、タイ市場向けおよび輸出向けにS05を生産している。
重要ポイント:Changanは欧州ですでにDeepal S07のミッドサイズSUVを投入している。S05は2026年上半期に欧州の10ヵ国以上で顧客に提供される予定だ。S05は中国市場ではバッテリー電気自動車とレンジエクステンダー式電気自動車の両パワートレインが設定されているが、2026年の欧州市場向けモデルでレンジエクステンダー式電気自動車パワートレインが提供されるかどうかは不明である。欧州で販売されているS07は、後輪駆動のバッテリー電気自動車である。
Mercedes-Benz、Geely出資のQianli Technology向け投資を完了
Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)
Mercedes-Benz Groupが、中国のテック企業であるChongqing Qianli Technologyの株式3%を取得した。取引額は13億4,000万元(1億8,790万米ドル)に上る。Qianli Technologyが発表した声明によると、同社の筆頭株主であるChongqing Lifan Holdingsは、Qianli Technologyの株式1億3,563万株をMercedes-Benzに譲渡した。Mercedes-Benzは今後12ヵ月間、保有比率を引き下げないことを約束している。Geelyは2020年にLifan Technologyの再編を主導した。Lifanは2025年初頭に社名をQianli Technologyへと変更し、それ以降、自動車製造からスマートキャビンおよび自動運転システムの開発へと事業の軸足を移し始めている。
重要ポイント:Mercedes-Benzは近年、中国市場向けモデルへのローカライズ技術の導入を強化している。GeelyがQianli Technologyの戦略的パートナーであることから、今回のQianli Technologyへの投資は、新型車への自動運転技術の展開をめぐって、GeelyおよびQianliとの協業を強化する取り組みの一環と受け止められている。Qianli Technologyが開発したGeelyの自動運転ソリューションであるG-Pilotは、すでにGeely、Galaxy、Zeekr、Lynk & Coの各ブランドに属する複数のGeely車種に採用されている。
東京オートサロン2026:スズキとホンダが出展内容を発表
Nitin Budhiraja(シニアアナリスト-オートモーティブ)
スズキとホンダが、2026年1月9日から11日まで千葉県・幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に向けた出展内容を発表した。ホンダのブースは「Honda Sports DNA」をテーマに掲げ、複数の注目モデルを展示する。主な見どころとしては、ホンダ・レーシング(HRC)のモータースポーツの知見を投入して仕上げた Civic Type Rの新バリエーションを初公開する「CIVIC TYPE R HRC Concept」、先に発売されたPreludeをベースにHRCパーツを採用し、ハンドリング性能を高めた「PRELUDE HRC Concept」、そして、より爽快な走りを実現する新開発のS+シフト制御技術を初披露する「CIVIC e:HEV RS Prototype」が挙げられる。このほか、2026年のSUPER GTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」や、過去のSUPER GTシーズンで実際に使用されたNSX-GTを用いたeモータースポーツのレーシングシミュレーターも展示される。一方、スズキは「Life with Adventure」をテーマに、コンセプトカー5台を含む計9モデルを東京オートサロン2026で披露する。注目モデルには、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」とコラボレーションした「Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition」および「" and "DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition」が含まれる。そのほか、アウトドア撮影向けにカスタマイズされた「New XBEE Nature Photographer」、2025年のENEOSスーパー耐久シリーズに参戦したAutoLaboレーシングチームのSwift Sport、そして2025年12月19日に発表された改良型「SUPER CARRY」の初披露も予定されている。
重要ポイント: 東京オートサロンは、1983年の初開催以来、カスタマイズカーを中心とした年次重要イベントとして位置づけられてきた。自動車メーカーにとっては、最新のイノベーションやカスタマイズモデルを披露し、最先端技術を幅広い業界関係者に示す場となっている。トヨタ自動車、マツダ、日産自動車、ダイハツ工業といった他の国内メーカーも、東京オートサロン2026への出展内容を発表している。
GACとDongfeng、Huaweiと共同開発の新型車を2026年発表へ
Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)
中国の自動車メーカーであるGAC(広州汽車集団)とDongfeng(東風汽車)は、Huaweiと協業し、新たな電気自動車(EV)プログラムを進めている。DongfengとHuaweiが共同で立ち上げたブランド「Yijing」では、そのプロトタイプ車両が12月22日に生産ラインから出荷された。Dongfengはすでに、この新型車がフルサイズのスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)であり、来年4月に開催される北京モーターショーで初公開される予定であることを発表している。一方、GACとHuaweiが立ち上げたブランド「Qijing」は、2026年6月に初のモデルの納車開始を目指している。GACによると、この新型車はプレミアムワゴンで、Huaweiのレベル3自動運転システムを搭載する予定だという。
重要ポイント: Huaweiが中国の自動車メーカーとの提携を拡大するなか、同社のOEMパートナーが立ち上げた各ブランドには、競合との差別化という課題が突き付けられている。現在、中国市場では約30車種がHuaweiのQianKun ADS(自動運転システム)を搭載しており、価格帯は15万元から100万元に及ぶ。QijingとYijingの両ブランドは、Huawei主導のHarmony Intelligent Mobility Alliance(HIMA)に属するモデルとの競合を避けるため、独自の販売ネットワークを構築する方針だ。HuaweiのQianKunインテリジェント車両ソリューションは、これら2つの新ブランドの今後のモデルに採用される予定である。
NHTSA長官、米国の安全基準改定に向けた目標を提示
Stephanie Brinley(アソシエイトディレクター)

Getty Images
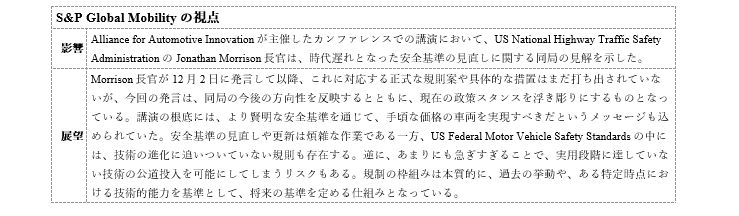
Source: Getty Images
従来型の自動車OEMは、単に車両を製造・販売するビジネスから、アップグレード可能なプラットフォームを販売し、コネクティッドカーサービスのサブスクリプションや、software-as-a-service(サービスとしてのソフトウェア、SaaS)やmobility-as-a-service(サービスとしてのモビリティ、MaaS)のユースケースなど、継続的な収益源を創出する方向へと、実質的に重点を移しつつある。
車両のソフトウェア定義化が進むなか、常時かつユニバーサルなコネクティビティによって、車両は周囲の環境と通信しリアルタイムでデータを収集してクラウドへ送信できるようになっている。こうしたデータを活用することで、コネクティッド機能およびサービスが提供され、無線アップデートによって継続的に強化されていく。従来のコネクティッドサービスに加え、リモート充電や車両ステータスデータを用いた最寄り充電ステーションの検索といった充電関連をはじめ、EV特有のデジタルサービス群も新たに台頭している。
Alliance for Automotive Innovation(自動車イノベーション協会)が主催したカンファレンスでの講演において、US National Highway Traffic Safety Administration(米国道路交通安全局、NHTSA)のJonathan Morrison長官は、時代遅れとなった安全基準の見直しに関する同局の見解を示した。この講演内容は、NHTSAのウェブサイトにも掲載されている。Morrison長官は9月に任命されたばかりで、就任からまだ数ヵ月しか経っていない。
Morrison長官は、NHTSAの基準は本来、特定技術に依存しない形で策定されていることを認める一方、多くの規制は当時の状況を前提に定められており、車両技術の進歩によって、一部の要件はもはや意味をなさない、あるいは逆効果になっていると指摘した。同長官はこうした規制を、人間の体に存在するものの実際の機能を果たしていない痕跡器官になぞらえ、「痕跡的な規制(vestigial regulations)」と表現した。Morrison長官は次のように述べている。「こうした痕跡的な規制は、硬直化しやすく、想定外の形で業界に影響を及ぼす傾向がある。時間の経過とともに連鎖的な影響を生むこともある。やがてそれらは、車両設計とは何かという基本的な考え方の中に組み込まれ、チェック項目が一つ増えるという形で定着していく。そして、そのチェックが一つ増えるたびに、メーカーが望むのであればより効率的かつ効果的に安全要件を満たし、さらにはそれを上回る新たな手法を設計することもできるはずの機会を、私たちは一つずつ失っていくことになる」
Morrison長官は具体例として、端子に12.8Vの直流電圧を印加した際の性能要件を定義している照明関連の基準を挙げた。この規則は、自動車メーカーが48Vアーキテクチャへ移行しようとする場合に、複雑性とコストを増大させる要因となっている。当該基準が策定された当時、48Vアーキテクチャは想定されていなかった。同長官は、こうした規則の一部については、通常7年程度を要するプロセスよりも迅速に是正できると述べ、次のように語っている。「安全上の便益がなく、議論の余地も少ない痕跡的な規制を廃止し、その事実を示すことができれば、このプロセスははるかに単純かつ迅速になる」。こうした見直しは、自動車業界に便益をもたらすと考えられる。
Morrison長官は、5月に16の規則から不要な文言を削除することを提案した過去のプログラムにも言及し、「それらの変更の大半は小規模なものだったが、今後は、より実質的な措置によって、その進展をさらに積み重ねていきたい」と述べている。また、現行の一部規制が、人が車両を操作することを前提に策定されているため、自動運転車の開発を妨げている点にも触れた。さらに、Morrison長官は次のように指摘している。「新たな車両技術がフリートに浸透するには数十年を要する。一方で、私たちは今すぐ交通死亡者数を減らす必要がある。そのため、広範な義務化を伴わない技術や法制度による『後押し』によって、ドライバーが自発的に正しい行動を取るよう促す行動安全プログラムの強化に注力している」。NHTSAでは、行動安全計画(Behavioral Safety Plan)を策定中である。この計画には、地域の安全関連法規の執行を支援するNHTSAの啓発キャンペーンの強化に加え、「州および地方の検察官や裁判官に対する研修の拡充」や、「模範的な交通取締り警察官に対する社会的評価の拡大」などが含まれる。Morrison長官は最後に、次のようにまとめている。「大事な点として理解してほしいのは、新しい車ほど安全であるという事実を私たちが認識しているということだ。私たちは、世界でこれまでにないほど安全かつ効率的な車両を手頃な価格で実現できるよう、自動車メーカーが自由にイノベーションを進められる環境を整えたい」。なお、NHTSAはこれまでにも、自動運転車に関連する安全基準への対応を強化する計画を発表している。
展望と影響
Morrison長官が12月2日に発言して以降、これに対応する正式な規則案や具体的な措置はまだ打ち出されていないが、今回の発言は、同局の今後の方向性を反映するとともに、現在の政策スタンスを浮き彫りにするものとなっている。講演の根底には、より賢明な安全基準を通じて、手頃な価格の車両を実現すべきだというメッセージも込められていた。安全基準の見直しや更新は煩雑な作業である一方、US Federal Motor Vehicle Safety Standards(米国連邦自動車安全基準、FMVSS)の中には、技術の進化に追いついていない規則も存在する。逆に、あまりにも急ぎすぎることで、実用段階に達していない技術の公道投入を可能にしてしまうリスクもある。規制の枠組みは本質的に、過去の挙動や、ある特定時点における技術的能力を基準として、将来の基準を定める仕組みとなっている。
ドナルド・トランプ大統領の政権からの包括的なメッセージとして、車両の価格がもっと手頃になれば、人々の新車購入ペースは加速し、古い車両が市場から姿を消すペースも速くなることで、結果的に道路の安全性が高まる、という考え方が示されている。Morrison長官もこのメッセージを引き継ぎ、次のように述べた。「新しい車ほど安全であること、そして、犠牲者が新しい車両に乗っていれば防げた事故が相当数あることを、私たちは認識している。したがって、安全性を高め、フリートの更新をより迅速に進めるという点で、私たちと皆さんの利害は100%一致している」
米国議会は、車両価格の手頃さを議題とする公聴会を2026年1月14日に開催する予定であり、安全技術も議論の一部となる見通しである。NHTSAはFMVSSやCorporate Average Fuel Economy(企業別平均燃費基準、CAFE)規制、ならびにリコールに対する監督権限を有しており、交通安全の向上に向けた取り組みを支援している。一方でNHTSAは、例えば州レベルにおける速度規制や、飲酒運転・わき見運転を禁止する法律を制定・執行する権限は持っていない。ただし、地域レベルでの取り組みを後押しするプログラムや、ドライバーの意識向上を目的とした啓発キャンペーンを支援するためのリソースは有している。
車両基準を変更するにあたり、米国議会はNHTSAに対し、技術動向や実現可能性の分析を行い、パブリックコメントを踏まえた上で、適切な規則を評価・決定するよう指示している。NHTSAの基準を改定するには通常およそ7年を要する。また、NHTSAは飲酒運転に関する州レベルの法律を直接定める権限は持たないものの、米国議会は、そもそも飲酒状態での運転を防止し得る車両技術について評価を行い、最終的には義務化するよう同局に命じている。ただし、この規則は現時点ではまだ最終決定には至っていない。
Huaweiのスマートカーアライアンス、統一エコシステムを構築へ
Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)
Huaweiが支援するHarmony Intelligent Mobility Alliance(ハーモニー・インテリジェント・モビリティ・アライアンス、HIMA)は12月9日、参加ブランドが技術展開に関する統一基準策定を目指すとともにリソースを共有することで、中国の新エネルギー車(NEV)市場における競争力を強化していく方針を発表した。HIMAは現在、Huaweiと同社のOEMパートナーであるSeres、Chery、BAIC、JAC、SAICが共同で立ち上げた5つのブランドで構成されている。上海で開催されたイベントではHuaweiと同社の自動車関連パートナー各社の幹部が、ソフトウェアプラットフォーム、サービスネットワーク、充電インフラ、マーケティングを対象として協業を深化させていくと述べた。今回の協業は、HIMAの傘下で展開されるAITO、Luxeed、Stelato、Maextro、Shangjieの全ブランドを対象としている。Huaweiのスマートカー事業責任者であるYu Chengdong氏は、統一基準の導入とリソース共有により、ユーザーに対してより「一貫した価値」を提供できるようになると述べている。また、この取り組みは、HIMAの戦略が個別の取り組みからエコシステム主導の協業へと転換したことを示すものだと強調している。HIMAは11月に81,864台を出荷しており、前年同月比で89.6%の増加となっている。
重要ポイント: HIMAの累計出荷台数は12月5日時点で100万台を超えている。成長の次段階では、スマートキャビンやインテリジェントドライビングシステムからクラウドベースのサービスに至るまで、自動車メーカー各社がブランド横断で共通の技術ソリューションを展開できる統一プラットフォームの構築を目指す。HIMAはまた、自前の充電インフラおよび共通のアフターセールスネットワークを構築するため、リソースの集約も進める方針だ。AITOは、HuaweiとSeres Groupが2021年に立ち上げたブランドで、現在HIMA傘下で最も販売台数の多いブランドとなっている。AITOブランドの2024年累計出荷台数は387,100台に達し、前年同期比で268%増となっている。
Ford、欧州市場向け新型PHEVにBroncoの名称を採用へ
Tim Urquhart(プリンシパルアナリスト)
Ford(フォード)が欧州市場向けに開発している新たなプラグインハイブリッド車(PHEV)には、Bronco(ブロンコ)のネームプレートが付与される見通しだ。Automotive News Europeが報じている。同報道によると、このモデルは角張ったデザインを持つCセグメントSUVで、タフかつアグレッシブなプロポーションを採用し、スペインの同社バレンシア工場でKuga(クーガ)と並行して生産されるという。2027年にデビュー予定で、サイズはKugaよりやや小さく、米国市場で高い販売実績を誇るBroncoおよびBronco Sportとは異なり、米国市場向けにオフロード志向を強化したこれらのモデルとの共通点はないとされる。
重要ポイント:Broncoは西欧市場で競争力を持つ製品になる可能性を秘めており、フォードが欧州戦略を転換したことを示す象徴的なモデルといえる。かつては2030年までにバッテリーEV(BEV)専業ブランドとする方針を示していた同社だが、昨年11月にこの欧州戦略の転換を発表している。当初はVWのMEBプラットフォームを採用したExplorer(エクスプローラー)およびCapri(カプリ)の電動DセグメントSUVの生産を開始したが、現時点ではいずれも販売は低調にとどまっている。BroncoはFord Europeにとって必要とされていた現実路線への回帰を象徴する存在であり、Fiesta(フィエスタ)とFocus(フォーカス)の生産終了後、主力となる量販モデルの拡充を求めてきたディーラーにも歓迎されるだろう。
中国本土EV事業Avatr、香港でIPO申請
Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)
Chongqing Changan Automobile(重慶長安汽車 、Changan Auto)の新エネルギー車(NEV)子会社であるAvatr Technologyが香港特別行政区で新規株式公開(IPO)を申請した。Avatrが香港証券取引所に提出した資料によると、IPOによる調達資金は、新モデルの開発、次世代車両アーキテクチャの構築、ブランド力および販売ネットワークの強化、ならびに運転資金の補填に充てられる予定だ。2025年6月末時点で、Changan AutoはAvatrの株式41%を保有する筆頭株主となっている。Avatrは2022年8月に初のモデルとなるAvatr 11を発売した。同社は現在、スポーツ用多目的車(SUV)2モデルとセダン2モデル、計4モデルを販売している。S&P Global Mobilityのデータによると、Avatrの販売台数は2023年に2万6,694台、2024年に6万4,451台となっている。エントリーモデルである06と07の2モデルを追加したことで、Avatrの販売は2025年も拡大を続けている。2025年1月~10月の販売台数は9万7,369台に達したが、前年同期は3万9,236台だった。
重要ポイント:Avatrは、香港上場に関する具体的な目標については明らかにしていない。EV市場の過密化に対する懸念や、中国自動車産業がデフレ圧力への対応に苦慮していることを背景に、中国の新興NEVメーカーにとって資金調達環境は一段と厳しさを増している。2025年上期のAvatrの純損失は、前年同期比11%増の16億元(2億2,600万米ドル)に拡大した。2022年~2024年の累計純損失は97億元に達している。
長安汽車、現代自動車の中国工場を買収
2025年12月1日
Abby Chun Tu Principal Research Analyst
中国の自動車メーカー長安汽車は、北京現代がかつて運営していた工場でディーパルのモデルを生産する。現代自動車と北京汽車の合弁会社(JV)「北京現代」は、事業再編の一環として2021年に工場での生産を終了した。その後、同工場は、重慶市の国有企業に16億2,000万元の取引価格で売却された。北京現代は現在、中国で北京と滄州の3つの自動車製造工場を操業している。
重要性: 長安の新エネルギー車(NEV)ブランドであるディーパルは現在、重慶と南京で自動車の組み立てを行っている。2024年は、中国での商品ラインナップの充実により、売上が急成長した。ディーパルによると、重慶工場の年間設計生産能力は15万台である。2024年の生産台数は110,092台に達した。コンパクトスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)「ディーパルS05」の需要拡大を背景に、2025年には14万台超の生産を見込んでいる。2025年のディーパルの販売目標は前年比50%増の36万台であった。2025年の最初の10ヶ月間で、輸出を含むディーパルの販売台数は259,728台に達した。
零跑汽車、エントリーモデルの電気SUV「A10」を公開
2025年11月27日
Abby Chun Tu Principal Research Analyst
中国の自動車メーカー、零跑汽車が中国でスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)「A10」を公開した。同電気自動車は、零跑汽車のエントリーレベルA製品シリーズの最初の製品である。零跑汽車はまだ「A10」の詳細な仕様を発表していない。同モデルは、車体の長さが4.2メートル以上、ホイールベースが2.6メートル以上になる見込みである。零跑汽車によると、「A10」の最大航続距離はCLTC (China Light-Vehicle Test Cycle) で500 kmであるという。このモデルには、LiDARベースの自動運転システムと、クアルコムのスマートコックピットチップSnapdragon 8295を搭載したスマートキャビンシステムが搭載される。
重要性: 零跑汽車は2026年に100万台の販売を目指している。売上目標は、4つの製品シリーズの見通しを反映している; A, B, C and D。零跑汽車の2025年の販売台数はすでに50万台を超えており、年末までに通年目標を達成している。「A10」のようなエントリーモデルは、ここ1年でBEVの人気が高まっている中国のサブコンパクトSUV市場で、零跑汽車の売り上げを伸ばす上で重要な役割を果たすだろう。このモデルはBYDの「Yuan Up」や吉利汽車の「Xingyuan」などと競合することになる。「Yuan Up」の上限は約8万元から、「Xingyuan」は7万元からの価格である。零跑汽車はまた、2026年に欧州で「A10」を発売し、世界市場の小型車購入者にアピールするためにハッチバックEV「Lafa5」を一緒に提供すると発表した。
ニオのファイアフライブランド、右ハンドル市場での拡大を目指す
2025年11月24日
Ian Fletcher Principal Analyst
ニオは、この構成の製品の生産を開始した後、右ハンドル市場へのファイアフライブランドの拡大に取り組んでいる。同自動車メーカーは声明で、最初の出荷はシンガポールに向かうと述べた。しかしながら、ロイターは、ファイアフライブランドの社長であるダニエル・ジン氏は、同ブランドが「短期的に関税障壁のない国での取り組みを大幅に強化する」と述べたと伝えられており、英国、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア諸国を主要市場として取り上げた。ジン氏はこれらの市場での販売台数の見通しについては明らかにしなかったが、消費者からの評判を高めるため、販売ペースは緩やかになる可能性が高いと述べた。
重要性:ニオは昨年末のイベントでファイアフライを発表した。当初は中国で発売され、その後ノルウェー、オランダ、ベルギーなど欧州の一部市場にも供給されてきたが、欧州では中国製電気自動車 (BEV) に対するEUの関税が発動され、販売台数は限られていた。そのため、右ハンドルモデルの生産を開始し、関税負担のない市場に焦点を当てている。しかしながら、ニオは中国の他の新しい電気自動車とは異なり、ファイアフライをプレミアムオプションとして位置付けようとしている。実際ジン氏によると、シンガポールではファイアフライの価格はこの分野の他の車よりも高い。同氏はまた、「代理店との交渉の中で当社が強調したのは、ファイアフライを中国製EVと単純に考えることはできない...ポジショニングを下げたら終わりだということである」と語った。S&P Global Mobilityは、2026年のファイアフライの販売台数を45,600台と予測しているが、その87%は中国での販売となる見通しである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ボルボ・カーズ、利益率改善に向け吉利汽車との提携強化を発表
2025年11月17日
Ian Fletcher Principal Analyst

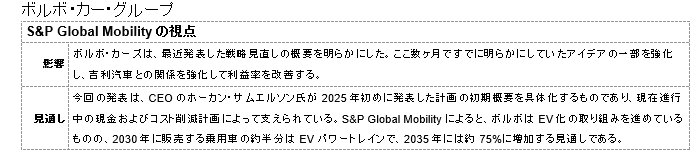
ボルボ・カーズは先週スウェーデンで開催したイベントで、最新の戦略的アップデートを発表し、その中で、これまでに明らかにしていたイニシアティブの一部と、利益率改善につながる吉利汽車との提携拡大の意向を具体化した。
プレゼンテーションで注目されたのは、2026年1月21日に最終的に近い将来発表されるボルボ「EX60」である。これは同自動車メーカー初のバッテリー駆動のミッドサイズクロスオーバーであり、バッテリー駆動のスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) カテゴリーでは既にいくつかの製品を展開しているが、このモデルの投入により電気自動車 (BEV) の市場規模は200%拡大することになる。この車の仕様は公表されていないが、同自動車メーカーは、この技術に乗り換えることで潜在的な所有者が抱くであろう多くの懸念に対処すると主張している。これには、内燃機関 (ICE) 乗用車と同程度の航続距離、平均的なトイレ休憩と同程度の速度での充電、同サイズのXC60 T6プラグインハイブリッド車 (PHEV) と同レベルの価格設定などが含まれるが、実現可能な販売台数は明らかにされていないものの、より高い利幅が見込まれる。
また、「EX60」のベースとなっているSPA3プラットフォームも拡張されている。ボルボはこれを「妥協のないEVアーキテクチャー」と呼び、「これまでにない利点」をもたらすと主張している。同社によると、従来のSPAプラットフォームとは異なり、このアーキテクチャはサブコンパクトなBセグメントから大型で豪華なFセグメントまで、幅広いサイズカテゴリで使用できるように設計されており、スケーラビリティの向上とコスト削減が期待できるという。その特徴の一つは、「メガキャスティング」プロセスの使用である。ボルボによると、「EX60」ではリアフロアに使われていた100個の溶接部品が単一鋳造品に置き換えられ、コストが35%削減されるという。また、バッテリーの設計・組立を自社で行うことで、25%のコストダウンを実現したという。また、近年開発された部品の中には、コストを下げたものもあると言われている。確かに、ボルボによると「EX60」に搭載される第3世代のバッテリーは、2024年に発売された第2世代に比べてキロワット (kWh)時あたりのコストを25%削減でき、第2世代は、2020年に発売された第1世代に比べてコストが15%向上したという。第3世代のバッテリーは第2世代と比べて、エネルギー密度が20%、kWhが10%向上すると同時に、充電時間が15%短縮され、製造時のカーボンフットプリントが40%削減されるという。もう一つの例は、自社開発の電気駆動システムの進化である。全輪駆動仕様では、2021年に発売した第1世代と比較して、2023年に発売した第2世代は16%のコストダウンを達成しているが、2025年に発売した第3世代は18%のコストダウンを達成している。さらに、第3世代の電気駆動システムは、第2世代よりも35%強力で、効率が1パーセントポイント向上し、重量は11%削減されている。
それを支えてきたのが、自社開発のハードウェアシステムによる垂直統合と、自社開発のソフトウェアによる水平最適化である。これは単一のソフトウェアスタックとコンポーネントのプラットフォームを中心としており、最終的にはすべての製品に展開される予定で、同社は「ソフトウェア・デファインド・ビークル [SDV] における当社のリーダーシップを強調するものである」と述べている。同社は、顧客に複数のメリットを提供するだけでなく、企業が製品のライフサイクルを通じてより迅速に製品をアップデートできるようになると指摘しており-1年に最大4回のアップデートが、本番稼働中または無線アップデート (OTA) を通じてインストールされ-迅速な開発と低コストを同時に実現できる。
ボルボは近く発売される「EX60」の仕様を公表していないが、主な競合車種として同社が見ているアウディ「Q6 e-tronクワトロ」、アウディ「SQ6」、BMW「iX3 50 xDrive」、メルセデスベンツ「GLC 400 4Matic」のデータをスライドに示し、「「EX60」は主要な分野で主な競合車種に打ち勝つと当社は確信している」と述べている。
しかしながら、より高いレベルの電動化は依然として自動車メーカーの戦略の重要な部分であるが、プレゼンテーションは、ICEを構成要素の一部として使用するパワートレインを次の10年に渡って提供する計画について、先週CEOであるサミュエルソン氏が報告したコメントを強調した。実際、同社の最高戦略・製品責任者であるマイケル・フレイス氏が行ったプレゼンテーションでは、同社は現在、当初の予定よりも長いBEV 100%への橋渡しをしていると述べた。これはSPA1とCMAのプラットフォームベースのモデル用にアップグレードされたPHEVパワートレインでサポートされ、一方「Gen 2 PHEV」と同社が呼ぶものは、航続距離拡張型電気自動車 (EREV) として知られるバックアップエンジン付きの電気自動車である。同社はこれを、顧客がBEVを通じてパワートレイン技術の利点の大部分を活用しているので、最も消極的な顧客をBEVに引き込むための重要な足がかりになると考えている。中国では「XC70」として発売されている。
吉利汽車とのシナジー拡大計画について、サミュエルソン氏は、中国ブランドが世界の自動車業界で大きなシェアを獲得している競争的な市場環境の中で、吉利汽車との独特な協業が明らかな強みになっているとの見方を示した。ボルボは、中国で最近発表した「XC70 EREV」を含む過去の製品提携を基に、吉利汽車との提携が製品の迅速な市場投入とコスト削減の鍵になるとしている。コスト効率の改善は、購入における節約とシナジー効果に起因し、共同交渉と共通の供給者パネルを通じて規模を活用することによって部分的に支援される。ボルボ最高産業事業責任者であるフランチェスカ・ガンボーニ氏によると、ボルボは現在、吉利汽車と共通のサプライヤーを130社持ち、部品費用の約75%を占めているが、今後数年間でこれを50%増やし、共通サプライヤーを200社程度にしたいと考えており、その中で、共同交渉や、見積依頼書 (RFQ) プロセスの拡大により、吉利汽車のサプライヤーも取り込むことで、コスト削減を8%まで高めたいと考えている。規模だけでなく、「should cost」-交渉開始前の部品の推定コスト-を共有することで、サプライヤーとのコストを最小限に抑えることができる。また、「文化とベストプラクティスの共有」に加えて、吉利汽車とのコストベンチマークからも利益を得られると考えており、中国の自動車セクターにおける開発のスピードと機敏性、共通性の向上、回復力の向上、破壊的な影響の軽減に注目している。これにより構造的コストを削減し、利払前・税引前利益 (EBIT) への寄与度を2%~3%と見込んでいる。
顧客ニーズに応えて利益を上げるための同自動車メーカーの取り組みを支援するとともに、同自動車メーカーは、3つの主要分野に焦点を当てた販売モデルの変更を行っている:シンプルさ、透明性、精度。シンプルさは、顧客に「包括的なサービス」ができるだけでなく、指定できるトリミングレベルとオプションの数を減らすことができる。透明性に関しては、顧客に透明な価格設定のオンライン購入オプションを提供する。精度は、インスタントオプションを含め、顧客に明確な納期を提供することを意味する。この販売モデルは、2026年1月からスウェーデンで提供を開始し、シンプルさと透明性を追求した上で、2026年第1四半期から第2四半期にかけて、即納または受注生産による正確な配送オプションを提供する予定である。オプションとして即納を提供する計画にもかかわらず、同社は顧客への配送を迅速化することで在庫レベルを10%削減できると見込んでおり、これは、パートナーとの在庫のオフバランス化の集中管理、バリエーションの少ないシンプルな提供構造、AIをサポートする注文から配送までのプロセスによって可能になる。さらに将来的には、AIを活用した「より迅速で透明性の高い対話型の購入決定」の提供を目指している。また、特定の消費者グループへのターゲティング、halo製品市場戦略、オンライン購入オファーと連携した「デジタルおよびシグナルベースの最適化」を通じて、自動車1台当たりのマーケティング費用を最大20%削減することを目指している。これにより、販売車両の簡素化、配送精度の向上、販売車両1台当たりの商業コストの削減に加え、収益性が1%パーセントポイント向上する。電動化計画や新製品、ボルボ・ブランドの強化により、利益はさらに2~3%パーセントポイント増加すると同社は予想した。
ボルボのフレドリック・ハンソン最高財務責任者は、上記の施策により長期的に8%以上のEBITマージンを達成できる体制が整うと述べているが、達成時期は明らかにしていない。しかしながら、同氏は、同社が製品の拡大に支えられた収益性の高い「電動化された成長」と、「EX60」による対応可能市場の成長を含む-SPA3から得られる利益-およびEREVを通じた電動化への橋渡しの拡大により-2%から3%のEBIT改善を見込んでいると付け加えた。同時に、中国製品の供給拡大にもつながる吉利汽車とのシナジー効果 や変動費の削減により、EBITは2%~3%改善すると見込んでいる。また、「固定費規律」による間接的なコスト削減により、1%から2%のEBIT改善を見込んでおり、単一のソフトウェアソリューションを持ち、ハードウェアの複雑さを軽減してエンジニアリングの効率化を図る計画;と「商業的な再生を実現する」。EBITの2%から3%の改善には、過去の製品投資などの減価償却費や電化・SDVプラットフォームへの多額のインフラ投資が足かせとなる。ボルボは「力強いプラスのキャッシュフロー」を目指しているおり、スロバキアのコシツェに新設したBEV工場のほか、SDVプラットフォーム、電動モーター、メガキャスティング、「セルツーボディ」車用バッテリーの導入など、自動車の主要エンジニアリング分野に最近巨額の投資を行っている。すでに投資額が減少している中、ボルボは2027年末までにそれらを完成させる計画であり、それは、投資額がそれ以上に減少するだけでなく、投資の配当を「収穫」することを意味している。
見通しと影響
この発表は、サミュエルソン氏が2025年の第1四半期に復帰した後、ビジネスを軌道に戻す方法についての同氏の当初の概要を具体化するものである。それまでの間、同社は180億スウェーデンクローナのコスト・キャッシュアクションプランを実行していた。これには、サプライヤーとの交渉や吉利汽車とのシナジー効果の拡大、物流事業のスリム化などに伴う変動費の30億クローナ目標が含まれる。さらに50億クローナを、整理解雇プログラムを通じて間接経費を削減することで捻出し、このプログラムは3,000人の雇用に影響を与えたが、コストは当初の予想よりも低いことが判明した。さらに、設備投資と運転資本を100億クローナ削減することを目標としており、これは在庫の削減、計画投資の削減、運転資本の規律によって支えられている。同自動車メーカーの第3四半期決算の発表で、同社は当初の計画よりも早く目標を達成していると述べた。
「EX60」はボルボにとって、特に新しい技術と投資の組み合わせを考えると非常に重要な製品になるだろうが、2030年の積極的な電動化目標を骨抜きにするという同自動車メーカーの決定と、100% BEV達成への橋渡しを延長することで、このモデルが短期的に成功するためのプレッシャーは小さくなるはずである。それでも、ボルボがこれまでに説明してきたように、この車は顧客にとって魅力的な提案になるはずであり、特に、「EX90」や「EX30」が抱えていた厄介な問題を回避することができれば、その魅力はさらに増すだろう。S&P Global Mobiilityは、このモデルの生産がスウェーデンのボルボのトースランダ工場で2026年4月に開始されると予測しているが、初年度の2027年には約61,200台が生産されると予想している。しかしながら、2028年までに中国の大慶、インド、マレーシアでも組み立てを開始し、2030年の世界生産台数は108,000台となる予定である。
中国ではすでに「XC70」が発売されており、世界の他の地域では一部の顧客にとってEREVは完全なBEVへの入り口とみなされているが、ボルボは他の地域での導入には消極的なようである。同社は「XC70」の地域化に関して、「Android」ベースのソフトウェアへの移行や、現地の安全規制および排出ガス規制への適合などの課題を指摘しているが、その理由の一部は、ボルボ「XC60」のアップグレードも予定されていることかもしれない。S&P Global Mobilityは、プログラムコード「V526B」で知られるこの車両が2026年後半に米国チャールストンで組み立てを開始し、2027年第2四半期にトースランダで生産されると予測している。新世代の「XC60」は、引き続きSPA1に支えられ、PHEVのパワートレインをアップグレードすることで、ゼロエミッションの航続距離を伸ばすことができる。さらに、ボルボが販売地の近くで生産する意向であることを考えると、「XC70」の出荷は、特に現在の関税要因を考えると、あまり魅力的な選択肢ではない可能性が高い。2028年後半に生産が開始される予定の大幅なアップデートが施された「XC90」もSPA1を採用しており、進化の一環としてパワートレインがさらに強化される可能性がある。
S&P Global Mobiltyは、この戦略プレゼンテーションに示された情報を吸収し、必要に応じて当社の予測を変更する。しかし、現時点では、当社は2025年の世界販売台数は、過去最高を記録した2024年に比べ、前年比8.3%減の696,200台を見込んでいる。しかしながら、当社は、新製品が市場に投入される今後数年間で成長は回復し、2027年から2028年にかけて75万台以上の販売台数に達すると予想している。また、ボルボは新たな電動化ブリッジに肉付けしたものの、2030年に販売する乗用車の約半数にEVパワートレインを搭載し、2035年には約75%に増加すると当社は予測している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ルノーグループ、ヴァレオとのレアアースフリーモーター共同開発を中止、中国の自動車部品メーカーとの共同開発に切り替える模様
2025年11月13日
Ian Fletcher Principal Analyst
関係筋2人がロイターに語ったところによると、ルノーグループはヴァレオとの間で進めていたEV用のレアアースを使用しないモーターの開発プロジェクトを中止した。ある情報筋は、「ヴァレオとの「EV7」エンジンプロジェクトは中止した」と付け加える前に代わりに「中国のサプライヤーから購入できる固定子を除いて、バリューチェーン全体にわたって完全に社内で行われる」と述べた。関係筋によると、今回の決定はコスト削減の必要性に基づくもので、中国のサプライヤーは競争力のある価格を提示しているという。BEV技術を専門とするルノーグループのアンペレ子会社の広報担当者は、「中国のパートナーになる可能性はある」と述べたが、決定は下されておらず、「プロセスはまだ継続中である」と付け加えた。しかしながら、代表者は「当社はフランスに (固定子を) 設置する可能性を検討している」と述べた。
重要性: ルノーグループとヴァレオは、2022年初頭に新しいレアアースを使用しない電気モーターを開発すると発表した。「E7A」モーターは2028年に発売される予定で、小型のBEVに使用されている現行世代の電気モーターより約25%高い200 kWの出力を実現するとともに、システム電圧を400 Vから800 Vに引き上げ、充電時間の短縮を図る。両社はこのプロジェクトに数年間取り組んできたが、中国のパートナーとの協力を検討するという決定は、中国の上海にある新しいACDC研究開発 (R&D) センターでの取り組みに由来する可能性がある。これまでのところルノーグループへの主な貢献は、先週発表された新世代ルノー・トゥインゴの開発支援であるが、開発期間と部品コストの削減で得た経験を他の分野でも活用したいと考えている。今回のモータに採用されている固定子もその一つであろう。しかしながら、報道によると、中国のサプライヤーの専門技術を活用する可能性はあるものの、電気モーターはフランスのクレオンにあるルノーの工場で組み立てられ、クレオンはすでにルノーグループの電気モーター生産の中心地となっているという。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
中国自動車メーカー、関税の逆風の真っ只中で世界生産拠点を拡大
2025年11月10日
Abby Chun Tu Principal Research Analyst
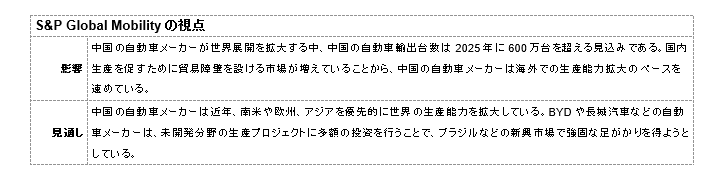
中国の自動車メーカーが世界展開を拡大する中、中国の自動車輸出台数は2025年に600万台を超える見込みである。2025年の最初の第3四半期には、中国本土の自動車メーカーが495万台以上を国際市場に出荷した。新エネルギー車 (NEV) は全体の出荷台数の36%近くを占めた。テスラとグローバル自動車メーカーの合弁会社 (JV) が中国の自動車輸出に貢献しているが、中国の国内自動車メーカーがこの部門の大部分を占めており、奇瑞汽車、BYD、上海汽車が3大輸出企業である。国内生産を促すために貿易障壁を設ける市場が増える中、中国の自動車メーカーは海外での新しい生産能力拡大を追加することに注力している。BYDは10月初め、同社の新しい工場によって生産された1,400万台目のNEVの生産を祝い、ブラジル初の工場の開所式を行なった。式典にはブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領とジェラルド・アルクミン副大統領が出席した。現地で組み立てたBYD Song Proを受け取った大統領は、同自動車メーカーのブラジルへのコミットメントを高く評価し、新工場を「カマカリとバイーアの人々の尊厳の回復」の象徴と呼んだ。総投資額55億レアル (10億米ドル) を投じた新工場は、BYDがアジア以外で最大の投資となり、ブラジル国内で2万人の直接・間接雇用の創出が見込まれる。長城汽車も8月に新しく完成したブラジル工場で生産を開始した。新工場は、メルセデス・ベンツが以前運営していた場所に建設され、中国以外では3番目の長城汽車の全工程生産工場となる。
東南アジアや中央アジアでも、中国との距離が近く、貿易関係が強いことから、この3年間、中国からの投資が流入している。両地域では、中国の5大自動車輸出企業であるBYD、奇瑞汽車、長安汽車、上海汽車、吉利汽車が、自社工場、合弁工場、現地パートナーの製品ラインを含め、南西および中央アジアの製造拠点を19拠点に拡大した。このうち15カ所以上は、中国自動車メーカーの海外進出が本格化した2022年以降に建設された。中央アジア最大の自動車市場であるウズベキスタンでは、2025年の中国自動車メーカーのライトビークル生産台数が前年比で36%増加すると予測されている。同国におけるグローバル自動車メーカーの生産台数が減少している中でのこの増加は、中国自動車メーカーの新興市場への参入が、米国、ドイツ、日本の既存の自動車メーカーに与える影響を示している。東南アジアでは、EVに対する消費者の関心の高まりと地域の大きな自動車需要により、インドネシアやマレーシアなどの国が中国自動車メーカーにとって重要な成長市場となっている。しかしながら、両国とも国内生産を促すため、完全輸入のEVに対する優遇措置を縮小している。例えばマレーシアは完全に輸入した電気自動車 (EV) に対する免税措置を2026年1月1日から廃止し、現地組み立て (CKD) EVは2027年まで優遇税制の恩恵を受ける。インドネシアの完全に組み立てられたEVの輸入に対する税制上の優遇措置も2025年末で終了する。こうした変化に対応するため、BYDや吉利汽車、奇瑞汽車など中国の自動車メーカーはコスト優位を維持するため、現地組立車の生産を拡大している。
欧州では、地政学的な不確実性と高い運営コストが中国企業の投資決定を複雑にしている。中国からのEV輸入の流入を受け、EUは国内産業と欧州ブランドの利益を守るために高額な関税を発表した。しかしながら、中国の大手自動車メーカーは関税の逆風にもかかわらず、同地域での生産拠点拡大で大きく前進した。例えばBYDは、輸入中国製BEVに対するEUの関税を回避するため、欧州に2カ所の生産工場を建設している。BYDはまだ正式な発表をしていないが、第3工場の建設も検討されているという。
BYDと比べると、奇瑞汽車のヨーロッパでの生産開始のアプローチは微妙である。同中国自動車メーカーはスペインの自動車メーカー、エブロEVモーターズと合弁契約を結び、スペインでエブロブランドの自動車を生産する。日産の旧工場を改装した同JVのバルセロナ工場では、奇瑞汽車の技術を採用して開発されたSUV「S400」、「S700」、「S800」の3車種のエブロモデルをまず組み立てる。バルセロナ工場では、ジャエクーとオモダの下でスペインと他の欧州市場向けに奇瑞汽車のモデルも生産する。中国のEVスタートアップはまた、費用のかかるグリーンフィールドプロジェクトにコミットするよりも、パートナーシップを活用してローカライズ計画を迅速に進める傾向がある。零跑汽車はステランティスの支援を受けており、ステランティスのポーランド工場を活用して欧州で車両の組み立てを開始した。同様のアプローチにより、零跑汽車はステランティスの既存のグルン工場を利用して今年末までにマレーシアで生産を開始する予定である。
見通しと影響
中国の自動車メーカーは長年、提携や自社工場への投資を通じて、世界各地で自動車の組み立てを行ってきた。しかしながら、これらの海外生産拠点が貢献する生産量は、まだ大きな規模には達していない。中国の3大自動車輸出企業である奇瑞汽車、BYD、上海汽車の国内生産台数を合わせると、2024年の世界生産台数の95%以上を占めている。奇瑞汽車は、10カ所を超える海外組立拠点と、20年以上にわたるグローバル販売網の構築により、海外生産量第1位となっている。
中国の自動車メーカーは近年、南米や欧州、アジアを優先的に世界の生産能力を拡大している。BYDや長城汽車などの自動車メーカーは、グリーン フィールド生産プロジェクトに多額の投資を行うことで、ブラジルなどの新興市場で強固な関係を築こうとしている。世界第6位の自動車市場であるBYDの新工場は、同国の指導者たちから前例のない注目を集めている。この南米最大の市場は、メルセデス・ベンツとフォードが操業を終了した後、製造業の再生を目指している。こうした状況の中、BYDのバイーア州への投資は、ブラジルが製造業の力を取り戻すための画期的な契約として注目されている。BYDにとってブラジルは大きな成長機会である。BYDは輸出を通じて、南米最大の自動車市場で既に勢いを得ている。2022年から2025年10月までのブラジルでの同中国自動車メーカーの販売台数は172,303台であった。2025年9月だけで、BYDの乗用車の登録台数は9,934台に達し、BYDブランドは5.56%のマーケットシェアを持ち、全国販売台数で第7位となった。しかしながら、中国の自動車メーカーの中には、より慎重に新しい収容能力を追加するメーカーもある。吉利汽車は市場を試すため、一部地域での拡大の初期段階で現地の組み立て業者と提携することを選んだ。吉利汽車の李書福会長兼創業者は6月、重慶で開催された自動車フォーラムで、世界の自動車業界は「深刻な過剰生産能力」に直面しており、吉利汽車は新たな工場を建設しないことを決定したと述べた。
新興国では、中国の自動車メーカーの存在感の高まりも、これらの地域市場のグリーン・トランジションを加速させるのに役立つだろう。BYDの「ドルフィン」や零跑汽車の「C10」、吉利汽車の「ギャラクシーE5」など、中国ブランドの世界市場向け電気自動車の生産拠点はすでに世界各地に割り当てられており、自動車購入者への納入を迅速化している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
シャオミ、YU7の配送待ち時間を10週間短縮
2025年11月10日
Abby Chun Tu Principal Research Analyst
シャオミ自動車は北京工場でYU7の生産を増強し、自動車購入者への納車を迅速化した。中国の経済メディアのランジンガーによると、「YU7」の納期は10週間短縮され、35週間から38週間となったという。「YU7」の最上位モデルである「YU7 Max trim」の納期を32週間から35週間に短縮した。シャオミ自動車は10月に中国で22の新しいショールームを追加し、その数を424に増やし、125都市に及んだ。
重要性: シャオミの10月の納車台数は2ヶ月連続で4万台を超えた。シャオミ初のスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) である「YU7」は、2025年6月の発売以来、好調な受注を維持している。シャオミは2025年の販売目標を35万台としている。現在の生産ペースでは、シャオミは既存の2つのモデルの出荷と2026年の大型高級SUVの登場をサポートするために年間生産台数を約50万台に増やすことができる。253,500元から販売される「YU7」は、シャオミ初のバッテリーEV SUVで、販売開始から最初の24時間で28万件以上の払い戻し不可の予約を受けたとシャオミは述べた。しかしシャオミの北京工場の生産は依然として予想を下回っている。シャオミのアプリによると、「YU7」と「SU7」セダンの配送待ち時間は26週間以上となっている。中国が電気自動車 (EV) 購入時の免税措置を2025年末で終了することを受け、シャオミは2026年に同社の車両を受け取る顧客に最大15,000元の補助金を提供する方針を示した。理想汽車や広州汽車などの自動車メーカーも同様のプログラムを発表しており、2025年第4四半期に顧客に注文してもらうことを目指している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スズキ、グローバル戦略においてフレックス燃料車とバイオガス事業でインドを重視
2025年9月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
スズキ株式会社|施設・運営、経費、企業、研究開発、ライトビークル、テクノロジー、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
スズキ株式会社は、技術戦略2025で、インドを同社のグローバル技術戦略の最前線に位置付けている。Economic Timesの報道によると、日本の自動車メーカーは今年度、インドでフレックス燃料車を発売するとともに、地元の酪農協同組合と協力して革新的なバイオガスイニシアティブを拡大することを計画している。2025年度のスズキのグローバル収益に占めるインドの割合は約41%、利益に占めるインドの割合は約45%であった。フレックス燃料車は複数の種類の燃料タイプ、通常はガソリンとエタノールまたはメタノールの混合燃料で運転できる内燃機関(ICE)を装備している。スズキは、牛糞を原料としたバイオガス生産プラントを開発・建設するバイオガス事業を通じて、インドのカーボンニュートラル推進に力を入れている。スズキ株式会社の代表取締役社長である鈴木俊宏氏は、インド市場で大好評を博する圧縮天然ガス(CNG)車への活用を強調した。このイニシアティブの社会経済的な意味合いは注目に値する。スズキは、地域の酪農家から牛糞を購入することで、約10億人が暮らす農村の所得向上を目指している。これは、エネルギーと肥料の自給自足を達成するというインドの国家目標と一致している。最初のバイオガスプラントは2025年に稼働する予定であり、このイニシアティブの重要な一歩となる。バイオガス事業に加え、スズキはインドで販売する全ての乗用車と二輪車が現在E20燃料に対応していることを強調し、二輪車分野ではすでにフレックス燃料(E85)モデルの量産を開始している。同自動車メーカーは、また、フレックス燃料モデルを今年度中に投入する計画を積極的に進めている。
重要性: スズキのインド子会社であるマルチ・スズキは、多くの競合他社とは異なり、脱炭素化に向けたマルチフューエルアプローチを採用しており、地域の需要に合わせて電気、ハイブリッド、CNG、フレックス燃料を含む幅広い車種を提供している。同自動車メーカーは、インドでの販売台数に占める電気自動車(EV)の比率を2031年3月までに15%に、ハイブリッド車(HEV)の比率を25%にする目標を掲げる。インドにおけるCNG車の総売上高は35%を占め、残りの25%をエタノール混合燃料対応車とする計画である。スズキは代替燃料に加え、インドでの軽量化技術を推進し、エネルギー消費と排出ガスの最小化を図っている。同社は、新素材の採用や車体構造の最適化により、燃費の向上とCO2排出量の削減を図っている。また、インドでのサーキュラーエコノミーにも積極的に取り組んでおり、分解設計による環境負荷低減、プラスチック使用量の削減、リサイクル材の利用拡大などに取り組んでいる。この多面的なアプローチは、進化するインドの自動車業界を舵取りするスズキの持続可能性と革新へのコミットメントを示している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
VW、米国での投資を検討、ポルシェは米国での生産計画なし-報道
2025年9月9日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国
フォルクスワーゲンAG|貿易(輸出入) 、生産、経費、ライトビークル
Stephanie Brinley, Associate Director
フォルクスワーゲン(VW))とポルシェの経営陣は最近、メディアとのインタビューで、高関税という現実に直面した場合の米国製造業への投資の可能性について話し合った。Automotive Newsの報道によると、VWグループの最高経営責任者を務めるオリバー・ブルーメ氏は、IAAミュンヘン・ショーで行われたメディアとの円卓インタビューでこのように述べたという。ブルーメ氏は、米国の投資は雇用を増やし、地域社会を強化し、新たなサプライチェーンを構築し、将来の税金と輸出を支えると述べ、VWグループは米国との貿易交渉の一環として米国への大規模な投資を検討していると述べたと伝えられている。ブルーメ氏によると、VWは米国の通商当局と協議しているが、投資プログラムの可能性の詳細については明らかにしていない。同氏は「当社は、関税のために多くの損失を被っている。15%の関税はフォルクスワーゲングループにとって負担であり、当社は、早急に合意に達する機会を歓迎する。私は期待している」と述べたと伝えられている。ブルーメ氏は、また、VWグループが米国でプロジェクトを成功させるには、インセンティブや税制上の優遇税制措置が必要であると示唆した。これとは別に、ポルシェ・カーズ・ノースアメリカの責任者であるティモ・レッシュ氏は、ポルシェが米国の製造投資に反対する決定を下したことについて、ハンデルスブラットに語った。 レッシュ氏は、アメリカの関税によるコスト増にもかかわらず、同社は生産拠点に満足しており、「それが現地生産を開始するための当面の具体的な計画がない理由である」と述べた。VWグループの別の工場やCKDの生産設備を活用する可能性についての質問に対し、レッシュ氏はポルシェにはどちらの選択肢も必要ないと答えた。むしろ、同社の生産量の減少が要因となっている。「このような理由からも、現時点では現地生産はコストの観点から合理的ではない。」
重要性: VWグループとその関連企業は、米国の高関税環境を整理しており、米国とEUの最新の貿易枠組みを維持しようとしていることは明らかである(ドイツ:2025年8月29日:EU、EU車の輸入関税を引き下げるため米国製品への関税撤廃へ および欧州-米国2025年8月22日:米国、EU、貿易協定への拘束力のないコミットメントに署名参照) 。これまでの報道によると、アウディは米国での生産オプションを検討しており、建設中の「スカウト」の工場や他のアウディプロジェクトの生産能力の一部を取得する可能性もあるという。しかしながら、VWグループはアウディの米国での生産を、現在の貿易協定の改定よりもかなり前から検討していた(米国:2025年6月23日:アウディ、米国での工場建設を検討および米国:2023年2月27日:VWグループ、米国で「スカウト」とアウディEVの生産を検討-報道参照)。ポルシェの米国での販売機会に関する指摘は、米国に工場を建設するには強力な輸出業者であるか、シェアされる必要があることを反映している。2024年、ポルシェは米国で8車種にわたる76,000台弱を販売した。アメリカでは「マカン」が約25,000台と最も売れた。米国は2024年、ポルシェの全世界総販売台数の約25%を占めた。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車のバッテリー工場建設が中断-報道
2025年9月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国
現代自動車|施設・運営、生産、ライトビークル、人事
Stephanie Brinley, Associate Director
オートモーティブ・ニュースとAP通信の報道によると、メタプラントの一部である現代自動車グループのバッテリー工場は、2025年9月4日に米国移民局が施設を強制捜査を行い、不特定多数の人々を逮捕したため、建設が中断されたという。この報道は、米国移民関税執行局(ICE) の広報担当者の発言を引用し、連邦捜査官と地元の法執行機関が「違法な雇用慣行とその他の重大な連邦犯罪の申し立てに対する進行中の犯罪捜査の一環として、司法捜査令状を執行した。この調査は、法に違反した者の説明責任を確保し、法の支配を維持することに焦点を当てている」と伝えている。報道によると、現代自動車の広報担当者は強制捜査があったことを認め、「当社は法執行機関に協力しており、すべての労働規則と出入国管理規則を遵守することを約束している」と述べたという。地元メディアによると、ジョージア州パトロール隊が境界を確保し、道路へのアクセスを制限し、工事は一時停止された。報道によると、何人が拘束されたかの情報はないが、人々を乗せたバスが出発するのが見られたという。
重要性: この記事を書いている時点では、どれくらい早く工事が再開されるのか、何人の従業員が影響を受けたのかは不明である。申し立ての詳細も明らかになっていない;現代自動車や提携先のLG、従業員に関連する他の請負業者に対する正式な告発はまだ行われていないようで、不正行為がどこにあるのか;実際にあったかどうかは不明である。しかしながら、米国の自動車産業プロジェクトに対するICEの強制捜査が報告されたのはこれが初めてである;確立された自動車製造施設では報告されていない。トランプ政権は、不法入国した移民の身元確認と強制送還に積極的な政策を取っている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ルノーコリア、新CEOにニコラ・パリ氏を指名
2025年9月4日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
ルノー|市場分析、人事
Isha Sharma, Research Analyst
ルノーコリア自動車は今週初め、ニコラス・パリ氏を新CEOに任命したと発表したと聯合ニュースは報じている。パリ氏は9月1日付で、ステファン・ドブレーズ氏」の後任としてルノーグループのインド事業を統括することになった。フランスのランス経営大学院を卒業したパリ氏は、2015年にルノーグループに入社する前は自動車サプライヤーのZFレンクシステムに勤務し、20年以上にわたりグローバルな自動車購買およびリーダーシップの分野で経験を積んできた。同氏の在職中、中国のアライアンス・イノベーション・ラボで購買部門を率いるなど、フランス、インド、中国で重要なポジションを歴任した。直近では、同氏は、バッテリー、電動パワートレイン、先進運転支援システム (ADAS)、コネクティビティ、ソフトウェア、電子部品の購買担当副社長を務めた。2022年3月にCEOに就任したドブレーズ氏は、ルノーのグローバル戦略に沿った重要な商品開発イニシアティブであるオーロラプロジェクトを立ち上げ、ルノーコリアの長期的な競争力とグループにおける戦略的意義の強化に取り組んできた。この取り組みの最初のモデルは2024年9月に発売した「グランドコレオス」で、すでに韓国市場で45,000台以上を販売している。
重要性: パリ氏のルノーコリア自動車CEO就任は、アジアを中心とした主要市場での事業強化に重点を置くルノーグループの戦略を反映したものであり、重要な意味を持つ。グローバルな自動車購買における豊富な経験とリーダーシップにより、急速に進化する自動車業界におけるルノーコリアの成長と競争力を強化する。同氏のリーダーシップは、ルノーの国際戦略に沿った製品開発を目指すオーロラプロジェクトなどのイニシアチブを実行し続ける重要な時期に発揮されている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日本がインドに4億米ドルを投資し竹由来バイオ燃料精製所を設立
2025年8月29日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本-インド
経費
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
Nikkei Asiaの報道を引用したBusiness Standardの報道によると、日本は、竹由来バイオマスを自動車用燃料に変換するインドのバイオ燃料プロジェクトに官民から最大600億円 (4億800万米ドル) の資金を提供する計画である。この資金調達は、政府系金融機関の国際協力銀行 (JBIC) と三井住友銀行などの民間企業が拠出する。JBIC単独で資金総額の2億4,400万ドルを拠出する。同取り組みは、国営の電力金融公社が主導し(PFC)、 持続可能なエネルギーに関する日印協力の一環である。融資はPFCを通じてインド法人Assam Bio Ethanol Private Limited(ABEPL) に融資され、アッサム州ゴラガート地区に新製油所を建設している。完成間近のこの施設では、地元で採れる竹からバイオ燃料を生産する。この製油所では、インドでガソリン添加剤として使用されるバイオエタノールを年間49,000トン生産する予定である。また、接着剤などに使用する酢酸11,000トン、合成樹脂の原料となるフルフラール19,000トンを生産する。残ったバイオマスは発電に利用し、ゼロウェイストアプローチを推進する。
重要性: バイオ燃料はインドの自動車産業にいくつかの重要な利益をもたらす。第一に、温室効果ガスの排出削減に貢献し、気候変動との闘いや都市部の大気環境の改善に貢献している。エタノールなどのバイオ燃料を燃料供給に統合することで、産業は輸入化石燃料への依存を減らし、それによって燃料価格を安定させることで、エネルギー安全保障を強化することができる。さらに、バイオ燃料の利用は、バイオ燃料生産に使用される作物などの農産物の新たな市場を創出することによって農村開発を促進し、農民の所得を増加させることができる。日本は資金を提供するだけでなく、製油所に日本の蒸留装置を設置し、日本の発酵技術を導入するための議論を継続するなど、バイオ燃料生産に関する技術的知見を提供する予定である。さらに、このプロジェクトは、化石燃料の輸入への依存を減らすためにガソリンに20%のエタノールを混合することを奨励するインドのE20プログラムに沿ったものである (インド:2025年7月25日:インド、ガソリンへのエタノール20%混合を前倒しで達成参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車労働者、賃上げ要求ストに賛成票
2025年8月26日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
現代自動車|施設・運営、生産、企業、ライトビークル、人事、電動化
Jamal Amir, Principal Research Analyst
韓国の現代自動車の労働組合は賃上げを求めてストライキを開始することに賛成票を投じ、この動きは7年ぶりのストライキにつながる可能性があると聯合ニュースは報じている。8月25日に行われた投票では、組合員の86.15%がストライキ計画を支持し、42,180人の組合員の95%近くが投票した。同日、国家労働委員会の仲裁が失敗し、ストの法的権利が確保されたことで、労組はストに備えることができた。ストライキへの圧倒的な支持にもかかわらず、即時の行動は期待されていない。労組は8月28日に臨時スト委員会を設置し、具体的な対策を協議する予定である。
重要性: 今回のストライキ投票の背景には、今年に入って17回の賃金交渉が行われるなど、労組と経営側の交渉が失敗に終わったことがある。労組は毎月の基本給の大幅な引き上げ、具体的には労働者1人あたり141,300ウォン (102米ドル) の賃上げを主張してきた。また、現代自動車の年間純利益の30%を成果給として分配し、ボーナスを現行の7.5ヶ月から、労働者一人当たりの給与の9ヶ月分に増やすことを要求している (韓国:2025年1月23日:現代自動車、2024年の純利益が前年比7.8%増、シェア2025年の見通し参照) 。労組はまた、雇用安定や報酬に対する懸念を反映し、定年を60歳から64歳に引き上げることを求めている。最近、米国の自動車輸出関税15%の発動など、外圧に直面している韓国自動車産業にとっては厳しい時期である。このような関税は、現代自動車の米国市場での事業と収益性に大きな影響を及ぼす可能性があり、労組の賃金とボーナスの引き上げ要求はさらに切迫したものになる。同報道は、現代 (ヒョンデ) 自動車グループのチョン・ウィソン会長が、イ・ジェミョン大統領とドナルド・トランプ米大統領の重大な首脳会談に出席するため、韓国財界代表団としてワシントンDC(米国)を訪問しているという。今回の首脳会談の結果は、現代自動車など韓国企業の今後の対米投資計画に影響を及ぼす可能性がある。状況が進展すれば、ストの可能性は、現代自動車の事業と従業員関係、さらには韓国のより広範な自動車産業に広範な影響を及ぼす可能性がある。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ヒュンダイ・インディア、顧客のデジタルキー機能登録率33%を発表
2025年8月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
現代自動車|企業、コンポーネント、ライトビークル、製品、テクノロジー、トレンド、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
ヒュンダイ・モーター・インディアは、特定の車種の顧客の間で革新的なデジタルキー機能の登録率が33%という驚異的な数字を発表したと、同社が発表したデータを引用してAutocar Professionalが報じている。この先進技術は、ユーザーがスマートフォンやスマートウォッチを使って車のロック解除、ロック、始動を行うことを可能にするもので、インドにおけるコネクテッドカーソリューションへの大きな転換を示している。デジタルキー機能は、2024年9月に現代自動車「アルカザール」で初めて導入され、その後2025年1月に「クレタ・エレクトリック」モデルに導入された。このシステムは、Hyundai Bluelinkモバイルアプリケーション内に統合された近距離無線通信(NFC)技術によって動作し、ユーザーのデバイスと車両間のシームレスな対話を可能にする。利用統計によると、デジタルキーユーザーの68%はiOSデバイスを利用しており、32%はAndroidプラットフォームを利用している。さらに、この機能はソーシャル・コネクティビティをサポートしており、ユーザーの35%がデジタルアクセスを家族や友人と積極的に共有している。最大3人のユーザーまたは7台のデバイスを同時に接続できるため、複数のドライバーがいる家庭での利便性が向上する。
重要性: 現代自動車は、早くも2019年にそのような機能を導入し、インドにおけるコネクテッドカー技術のパイオニアと位置付けている。同社は、将来的にデジタルキー機能を他の車種にも利用できるよう拡大し、自動車技術分野における同社のリーダーシップをさらに確固たるものにする計画である。ヒュンダイ・モーター・インディアのマネジングディレクター、キム・ウンス氏は「デジタルキーに対する熱狂的な反応は、日常生活に真の価値をもたらす技術を生み出すというわれわれの信念を再確認するものである」と述べた。これは、技術革新を通じてユーザー体験を向上させるという現代自動車のコミットメントを示している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
シャオミ、2027年の欧州市場参入を目指す
2025年8月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ
施設・運営、市場分析、ライトビークル、電動化
Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst
シャオミは中国でEV事業を立ち上げた後、2027年までに欧州で初の電気自動車(EV)を発売し、世界での競争を目指す。シャオミの社長であるルー・ウェイビン氏は、スマートフォン需要の減少を補い、今年に入って2番目のEVを投入したことで四半期収益が31%増加したことを受けて、この拡大の詳細を明らかにしたとブルームバーグは報じている。
重要性: シャオミは海外進出の意向を表明しているが、これまで具体的なターゲット市場を特定していなかった。同社はすでに、ドイツのミュンヘンでの公道テスト用にシャオミSU7 Ultraを登録するなど、欧州での機会を模索し始めている。欧州は中国のEVメーカーにとって利益率が高い可能性があるため魅力的だが、多額の関税が課される。シャオミがEVを欧州に輸出した場合、最大48%の関税が課される可能性があり、EUは市場競争を歪め、現地メーカーを脅かす不公正な国家補助金への懸念から10%の輸入関税と35~38%の追加の相殺関税を課している。米国の状況はさらに厳しく、中国のEVメーカーは100%の関税に直面しており、事実上市場から締め出されている。これらの障害にもかかわらず、6月下旬に発売されたシャオミのスポーツ・ユーティリティ・ビークルYU7に対する強い需要は、競争の激しいEV市場における同社の100億米ドルの投資に拍車をかけている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
テスラ、インドで小売拠点を拡大
2025年8月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
テスラ|施設・運営、経費、企業、売上高、ライトビークル、電動化、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
テスラは、主要都市部に一等地の小売スペースを確保することでインド進出戦略を大きく前進させ、インドの電気自動車 (EV) 業界では極めて重要な動きを見せているとET Autoが報じている。最近、同自動車メーカーはデリーのエアロシティーにあるWorldmark 3の1階に8,200平方フィートの小売スペースをリースし、この決定は、インドの主要都市において認知度の高いプレゼンスを確立するという同社のコミットメントを強調するものである。2025年7月30日に文書化されたリース契約は、Oak Infrastructure Pvt Ltdとの9年間のサブリースであり、36ヶ月のロックイン期間を特徴としている。テスラは、当初の月額賃料1,722,000ルピー(平方フィート当たり約210ルピー)と共用エリアメンテナンス(CAM)料、平方フィート当たり33.5ルピーを支払う。この契約には、10台分の駐車スペースが含まれ、それぞれ月額6,000ルピーで、前払いで払戻可能な敷金1,030万ルピーと共益費10,300,000ルピーが含まれる。賃料は2025年3月15日から3年ごとに15%ずつ上昇し、120日間の装備期間を設けて運用を開始する。デリー空港の近くに戦略的に位置するこのショールームは、テスラの多様なEVとエネルギー製品を展示する主要小売店として機能すると予想されている。デリーのショールームに加えて、テスラはグルガオンでもSohnaロードのOrchid Business Parkに33,475平方フィートの大きなスペースをリースして存在感を示している。この施設は小売店舗としてだけでなく、デリー・NCR地域における同社初の統合サービスセンターおよび配送ハブとしても機能する。2025年7月15日から有効となる9年間のリース契約は、7月28日に複数の不動産開発業者と登録され、テスラのインドにおける包括的な事業基盤を確立するというコミットメントをさらに確固たるものにした。
重要性: 7月15日、ムンバイのバンドラクルラコンプレックス(BKC)にテスラ初のインドショールームを開設し、インド市場向け「モデル Y」を5,989,000ルピーで公開した(インド:2025年7月16日:テスラ、モデル Yでインド市場に参入参照) 。さらにテスラは、ムンバイのKurla Westに24,565平方フィートの車両サービスセンターをリースしてサービス業務を行っており、カスタマーサービスとサポートに対する強力なアプローチを示している。特に米国と欧州の市場が飽和状態に近づいている今、インドはテスラにとってまたとない機会を提供している。Autocar Professionalによる報道は、先に、持続可能性を優先する裕福な消費者層の増加に伴い、インドの高級EVセグメントが急速に成長していると指摘していた。現在、高級車セグメントにおけるEVの普及率は11%を超えており、これは内燃エンジン(ICE)搭載の高級車が最高48%なのに対し、EVには一律5%の物品サービス税(GST)が課されるなどの優遇税制が背景にある。テスラの価格設定は、同社を高級車セグメントに正々堂々と位置づけ、タタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラ(M&M)のような大衆市場のインド企業ではなく、BMWやメルセデス・ベンツなどのドイツブランドと競合する。S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
VW、米市場でのハイブリッド車販売を待ち受ける
2025年8月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国
フォルクスワーゲンAG|施設・運営、企業、ライトビークル、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
フォルクスワーゲン(VW)オブアメリカは米国での販売を加速させるため、新しいハイブリッドモデルの提供を待っているとAutomotive Newsは報じている。VWの乗用車ブランドは、ここ数ヶ月、米国市場での新型モデルの発売が好調で、「ジェッタ」フェイスリスト、サブコンパクトクロスオーバーの「タオス」、第3世代の「ティグアン」、そして待望の「ID.Buzz」が欧州市場での発売に比べて遅れて同社のラインナップに加わった。しかしながら、米国ではパワートレインの人気が高まり、ハイブリッド車の選択肢が少ないという問題があった。フォルクスワーゲンオブアメリカのCEOであるクイェル・グルーナー氏は4月、同社の2つのベストセラーモデルである「ティグアン」と「アトラス」D-SUVクロスオーバーのハイブリッドモデルを米国で発売する計画であると述べた。
重要性: VWには、米国市場での販売を大幅に拡大し、幅広い消費者にとって魅力的なハイブリッドモデルがないことは明らかである;同社の電動IDシリーズは安定したペースで販売されている。しかしながら、VWは欧州市場向けのプラグインハイブリッド車の開発に注力し、それは米国市場にとってうまくいきそうにないコストとウェイトペナルティとなる。その結果、VWはこれらのフルハイブリッドモデルをゼロから開発しなければならず、それは費用と時間のかかるプロセスであり、米国市場向けの「ティグアン」と「アトラス」のフルハイブリッドモデルの正式な発売日はまだ決まっていない。その結果、S&P Global Mobilityは、VWブランドの米国での登録台数は2025年に344,000台、ハイブリッド車の販売台数が本格化するとみられる2027年には384,000台に増加すると予想している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタウーブン・シティは新しいインベンターズ12人を集める
2025年8月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|テクノロジー、トレンド・進化、自動運転車、コネクテッドビークル
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
トヨタ自動車株式会社 (以下、トヨタ自動車) とウーブン・バイ・トヨタ株式会社は、日本の裾野市に開設する実世界コースモビリティのテストコース「Toyota Woven City」において、9月よりフェーズ1を開始するにあたり、新たに12名の「インベンターズ」を追加したと発表した。インベンターズとウィーバーズ-住民と訪問者-が協力して、社会に役立つ製品とサービスの開発を加速させる。新グループにはトヨタ以外の2社が含まれる:インターステラテクノロジズはロケットや人工衛星の開発に注力しており、共立製薬は獣医学に取り組んでいる。残る10のインベンターズは、株式会社豊田自動織機、株式会社ジェイテクト、トヨタ車体株式会社、豊田通商株式会社、株式会社アイシン、株式会社デンソー、トヨタ紡織株式会社、トヨタ自動車東日本株式会社、豊田合成株式会社、トヨタ自動車九州株式会社のトヨタグループ各社で構成されており、2025年1月に発表した初期のグループの上に築く全体で19のインベンターズになった。
重要性: ウーブン・シティには、自動化地上移動のための専用道路と、物流サービスの自動化実験のために設計された地下道である「物流ストリート」がある。第一段階は47,000平方メートルの広さで、昨年完成した14の建物のうち8棟が含まれており、主に居住用の建物で、インベンターズと居住者の交流センター、エネルギービルなどがあるという。ウーブン・シティの核となるのは、トヨタがロボット工学や自動運転車、コネクティビティの開発を研究室からより自然な日々の交流を研究できる場所に移すためのスペースを提供することである。トヨタはこの都市の主要な電力源を水素にする計画である。2,000人の居住者には、ホームロボティクスや入居者の健康をチェックするセンサーベースの人工知能(AI)など、最新のヒューマンサポート技術を導入する計画である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
BMW、マグナ・シュタイアー、「ノイエ・クラッセ」のBEVパワートレイン生産を開始
2025年8月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-オーストリア
BMW |施設・運営、生産、経費、企業、ライトビークル、電動化、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
企業の声明によると、BMWシュタイアーはまったく新しい中型電動スポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) iX3のパワートレインの製造に着手しており、同車種は来月のIAAミュンヘン・モーターショーで一般公開される予定であるという。iX3がBMWの歴史の中で最も重要な立ち上げの1つであることを考えると、BMWが本拠地でこの車をデビューさせることは適切と言えるだろう。というのも、iX3が、今後公開されるモデルの大部分をサポートする、同社のまったく新しい電気自動車 (BEV) アーキテクチャ上に構築される最初のモデルであるからである。BMWのオーストリア製造工場では、新型iX3用の同社の第6世代BEVパワートレインの生産が現在始まっている。BMWグループの生産担当役員であるミラン・ネデリコヴィッチ氏は、この開発について次のように述べて、「今日、当社はBMWグループの未来の基礎を築いた。Gen6電動エンジンの最初の生産拠点として、シュタイヤー工場は「ノイエ・クラッセ」と当社のグローバル生産ネットワークの継続的な発展の中心となっている。」と述べた。
重要性: 2022年のプロジェクト開始から2030年までの間に、BMWグループはシュタイアー工場におけるBEVパワートレインの開発と生産の専門知識の拡大に10億ユーロ以上を投資している。今回の生産能力増強により、同工場はBMWグループの主要なパワートレイン製造拠点であり続ける。40年以上にわたり、同工場は、BMWおよびMINIブランド向けの内燃機関 (ICE) を開発、製造してきた。同工場では、ICEディーゼルおよびガソリン (石油) エンジンの製造を継続するとともに、電動パワートレインの製造も継続する。モーター部品に関しては、ローター、ステーター、トランスミッション、インバータがシュタイアーで製造される。電動エンジンのハウジングはランツフート工場のアルミニウム鋳造アルミニウム鋳造で鋳造され、さらにシュタイヤーで加工される。このインバータは、新しい社内クリーンルーム環境で製造される予定であり、この重要な機器の汚染を避けるために、製造が可能な限りクリーンな環境で行われることを保証するために多くの投資が行われてきた。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、欧州本社の人員削減を協議
2025年8月6日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–フランス
日産自動車株式会社|施設・運営、企業、市場、ライトビークル、人事、コーポレート
Ian Fletcher, Principal Analyst
日産は、フランスのモンティニー=ル=ブルトンヌー にある欧州本社の人員削減について、労働組合と協議している。日産はロイターに対し、欧州日産の従業員約560人と協議を開始したことを認めた。同通信が確認した同社の文書と内部メールによると、経営陣と組合は、強制解雇の前に自主的な解雇について話し合うことで合意しており、話し合いは2025年10月20日までに終了する予定であるという。詳細は11月に従業員と共有される予定である。事情に詳しい匿名の人物がロイターに語ったところによると、日産はオフィスの大幅な変更を計画している。
重要性:日産はこれまで、経営再建計画「Re:Nissan」の下、コスト削減と効率化の一環として、グローバル事業の再編計画を発表してきた(日本:5月14日日産、2024~2025年度に対比して、6,709億円の純損失を計上し、経営再建計画「Re:Nissan」を発表参照)。同社は、2024~2025年度(FY)に対比して、固定費と変動費の合計で5,000億円のコスト削減を目指す。構造改革の一環として、同自動車メーカーは、2027~2028年度までに車両生産工場を現在の17工場から10工場に削減する計画である (メキシコ:2025年7月30日:日産、メキシコと日本の工場閉鎖を確認および日本:2025年7月16日:日産、追浜工場での生産を2027年度末までに終了へ参照)。また、日産は、2024~2025年度と2027~2028年度の間に合計2万人の人員削減を計画しており、欧州日産での人員削減もこの動きの一環となる。これと同時に予定されている大きな変更に関する情報源からのコメントは、施設の責任に関連している可能性がある。現在は欧州だけでなく、アフリカ、中東、インド、オセアニア地域でも活動している。これは、時間帯の問題だけでなく、地域の市場要件に迅速に対応する能力の問題を引き起こす可能性がある。いかなる変更も、地域の独立性を高め、現地の競争や傾向に適応する自由を与えることを目指すかもしれない。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
小鵬汽車、新型P7クーペを公開
2025年8月1日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土)
企業、販売、展示・発売、ライトビークル、製品、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
Gasgoo Chinaの報道によると、小鵬汽車は最近、最新モデルXPENG P7電気自動車クーペの公式画像を公開した。8月6日に中国で発売される予定のこのモデルは、小鵬汽車のデザインとテクノロジーを大幅に進化させたもので、非常に魅力的でスポーティな4ドアクーペデザインを採用しており、ポルシェのタイカンなどと競合することになる。公式画像によると、2024年モデルのP7+とよく似た印象的なフロントとリアのデザインで、空力性能を向上させるリアスポイラーを特徴としている。新型P7のサイドプロファイルは、よりアスレチックなクーペのようなシルエットを採用し、洗練されたスマートな外観に寄与するフラッシュドアハンドルを採用している。同車はEセグメントで、長さ5,017 mm、幅1,970 mm、高さ1,427 mmである。3,008 mmのホイールベースは、ユニボディ構造と相まって、中型電気自動車セグメントの消費者にとって重要な要素である安定性とハンドリングを向上させる。このモデルにはオプションのシザードア、衝突防止機能付きフロントバンパー、レーダーシステム、隠しドアハンドルが装備されている。さらに、車両後部には、速度に応じて空力を最適化するアクティブリフトスポイラーが装備されている。「P7」はまた、低抵抗デザイン、コントラストカラー、ブラックアウトの3つの異なるホイールオプションを提供し、すべてが目を引くオレンジ色の4ピストンキャリパーを備えている。このレベルのカスタマイズは、消費者が個人の好みに合わせて車を調整することを可能にし、競争の激しい自動車市場においてますます重要な側面となっている。「P7」は3つのバリアント、2つのバッテリーオプションを利用できる予定である:中国小型車テストサイクル(CLTC )での航続距離が625 kmの74.9 kWhバッテリーパックと、CLTCでの最大航続距離が820 kmのより堅牢な92.2 kWhバッテリーパックである。この航続距離の柔軟性により、「P7」は都市部での通勤と長距離移動の両方に適した選択肢となり、電気自動車の消費者の主な懸念の1つである航続距離不安に対処する。
重要性: XPENG P7は2020年4月に発売され、同年11月には「P7」エディションが発売された。このモデルは大きな成功を収め、2022年3月23日には生産台数10万台というマイルストーンを達成した。この成功は、小鵬汽車が先進的な技術をユーザーフレンドリーな機能と統合することに戦略的に重点を置いていることに起因しており、これは中国の技術志向の高い消費者ベースによく共鳴している。今回の大幅な見直しにより、競争が激化する中国の高性能BEV市場での販売拡大が期待される。S&P Global Mobilityは、新型「P7」の販売台数が2030年にピークの46,000台に達すると予想しているが、ただ、初代モデルのピークは2021年の61,000台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ヒュンダイ・インディア、GSTに51億7,000万ルピー要求支払い不足の疑い
2025年7月24日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
現代自動車|方針・規制、企業、ライトビークル、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
ヒュンダイ・モーター・インディア(HMIL) は最近、特定のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV) モデルに対する物品・サービス税 (GST) の補償税の支払い不足を理由に51億7,000万ルピー (5,990万米ドル) の多額の支払いを要求され、税務当局の厳しい目にさらされているとAutocar Professionalは報じている。当局への提出書類によると、命令はタミル・ナードゥ州の中央物品・サービス税 (CGST) 局長官が発したもので、GSTの補償金25億9,000万ルピーと罰金25億9,000万ルピーの支払いを確認する内容である。この要求は2017年9月から2020年3月までの期間に関するものである。
重要性: 報道は、GST補償税が通常28%に設定されている標準GST率を補完する、特定のカテゴリーの車両に課される追加課税であると指摘している。2017年に導入されたこの税は、GST制度への移行によって生じる潜在的な歳入不足を州が補うことを目的としている。この税の賦課は、メーカーがコンプライアンスと課税の複雑さをナビゲートする中で、自動車業界内で論争の的となっている問題である。この要求に対し、現代自動車はこの命令は財務や事業などに影響はないと主張している。同自動車メーカーは現在同命令を再検討し、税務当局の決定に対して不服申し立ての権利を行使する意向を示している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スズキ、新型「アルトラパン」「アルトラパンLC」を来月発売へ
2025年7月24日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本スズキ株式会社|製品
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
スズキは、軽乗用車「アルトラパン」と「アルトラパンLC」の仕様を一部変更し、8月25日に発売する。R06Dエンジンやマイルドハイブリッドシステムを搭載し、走りやすさと燃費性能を向上させた。デザインの変更点は、フロントグリルとバンパーの改良を含む。新しいカラーオプションである-ルーセントベージュパールメタリックとフォギーブルーパールメタリックは-「アルトラパン」のパレットを11色、「アルトラパンLC」のパレットを12色に広げる。デュアルセンサーブレーキサポートII、車線逸脱抑制機能、信号切り替わりにも対応した発進お知らせ機能を標準装備し、安全性を高めている。また、急速充電が可能なUSB電源ソケットを搭載し、スズキコネクトにも対応する。月間販売目標は3,000台である。
重要性: 「アルト」は、PK5プラットフォームをベースにしたAセグメント車で、日本のスズキ湖西工場で製造される。S&P Global Mobilityのデータは、日本での人気は高いものの、2014年の約70,900台から2024年には42,200台まで減少しており、2025年には40,200台までさらに減少すると示している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、新たな顧客特典プログラムを開始
2025年7月17日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国
現代自動車|研究開発、売上高、ライトビークル
Stephanie Brinley, Associate Director
現代自動車は、デジタルサービスを利用する顧客に報いる3段階のプログラム「Hyundai Rewards」を創設した。このプログラムは新規および既存のオーナーが利用でき、MyHyundaiアカウントから無料で参加できる。顧客は、Bluelinkの機能の利用、定期的なメンテナンスの完了、自動車の購入、リコールまたはサービスキャンペーンの完了、Bluelinkの有料サブスクリプションへの登録、リモートサービスの利用、およびデジタルキーの「Phone-as-Key」機能の利用によって報酬を得る。従来のポイントプログラム ロイヤルティ プログラムのようにクレジットカードと連動していないため、ポイント制ではなく、信用調査も必要ないと現代自動車は説明している。現代自動車は、「オーナーはブランドと関わるためにすでに行っている行動に対して報酬を得ることができる」と述べた。報酬にはシルバー、ゴールド、ブルーがあり、ブルーが最高レベルである。Hyundai Motor Americaのアフターセールス・カスタマー・エクスペリエンス担当の副社長、ミシェル・ポワリエ氏 は、「全く新しいHyundai Rewardsプログラムで、当社の忠実な顧客のために現代自動車のオーナーシップ体験を強化することを目指している。当社は、インタラクティブな感じがして、ヒュンダイを所有することにもっと満足感が得られるプログラムを作りたかったのである。Hyundai Rewardsは顧客が簡単に参加でき、すでに行っている行動で報酬を得ることができる」と声明において述べた。
重要性: このプログラムは、外部からの支出に報いるクレジットカードではなく、デジタル上の交流や車両サービスに報いることで、現代自動車のディーラーや技術との交流の価値を高めるものである。このプログラムは、オーナーが時間をかけずに使っていたかもしれない機能を使うように促す可能性がある。オーナーがその機能を気に入れば、所有体験を向上させ、ロイヤルティを高めることができる。リコールとサービスの完了に対する報酬は、車両の適切なメンテナンスを確実にするのに役立つ可能性がある。リコールの要素も興味深く、なぜなら、リコールは消費者に完了を最後まで実行するさせるのが難しいことが多いからだ。現代自動車のアプリを使うことで、その車両のオーナーとより直接的なコミュニケーションが可能になり、リコールが完了するまでリマインダーを繰り返すことができる。現代自動車のプログラムは、所有期間を通じて消費者のエンゲージメントを維持するように設計されていることが多く、このプログラムは現代自動車の一般的な消費者エンゲージメントを強化するものである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
テスラ、インド市場に「モデルY」投入
2025年7月16日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
テスラ|企業、売上高、展示・発売、ライトビークル、製品、電動化、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst

テスラ
S&P Global Mobilityの視点
テスラはインドで「モデルY」を正式に発売し、素晴らしい航続距離と機能を備えた2車種を提供するとともに、ムンバイに初のショールームを開設した。 S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。
テスラは「モデルY」の発売と同時に、ムンバイの高級住宅地バンドラ・クルラ・コンプレックスに同社初のショールームを開設し、インドの自動車市場に本格的に参入したとAutocar Indiaは報じている。デリーには第2のショールームが計画されており、市場の反応次第でさらなる拡張が可能である。 インドでは「Model Y」に2つのバリアントがある:スタンダードおよびロングレンジ。現在予約が開始されており、最初の登録と出荷はデリー、グルグラム、ムンバイに限定され、主要都市での戦略的展開となる。価格はスタンダードバリアントが5,989,000ルピー (69,705米ドル)、ロングレンジバリアントが6,789,000ルピーである。
スタンダードバリアントは、世界統一軽自動車テスト手順 (WLTP) に基づく一回の充電で最大500 kmの航続距離を誇り、わずか5.9秒で0から100 km/hまで加速する。ロングレンジバリアントは、WLTP認定の1回の充電で航続距離622 kmを誇り、同じ加速を5.6秒で達成する。Tesla Indiaのウェブサイトにはバッテリーの仕様が明記されていないが、スタンダードモデルYは63 kWhのバッテリーと283馬力のリアモーターを搭載し、ロングレンジバリアントは83 kWhのバッテリーとより強力な312馬力のリアモーターを搭載する。どちらのバリアントも最高速度は201 km/hであるという。テスラによると、同社のロングレンジバッテリーは、250 kWhの充電速度でスーパーチャージャーを使用すると、わずか15分で最大267 kmの走行距離を走行できるという。同電気自動車(EV)メーカーはインド国内に16カ所のスーターチャージャーステーションを設置する計画で、最初の8カ所はムンバイとデリー周辺に設置する。テスラはインドデビューの一環として、購入者全員に無料の家庭用壁充電器をプレゼントすると発表した。
「モデルY」が、テスラの特徴である控えめなデザインを施した最新バージョンでインドに登場した。車両は長さ4,790 mm、幅1,982 mm、高さ1,624 mmである。エクステリアには、フルワイドLEDライトバー、戦略的に配置されたヘッドランプ、ぴったりフィットするドアハンドル、19インチのエアロ最適化アロイホイールを備えたスタイリッシュなデザインが特徴である。リアデザインには、傾斜ルーフライン、ダックテールスポイラー、フルワイドLEDテールライトが含まれている。モデル Yの内部は、テスラのミニマルなアプローチを踏襲しており、15.4インチの中央タッチスクリーンでほぼすべての車両機能を制御する。フロントシートの電動化、暖房、ベンチレーション、乗客用8インチ後部タッチスクリーン、9スピーカーオーディオシステム、電動テールゲート、前方衝突警報、アクティブエマージェンシーブレーキ、車線逸脱防止など、利便性、安全性、技術面でさまざまな特徴を備えている。さらに60万ルピーを追加すれば、顧客は、テスラのオートパイロット機能を選択できる。
テスラは車両全体に4年間または8万 km保証、バッテリーとドライブユニット8年間または192,000 km保証を提供している。完全輸入車であるにもかかわらず、「モデルY」は競争力のある価格設定となっており、起亜EV6、ボルボEC40、メルセデス・ベンツEQAなどの競合車と肩を並べる。「モデルY」はテスラの上海ギガファクトリーから輸入されており、インドとEUの自由貿易協定が発効すればベルリンからも輸入する計画である。「スタンダードモデルY」は今四半期に、「ロングレンジ」バリアントは10月に出荷が開始される予定である。
見通しと影響
テスラのCEOイーロン・マスク氏が2016年にインド進出の可能性を示唆して以来、同社のインド進出は期待と挫折の連続であった。完成車の輸入関税は最大100%に達することがあるほか、複雑な規制環境やインド政府による現地生産への強い優遇措置などが主な理由で、当初の意欲は大きな障害に直面していた。マスク氏とインドのナレンドラ・モディ首相が今年初めに米国で会談した後に突破口が開かれ、それがテスラのインド事業への道を開いたようである。インド連邦重工業大臣H.D.クマラスワミー氏は最近、テスラは現地生産に傾倒しておらず、主にショールームを開設して輸入車を販売することを目指していると述べた。このアプローチは、欧州での販売減少や中国での競争激化など、グローバルな課題が山積する中で、大きな可能性を秘めた市場に参入するための戦略転換を示唆している。 特に米国と欧州の市場が飽和状態に近づいている今、インドはテスラにとってまたとない機会を提供している。Autocar Professionalの報道によると、持続可能性を優先する裕福な消費者層の増加に伴い、インドの高級EVセグメントは急速な成長を遂げている。現在、高級車セグメントにおけるEVの普及率は11%を超えており、これは内燃エンジン(ICE) 搭載の高級車が最高48%なのに対し、EVには一律5%の物品サービス税 (GST) が課されるなどの優遇税制が背景にある。テスラの価格設定は、同社を高級車セグメントに正々堂々と位置づけ、タタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラ (M&M) のような大衆市場のインド企業ではなく、BMWやメルセデス・ベンツなどのドイツブランドと競合する。 さらに、テスラのインド進出は地政学的な状況も後押ししており、インド政府はBYDや長城汽車など中国のEVメーカーに消極的な姿勢を示している。これによりテスラは、中国勢と直接競合することなく、インドで唯一の海外高級EVブランドとなり、高級車市場をより効果的に獲得できる。 しかしながら、現地生産の欠如は大きな課題となっており、同国におけるテスラの販売台数と成長を制限する可能性がある。マスク氏は以前、インドに製造施設を含めて20億米ドルから30億米ドルを投資することを示唆していたが、同氏のインド訪問のキャンセルにより影が薄くなり、テスラの長期的な市場へのコミットメントに疑問が生じた。
全体として、テスラのインドへの正式参入は画期的な進展であり、インドの自動車とクリーンエネルギーの未来に大きな影響を与える。直接的な影響は高級車分野に限定されるかもしれないが、テスラのブランド力、技術力、世界的な影響力は、消費者の認識や政策、業界力学に幅広い変化をもたらすと予想される。今後の道のりは-高価格、インフラ不足、政策の不確実性などの-課題に満ちているが、複雑で急速に進化するインド市場の舵取りに長けた者にとっては、チャンスに満ちている。テスラが現地生産にコミットし、より手頃な価格のモデルを投入すれば、インドのEV市場に与える影響は大きく変わるだろう。
S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
マツダ、東京に研究開発拠点を新設
2025年7月9日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本
マツダ株式会社|施設・運営
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
マツダ株式会社は、首都圏における事業強化戦略の一環として、東京・麻布台ヒルズに研究開発拠点「マツダR&Dセンター東京(MRT)」を新設した。これには、霞が関ビルからの東京オフィス移転も含まれる。同自動車メーカーは、「走る歓び」、「デザイン」、「品質」などの従来の強みを磨き上げる一方で、電動化や知能化に注力していく。マツダは、新R&Dセンターの設立により、ソフトウェア開発能力を強化し、ソフトウェアエンジニアの共同作業環境の整備や大学・研究機関との連携を推進するとしている。東京オフィスでは、国内事業の変革を支えるマーケティング機能を強化し、全社的な採用活動を強化する。
重要性: 新R&Dセンターは、マツダがこのほど発表した、国内事業の基盤強化と日本市場におけるプレゼンスの再活性化を目的とした「国内ビジネス構造変革の方針」を支えるものである。この方針は、次の3つの柱に基づいている:ブランド強化のための成長投資;大都市圏の優先順位付け;店舗での体験を向上させるための強力な最前線のサポートを提供している(日本:2025年6月20日:マツダ、国内市場での事業強化戦略を発表参照) 。マツダは3月、近年の課題を受けて電動化開発コストを削減することを目的とした新しいリーンアセット戦略を発表した (日本:2025年3月19日:マツダ、電動化開発コスト削減のための新しいリーンアセット戦略を発表参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、社債発行による構造改革で8,600億円調達
2025年7月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
日産自動車株式会社|財務、ライトビークル、コーポレート
Ian Fletcher, Principal Analyst
日産は、社債の新規発行で約8,600億円を調達したと発表した。同社は声明で、米ドル建てとユーロ建ての社債で6,600億円、円建ての転換社債で2,000億円を調達したと発表した。同自動車メーカーは、これらの資金は中長期計画を支援するために、より長期の4年間と10年間で調達されたと付け加えた。
重要性: 起債の背景には、同自動車メーカーがここ数ヶ月間に事業再編計画を発表したことがある。日産はこの声明の中で、米ドルおよびユーロ建て社債の発行により調達した資金の使途について、「一般的な事業活動および2025年度[FY]を含む今後の社債の償還」と述べている。円貨建転換社債型新株予約権付社債の手取金については、2030年度までに電動化やソフトウェア・デファインド・ビークル (SDV) 等の新製品・新技術への投資に充当する予定である。同自動車メーカーによると、これらの社債の販売は「Re:Nissanリカバリープランに対する投資家の信頼を反映」申し込みが殺到したという(日本:2025年5月14日:日産、2024~2025年度の純損失は6709億円と報告、 Re:Nissanリカバリープラン発表参照) 。同自動車メーカーは、また、「同社は、Re:Nissanの目標達成に向け、引き続き資金調達力を強化し、自動車事業の流動性を確保していく」とも述べている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、サプライヤーに支払い遅延の受け入れ要請
2025年7月1日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
日産自動車株式会社|財務、ライトビークル
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日産は一部の部品サプライヤーに対し、利息付きの遅延支払いに同意するよう要請しており、これは同社の短期的なキャッシュフローを強化するための措置だとフィナンシャル・タイムズは報じている。 日産はロイターへの声明で、「彼ら/彼女ら[サプライヤー]は利息を即時に支払うか、後払いを選択できる」と述べた。また、同自動車メーカーは、全世界で2万人削減する大まかな取り組みの一環として、英国のサンダーランド工場で自主退職制度を通じて250人を削減するつもりである。日産は、2兆2,000億円 (154億米ドル) のキャッシュ・リザーブとクレジット・ラインは、これらの人員削減と工場閉鎖の可能性に十分対応できると主張しているが、これらの最近の行動は、同社の財務健全性に対する投資家の懸念を高める可能性がある。また、自動車事業のネガティブなフリーキャッシュフローは、3月末の2,430億円から6月末には5,500億円と大幅に増加する見通しである。
重要性: 日産は5月に発表した「Re:Nissan」リカバリープランに基づき、今後数年間でコスト削減と事業の効率化をより幅広く目指している。「Re:Nissan」計画に示された目標は、日産が2月に発表した再建策よりも野心的であり、深刻化する日産の危機と財務健全性の回復が急務であることを反映している (英国:2025年5月14日:日産、2024~2025年度の純損失は6,709億円 と報告、「Re:Nissan」リカバリープランを発表参照) 。先週、日産は2025~2026年度第1四半期に純損失を計上すると警告した。共同通信は、6月24日の年次株主総会で、同自動車メーカーが2025年4月から6月の間に約2,000億円の純損失を見込んでいることが確認されたと報じている。日産はこの重要な時期を乗り切るために、日産の戦略は、事業の合理化、資源の最適化、イノベーションの促進に焦点を当て、投資家の信頼を回復し、全体的なパフォーマンスを向上させることになる。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
起亜自動車、EV4セダンとピックアップトラック「タスマン」の生産仕様を公開
2025年6月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ヨーロッパ-オーストラリア-韓国現代自動車|売上高、ライトビークル、、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化
Stephanie Brinley, Associate Director

起亜株式会社
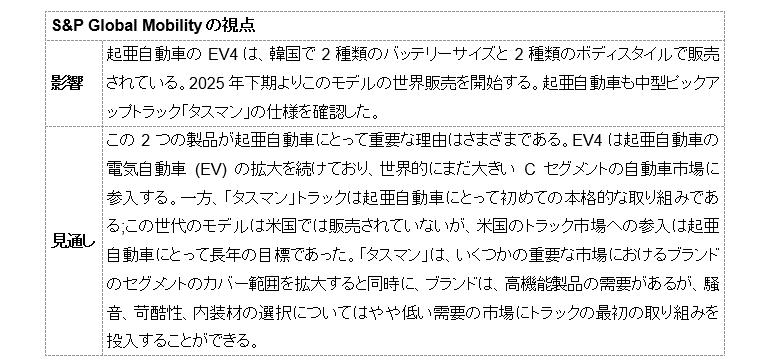
起亜自動車のEV4は、韓国で2種類のバッテリーサイズと2種類のボディスタイルで販売されている。2025年下期よりこのモデルの世界販売を開始する。企業の声明によると、起亜自動車は、中型ピックアップトラック「タスマン」の仕様も確認したという。
EV4:技術レベルの高いコンパクトセダンとハッチバックEV、2つのバッテリーサイズ
EV4は起亜自動車のE-GMPプラットフォームの恩恵を受け、市場に応じてセダンとハッチバックのラインナップに加わる。この4ドアセダンは韓国で販売されており、北米での販売も計画されている;欧州向けに5ドアハッチバックが開発されている。北米、欧州では2025年末までに販売開始;韓国での販売は始まったばかりである。起亜自動車のホ・ソン社長兼最高経営責任者は声明で、「起亜自動車はEV4で、最先端のデザインと先進的なデジタル技術、魅力的なユーザー機能を独自に融合させ、Cセグメントの電気セダン部門を変革するための細部を惜しまなかった。新しい世代のドライバーのニーズを満たすために作られたEV4は、起亜自動車の受賞歴のある電気自動車のグローバルなラインナップの深みと魅力を大幅に広げる。 EV4はまた、革新的で刺激的な持続可能なモビリティソリューションをすべての人に提供し、世界をリードするという起亜自動車の大胆なミッションの次の段階を強調している」と述べた。Cセグメントにおいて、EV4は起亜自動車のEVがまだ占有していない領域に、より小型で手頃な価格の製品として進出する。
EV4の外観はEV6のファミリールックを踏襲しており、空気力学的な形状とフルアンダーボディーカバーにより、抗力係数はわずか0.23となっている。EV4は持続可能なリサイクル素材を多用している。フロントバンパー、リアバンパー、サイドガーニッシュには、自動車の内装材から発生するリサイクル材を20%使用している。起亜自動車のカリム・ハビブ氏をデザインセンター長は、「EV4のすべてのラインと表面は、見た目のインパクトだけでなく、空力効率を最適化するために彫刻されている。同時に、当社は、同車両全体にリサイクル素材を取り入れるなど、持続可能性を重視している。EV4のデザインは、起亜自動車の未来のビジョンと、効率的で環境に責任があり、感情的に魅力的な顧客中心の車両を作るという当社の揺るぎない決意を反映していまる」と述べた。EV4では、起亜自動車はフロントフェンダーに充電ドアを配置している;手動ドアには、車両の状態をより確認しやすいように充電状態インジケータが強化されている。起亜自動車はEV4のすべてのトリムレベルに先進的なLED照明システムを採用しており、自動感知式のフロント照明システム (インテリジェントフロントライティングシステム [IFS] ) もオプションとして提供している。IFSはハイビームを20の個別に制御されたセグメントに分割する。この照明システムはこのセグメントでは一般的ではなく、どのセグメントでも通常期待されるよりも高いコンテンツと価値を提供するという起亜自動車のアプローチをさらに推し進めるものである。フロント照明用ロービームモジュールは、起亜自動車が「Total Inner Reflection (TIR) 」と呼ぶ新技術である;照明効率の向上、消費電力の削減、照明ユニットの軽量化を実現している。北米以外では、このモデルは、フローティングタイプのテールライトが採用されている。このシステムは、先進的なベゼル構造によってリアサイドのストップライトの視認性を高める。EV4では、オプションのフロントおよびリアのダイナミックウェルカムライトとエスコートライトを使用して、動きのある点灯パターンを設定できる。

2026年起亜・EV4 出典:起亜株式会社
インテリアには、フロントシートをリクライニングできるレストモードや、駐車中に落ち着いた雰囲気になるように照明やディスプレイの設定を調整できるレストモードなど、Cセグメントのスタンダードエントリーにはない快適性を追求した興味深い機能が搭載されている。センターコンソールにはスライドテーブルも付いている;起亜自動車によると、このレイアウトは「室内を動きにも静止にも適した空間に変える」という。インテリアの周囲光はドアトリムに埋め込まれ、2層構成になっている。超薄型フロントシートは、後方視界と2列目乗客の足元スペースを改良する。EV4はEVプラットフォームとして、ゴルフバッグなどの大きな荷物をより収納しやすい広い開口部と広いスペースを備えている。セダンの荷物容量は490リットル、ハッチバックは435リットルのトランクスペースがある。超薄型のウィングレスエアベントと、インフォテインメントと気候のコントロールを統合したタッチスクリーンを搭載している。

2026年起亜・EV4 出典:起亜株式会社
ほとんどの市場では、3つのトリムレベルが提供される。米国では「Light」「Wind」「GT-Line」が、欧州では「Air」「Earth」「GT-Line」トリムレベルが提供される。起亜自動車は将来的にGT版を出すことを約束していないが、これは助けになるかもしれない。EV4は、800V技術を採用したより大型で高価なEV6やEV9とは異なり、400Vアーキテクチャを採用している。バッテリー容量は標準モデルが58.3 kWh、長距離モデルが81.4 kWhである。いずれの場合も、150 kWの前輪駆動 (FWD) モータが使用される。セダンの場合、標準航続距離モデルは世界統一軽自動車試験手順 (WLTP)サイクルで430 km、長距離バリアントは630 kmの航続距離を誇る。同ハッチバックはある程度距離が減り、短距離モデルが410 km、長距離バリアントが590 kmとなっている。起亜自動車はEV4で、回生ブレーキシステムの性能を向上させ、「i-Pedal 3.0」と名付け、これにより、ゼネラルモーターズ (GM) などが提供するワンペダル駆動に近づいた。起亜自動車によると、i-Pedal 3.0システムは、システムの設定を調整し、ドライビングスタイルに合わせる柔軟性が高いという。充電時間は、標準型セダンで10%から80%まで29分、長距離型セダンまたはハッチバックで31分となっている。AC充電で10%から100%まで充電するのにかかる時間は、標準航続距離車両で5時間20分、長距離航続距離モデルで7時間15分である。起亜自動車の他のEVと同様に、ヴィークル・ツー・ロードとヴィークル・ツー・グリッド機能がある。他のE-GMP車と比較して、EV4は新しい油圧モーターマウントとモーターサポートの軽量アルミブラケットを採用している。0-100 km/h加速時間は標準車が7.4秒、長距離車が7.7秒である。
起亜自動車のハイウェイ・ドライビング・アシスト2システムは、12インチのヘッドアップディスプレイとともにEV4に搭載される。先進運転支援システム (ADAS) には、ハンドルとドライバーの手の接触を感知するハンドルのハンズオン検出機能も搭載されている。このサイズクラスでシステムを利用できるようになったことは、消費者がこのような技術を最上級モデルだけでなく、より小さな車でも利用できるようにすることを求めていることをさらに強調しており、また、一般的により高いEVの価格に見合う魅力的な技術を確保するための起亜自動車の取り組みでもある。EV4には、駐車中に利用できるシアターモードなど、新世代のインフォテインメントシステムが搭載されている。車載ストリーミングは、インストルメントクラスターやヘッドアップディスプレイを含むオーディオ、ビデオ、ナビゲーション、テレマティクス (AVNT) システム上で表示できる。高度な音声認識機能により、一部の車両機能を音声で制御でき、デジタルキー2.0が利用可能である。もちろん、EV4には無線通信 (OTA) やオンデマンドのアップデート機能も組み込まれている。
EV4セダンは、全長4,730 mm、全高1,480 mmである。ハッチバックは全長4,430 mm、全高1,485 mmだが、車幅1,860 mm、ホイールベース2820 mmとなっている。
起亜自動車、中型ピックアップトラック「タスマン」を発売へ
「タスマン」は、起亜自動車初のピックアップトラックで、韓国、欧州、オーストラリア、中東、アフリカで販売される予定である-が、北米では販売されなく、北米では長年にわたって「チキン税」が課せられており、ピックアップトラックの米国への輸入には25%の関税がかかっているからである。チキン税は1960年から課税されており、いくつかの自動車メーカーが競争の激しい米国のトラック市場に小型トラックを輸入するのを妨げている。「タスマン」は伝統的なトラック式で、強化されたボディ・オン・フレーム構造を採用している。積載能力は1,151 kgまで、牽引能力は3,500 kgまでである。「タスマン」は全長5,410 mm、全幅1,920 mm、ホイールベース3,270 mmである。高さはトリムレベルとルーフラックによって異なり、1,870 mm~1,920 mmである。
起亜自動車は、「タスマン」は同社が生産した車両の中で最もオフロード性能が高く、同モデルは、性能を前面に押し出して開発されたと説明している。オフロード仕様には、水上歩行機能、2速アクティブトランスファーケース (ATC)、電動ロッキングディファレンシャル、テレインタイヤが含まれる。ATCは、このタイプのトラックでは一般的な4つのドライブモード(2H、後輪駆動;4H、ハイレンジ四輪駆動;4L、ローレンジ四輪駆動;および4A、自動全輪駆動)を有効にする。中東とアフリカで販売されているタスマン車両は、砂丘用に調整されたデザート・ドライブ・モードを備えており、追加の冷却ニーズに対応するために水冷オイルクーラーを備えている。「タスマン」はX-Trekモードと呼ばれる低速 (最高時速10 km) オフロードのクルーズコントロールも備えている。X-Proモデルは、より高い最低地上高 (252 mm) とアグレッシブなアプローチ、ディパーチャー、ランプオーバーアングルにより、不整地にさらに最適化されている。フロントサスペンションは、フロントにハイマウントのダブルウィッシュボーン、リアにリーフスプリングを備えたリジッドアクスルを採用している。ショックアブソーバーには、さまざまな路面での乗り心地を実現するために、周波数感応バルブとウレタン製バンプストップを採用している。タイヤはトリムレベルに固有である;標準的なトラックにはハイウェイテレインタイヤが搭載されているが、X-Proには大径のオールテレインタイヤが搭載されている。

2026起亜・タスマン 出典:起亜株式会社
エンジンの可用性も市場によって異なる。韓国において、「タスマン」は、281 PSの2.5リッター4気筒ガソリンエンジンと8速トランスミッションを搭載する。オーストラリアは排気量2.2リットル、出力210 PS、8速トランスミッションを搭載する。他の一部の市場では、これらのエンジンのいずれかを選択することができ、ディーゼルバージョンには6速マニュアルトランスミッションを選択することができる。牽引能力をサポートするために、トレーラーブレーキコントロールとトレーラースタビリティアシストを装備している。積載空間(ベッド)には、木製パーティション用の仕切りスロット、タイダウンフックとカーゴレール、ベッドライナー、サイドマウント照明、220Vインバーターが装備されており、運搬装置の準備ができている。起亜自動車は、スポーツバー、ベッドカバー、スライドトレイ、サイドステップだけでなく、キャンプ用品のアクセサリーも開発したという。

2026起亜・タスマン 出典:起亜株式会社
「タスマン」には起亜自動車のConnected Car Navigation Cockpit (ccNC) とハーマンカードンプレミアムサウンドが搭載され、折りたたみ式のコンソールテーブルと後部座席下のシート下収納も備えている。リアドアは80度まで開くワイドオープンヒンジである。
見通しと影響
この2つの製品が起亜自動車にとって重要な理由はさまざまである。EV4は起亜自動車のEVラインアップを拡大し続けており、世界的にまだ大きいCセグメントの自動車市場に参入する。一方、「タスマン」トラックは起亜自動車にとって初めての本格的な取り組みである;この世代のモデルは米国では販売されていないが、米国のトラック市場への参入は起亜自動車にとって長年の目標であった。「タスマン」は、いくつかの重要な市場におけるブランドのセグメントのカバー範囲を拡大すると同時に、ブランドは、高機能製品の需要があるが、騒音、苛酷性、内装材の選択についてはやや低い需要の市場にトラックの最初の取り組みを投入することができる。
タスマンは2024年10月に初めて公開された (韓国:2024年10月29日:起亜自動車初のピックアップトラック「タスマン」が世界デビュー参照)、起亜自動車初のトラックとしては印象的な機能と性能を備えている。起亜自動車はトラック方式を忠実に守っているように見えるので、市場の受け入れは改善されるだろう。起亜自動車は、最終的には米国でもピックアップトラックを販売する予定だと伝えられているが、これは「タスマン」ではない (米国:2025年4月10日:起亜自動車は最終的に米国で9万台のEVピックアップトラックを販売することを目指している-報道参照)。
EV4は2月に発表された (韓国-スペイン:2025年2月28日:起亜自動車は新しいEV4とコンセプトEV2モデルを発表参照)し、起亜自動車のEVの存在感を「タスマン」よりも多くの市場で、より多くの市場セグメントに拡大する仕事をしている。EV4は基本的に、K4内燃エンジン (ICE) セダンと同じ位置に収まる。米国市場向けモデルは4月に公開されており、起亜自動車はまず関税をかけずに米国への輸出を進める意向を明らかにした (米国:2025年4月17日:ニューヨーク・オートショー2025:現代自動車、ジェネシス、起亜自動車が再びリードおよび米国:2025年4月18日:キアアメリカCOO、同社は安定した売り上げで関税を乗り切れると語る参照) 。
グローバルベースでは、「EV4」は、2029年までに96,000台の販売が見込まれており、販売台数は引き続き増加する見込みである。2029年には「EV4」の販売台数は、起亜自動車の世界販売台数の3.1%程度に達すると予測される。「タスマン」は低水準の販売台数見通しで、2029年の販売台数が約26,000台と予測されている。しかしながら、低水準の販売台数とはいえ、「タスマン」は起亜自動車がピックアップトラックの有力なライバルとしての地位を確立する上で重要である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、フルサイズSUV「アルマーダNISMO」を発表
2025年6月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国
日産自動車株式会社|売上高、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)
Stephanie Brinley, Associate Director
2026年モデル イヤー(MY) では、日産はアルマーダNISMOバージョンを設定し、大型SUVのスポーティな要素の取り込みを図った。アルマーダNISMOツインターボ3.5リットルV6は、ベースエンジンと同じ基本エンジンだが、日産のプレスリリースによると、NISMOのエンジニアが最適化した結果、ベースエンジンより35馬力アップし、460馬力になるという。日産によると、エンジンプログラムの変更やバルブクリアランスの微調整により、プレミアムグレードのガソリンを使って追加出力を確保できるという。エグゾーストをリチューンすると、より大きくアグレッシブなサウンドになる。日産によると、アクティブサウンドエンハンスメントは「エンジン音を増幅し、搭乗者全員をワクワクさせる」という。電動パワーステアリングをスポーティーに、アダプティブエレクトロニックエアサスペンションを採用することで、よりレスポンスの良いドライビングエクスペリエンスを提供するという。アルマーダNISMOは22インチホイールとオールシーズン用の高性能タイヤを装備している。よりアグレッシブな外観を作り出すためのデザインのヒントが豊富にある。日産のNISMOチームによって、フロントとリアのファシア、グリル、サイドステップ、リアスポイラーが改良された。これらの変更は、機能的な変更ではないが、「より性能を重視した外観」を作り出すと日産は述べた。フェンダーフレア、LEDフロントフォグランプ、赤塗装ブレーキキャリパーも標準装備している。インテリアは特殊なキルティングレザーと赤のアクセントとステッチが施されている。シートにはサイドのボルスターも追加されており、前席の乗客を固定するのに役立つ。エクステリアは、370ZやGT-Rの日産・NISMOの加工を彷彿とさせるスポーツのアクセントとトリムが施されている。日産はこれまで、「セントラ」「370Z」「GT-R」「ジューク」などの車種を中心にNISMOの扱いを受けてきた。アルマーダNISMOは2025年第3四半期に米国で発売される。 オートモーティブ・ニュースは、日産のアルマーダのマーケティング・マネージャー、ブライアン・ヨッケル氏の発言として、NISMOは3列シートSUVセグメントに「自己表現の香り」をもたらすと伝えた。この報道によると、日産はNISMOがアルマーダの米国での販売台数の約5%を占めると予想している。
重要性: 日産は、フルサイズSUVのパワフルモデルとオフロード向けモデルの両方を提供するというトレンドに乗ろうとしている;アルマーダはまた、日産が長年培ってきたオフロードでの評価と、何十年にもわたる全地形対応SUV「パトロール」をベースにしたPRO-4Xバージョンとともに発表された。性能重視のフルサイズSUVのトリムレベルの例は数多くあるが、アルマーダNISMOはこのトレンドに遅れて追随しているようで、外観はぎこちなく見える。これらの高性能のオンロードSUVは、価格帯の最上位で販売することができ、利益率を最大化することができるが、設計とエンジニアリングのコストは増加するだけである。しかしながら、V6の460馬力は、キャデラック・エスカレードVやBMWやメルセデス・ベンツの大型SUVほどではないにしても、GMのシボレー・タホやGMCユーコンの上位エンジンよりは高い。最新世代は2024年9月に発表された (サウジアラビア-アラブ首長国連邦-米国:2024年9月4日:日産、新型パトロール、米国市場向けアルマーダを発表参照) 。世界的には、アルマーダとパトロールは日産にとって重要な製品であり、何十年にもわたってその能力に敬意を払ってきた。同時に、ドライビングダイナミクスは競合他社よりも精度が低いことが多い;NISMOバージョンのシャーシのチューニングを変更することで、これらの問題の一部を解決できる可能性がある。

2026日産・アルマーダNISMO 北米日産会社
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
KGモビリティ、2030年までの新車投入で持続的成長に向けた野心的なロードマップを発表
2025年6月18日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
企業、販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst

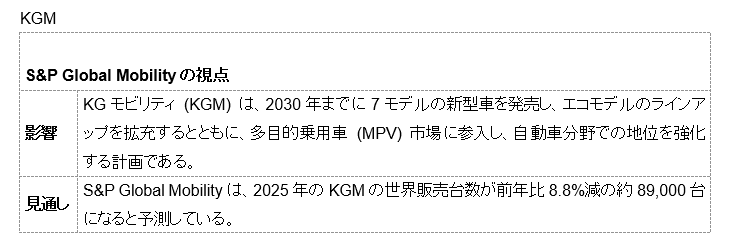
KGモビリティは、2030年までに7モデルの新車を発売するという野心的な目標を掲げており、自動車産業の持続的成長と革新に向けた重要な転換点となっているとBusiness Korea Daily Newsは報じている。2022年にKGグループに買収されて以来、変貌を遂げてきた同自動車メーカーは、従来のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)中心の商品ラインアップからMPVへと拡大し、多様な消費者ニーズに対応することを目指している。
6月17日、大韓民国 京畿道平沢市のKGM本社で開催されたイベント「KGM FORWARD」において、KGMは中長期的なロードマップを発表し、環境に優しい技術への取り組みを強調した。クァク・ジェソン会長は、同自動車メーカーの波乱に満ちた歴史を認めながらも「2022年にKGグループに入り、診断に力を入れてきたが、今年で3年目を迎え、治療を開始する。」とし、未来を楽観した。この比喩は、KGMの再生と成長に向けた戦略的方向転換を強調している。
KGMの戦略には、BYDや奇瑞汽車などの中国自動車メーカーを中心としたグローバルパートナーとの連携強化が含まれている。これらの提携により、KGMはハイブリッド車とレンジエクステンダー搭載車(REEV)の開発能力を強化し、環境に優しい輸送オプションに対する需要の高まりに対応することが期待される。来年は、奇瑞汽車と共同開発した中大型ハイブリッドSUV「SE10」を皮切りに、「コランド」の後継モデルである「KR10」を投入する計画である。
同自動車メーカーはまた、MPV市場にも参入しており、ファミリー向けやレジャー向けの車種とのギャップを認識している。KGMのクァク・ジョンヒョン事業戦略部門長は、「国内MPV市場は、学齢期の子供や親の介護、レジャー活動などの需要が増えると予想されるが、消費者が利用できるモデルが多くない。当社は、新型MPVを投入し、成長するミニバン市場で消費者の選択肢を広げていく」と述べた。 KGMのイノベーションへのコミットメントは、ハイブリッド車のラインナップを強化する計画によってさらに強調されている。同自動車メーカーは、韓国最大の1.83 kWhのバッテリー容量を誇るハイブリッドシステム技術を活用し、REEVやプラグインハイブリッド車 (PHEV) を開発している。KGMのクォン・ヨンイル技術研究所長は、頻繁に充電しなくても電気だけで走行できるデュアル技術の可能性を強調した。
KGMは車種の拡充に加え、KGMエクスペリエンスセンターなどを通じて顧客体験の向上を目指している。2027年までにこれらのセンターの数を全国で2カ所から10カ所以上に増やす。自動車保有の経済的負担を減らすためのサブスクリプションサービス「KGMモービル」の導入も視野に入れている。 グローバル戦略の一環として、KGMは欧州とアジア市場の両方でのプレゼンスを高めることを目指している。現在、同自動車メーカーは、73カ国に輸出しているが、年内に98カ国に増やす計画である。この目標を支援するために、KGMは最近、インドネシアとイタリアで事業を拡大した。ドイツにも子会社を設立しており、ドバイにも新たな子会社を開設する計画である。前述したように、この積極的なグローバル展開と多角化により、2024年の同自動車メーカーの営業利益は123億ウォン (890万米ドル)、純利益は462億ウォンに達した。昨年の総輸出台数は前年比18.2%増の62,378台であった。今年は9万台以上の輸出を目指す。
見通しと影響
KGMの戦略的な方向転換は、持続可能性と消費者の好みが最も重要である進化する自動車業界への積極的なアプローチを反映している。KGMは、MPVやハイブリッド車などの車種を拡充することで、市場のギャップに対応するだけでなく、世界的なエコ輸送の潮流にも対応している。BYDや奇瑞汽車など中国の大手自動車メーカーとの提携は、KGMの技術力を高め、競争力のある市場への参入を加速する戦略的な動きである。
さらに、KGMエクスペリエンスセンターやKGMモバイルのサブスクリプションサービスなど、顧客中心の取り組みを導入しており、顧客エンゲージメントと満足度を高めるための同自動車メーカーのコミットメントを示している。全体として、KGMのロードマップは、ブランドを再活性化し、自動車業界における持続可能な成長を実現するための包括的な戦略を示している。
S&P Global Mobilityは、2025年のKGMの世界販売台数が前年比8.8%減の約89,000台になると予測している。今後、KGMのグローバル年間販売台数は2026~2030年に81,000台~89,000台の間で変動すると予想される。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、インドへのコミットメントを確認、2027年までに新型3車投入を目指す
2025年6月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
日産自動車株式会社|施設・運営、市場分析、製品
Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst
日産自動車はインド市場へのコミットメントを確認し、グローバルCEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、同社が明確な製品導入計画を持っており、撤退の憶測にもかかわらずインドに留まる意向であると述べた。同氏は、日産にとってのインドの重要性を強調し、今後18ヶ月から24ヶ月の間に、インド市場向けだけでなく、さまざまな国への輸出を促進する重要な製品を発売する計画を説明した。同自動車メーカーはその期間内に、多目的車 (MPV)、5人乗りのスポーツ用多目的車 (SUV)、7人乗りのSUVの3モデルを発売する計画であるとThe Economic Timesは報じている。
重要性: これは、日産が保有していたタミル・ナードゥ州の製造合弁会社(JV)ルノー日産オートモーティブ・インディア社の株式51%をルノーが取得したことに伴い実現したもので、ルノーはこの合弁会社を100%保有し、日産の受託製造会社となる(インド:2025年5月21日:ルノーはインドJVの残りの株式取得についてCCIの承認を求めている参照)。インドの乗用車市場では、昨年度(FY)の販売台数が27,881台と苦戦を強いられているが、2025年度の出荷台数は71,334台と、引き続きインドを代表する輸出企業である。エスピノサ氏は販売拡大に楽観的で、2027年末までに年間販売台数を現在の3倍の10万台に引き上げることを目指している。日産は現在、現地生産のコンパクトSUV「マグナイト」を販売し、SUV「エクストレイル」を輸入している。また、同社は、チェンナイにあるルノー日産テクノロジー&ビジネスセンターを車両の開発・生産に活用し、インドの技術力を活用する計画である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
KGモビリティ、2030年までの新車投入で持続的成長に向けた野心的なロードマップを発表
2025年6月18日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
企業、販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst

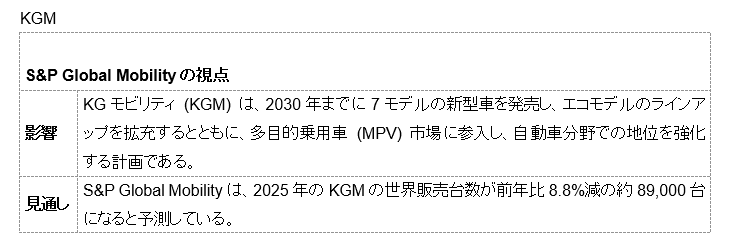
KGモビリティは、2030年までに7モデルの新車を発売するという野心的な目標を掲げており、自動車産業の持続的成長と革新に向けた重要な転換点となっているとBusiness Korea Daily Newsは報じている。2022年にKGグループに買収されて以来、変貌を遂げてきた同自動車メーカーは、従来のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)中心の商品ラインアップからMPVへと拡大し、多様な消費者ニーズに対応することを目指している。
6月17日、大韓民国 京畿道平沢市のKGM本社で開催されたイベント「KGM FORWARD」において、KGMは中長期的なロードマップを発表し、環境に優しい技術への取り組みを強調した。クァク・ジェソン会長は、同自動車メーカーの波乱に満ちた歴史を認めながらも「2022年にKGグループに入り、診断に力を入れてきたが、今年で3年目を迎え、治療を開始する。」とし、未来を楽観した。この比喩は、KGMの再生と成長に向けた戦略的方向転換を強調している。
KGMの戦略には、BYDや奇瑞汽車などの中国自動車メーカーを中心としたグローバルパートナーとの連携強化が含まれている。これらの提携により、KGMはハイブリッド車とレンジエクステンダー搭載車(REEV)の開発能力を強化し、環境に優しい輸送オプションに対する需要の高まりに対応することが期待される。来年は、奇瑞汽車と共同開発した中大型ハイブリッドSUV「SE10」を皮切りに、「コランド」の後継モデルである「KR10」を投入する計画である。
同自動車メーカーはまた、MPV市場にも参入しており、ファミリー向けやレジャー向けの車種とのギャップを認識している。KGMのクァク・ジョンヒョン事業戦略部門長は、「国内MPV市場は、学齢期の子供や親の介護、レジャー活動などの需要が増えると予想されるが、消費者が利用できるモデルが多くない。当社は、新型MPVを投入し、成長するミニバン市場で消費者の選択肢を広げていく」と述べた。 KGMのイノベーションへのコミットメントは、ハイブリッド車のラインナップを強化する計画によってさらに強調されている。同自動車メーカーは、韓国最大の1.83 kWhのバッテリー容量を誇るハイブリッドシステム技術を活用し、REEVやプラグインハイブリッド車 (PHEV) を開発している。KGMのクォン・ヨンイル技術研究所長は、頻繁に充電しなくても電気だけで走行できるデュアル技術の可能性を強調した。
KGMは車種の拡充に加え、KGMエクスペリエンスセンターなどを通じて顧客体験の向上を目指している。2027年までにこれらのセンターの数を全国で2カ所から10カ所以上に増やす。自動車保有の経済的負担を減らすためのサブスクリプションサービス「KGMモービル」の導入も視野に入れている。 グローバル戦略の一環として、KGMは欧州とアジア市場の両方でのプレゼンスを高めることを目指している。現在、同自動車メーカーは、73カ国に輸出しているが、年内に98カ国に増やす計画である。この目標を支援するために、KGMは最近、インドネシアとイタリアで事業を拡大した。ドイツにも子会社を設立しており、ドバイにも新たな子会社を開設する計画である。前述したように、この積極的なグローバル展開と多角化により、2024年の同自動車メーカーの営業利益は123億ウォン (890万米ドル)、純利益は462億ウォンに達した。昨年の総輸出台数は前年比18.2%増の62,378台であった。今年は9万台以上の輸出を目指す。
見通しと影響
KGMの戦略的な方向転換は、持続可能性と消費者の好みが最も重要である進化する自動車業界への積極的なアプローチを反映している。KGMは、MPVやハイブリッド車などの車種を拡充することで、市場のギャップに対応するだけでなく、世界的なエコ輸送の潮流にも対応している。BYDや奇瑞汽車など中国の大手自動車メーカーとの提携は、KGMの技術力を高め、競争力のある市場への参入を加速する戦略的な動きである。
さらに、KGMエクスペリエンスセンターやKGMモバイルのサブスクリプションサービスなど、顧客中心の取り組みを導入しており、顧客エンゲージメントと満足度を高めるための同自動車メーカーのコミットメントを示している。全体として、KGMのロードマップは、ブランドを再活性化し、自動車業界における持続可能な成長を実現するための包括的な戦略を示している。
S&P Global Mobilityは、2025年のKGMの世界販売台数が前年比8.8%減の約89,000台になると予測している。今後、KGMのグローバル年間販売台数は2026~2030年に81,000台~89,000台の間で変動すると予想される。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、インドへのコミットメントを確認、2027年までに新型3車投入を目指す
2025年6月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
日産自動車株式会社|施設・運営、市場分析、製品
Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst
日産自動車はインド市場へのコミットメントを確認し、グローバルCEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、同社が明確な製品導入計画を持っており、撤退の憶測にもかかわらずインドに留まる意向であると述べた。同氏は、日産にとってのインドの重要性を強調し、今後18ヶ月から24ヶ月の間に、インド市場向けだけでなく、さまざまな国への輸出を促進する重要な製品を発売する計画を説明した。同自動車メーカーはその期間内に、多目的車 (MPV)、5人乗りのスポーツ用多目的車 (SUV)、7人乗りのSUVの3モデルを発売する計画であるとThe Economic Timesは報じている。
重要性: これは、日産が保有していたタミル・ナードゥ州の製造合弁会社(JV)ルノー日産オートモーティブ・インディア社の株式51%をルノーが取得したことに伴い実現したもので、ルノーはこの合弁会社を100%保有し、日産の受託製造会社となる(インド:2025年5月21日:ルノーはインドJVの残りの株式取得についてCCIの承認を求めている参照)。インドの乗用車市場では、昨年度(FY)の販売台数が27,881台と苦戦を強いられているが、2025年度の出荷台数は71,334台と、引き続きインドを代表する輸出企業である。エスピノサ氏は販売拡大に楽観的で、2027年末までに年間販売台数を現在の3倍の10万台に引き上げることを目指している。日産は現在、現地生産のコンパクトSUV「マグナイト」を販売し、SUV「エクストレイル」を輸入している。また、同社は、チェンナイにあるルノー日産テクノロジー&ビジネスセンターを車両の開発・生産に活用し、インドの技術力を活用する計画である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
起亜自動車、「PV5 PBV」の価格と仕様を発表
2025年6月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
現代自動車|企業、販売、展示・発売、ライトビークル、製品、電動化、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
起亜自動車初のEVのpurpose-built vehicle (PBV) であるPV5の仕様と価格を公開し、本日 (6月10日) から予約受付を開始したと、Business Korea Daily Newsは報じている。乗用車(5人乗り、2-3-0)とカーゴ (ロング) モデルを全てのラインアップの中で最初に導入し、今後もラインアップを拡大していく。PV5は現代自動車グループのElectric-Global Modular Platform for Service (E-GMP) をベースに開発されており、E-GMP.Sは、さまざまな車体を柔軟に組み合わせることができる電動スケートボード専用アーキテクチャである。この車両には、顧客や業界パートナーと共同で開発した高度なハードウェアとソフトウェアソリューションが統合されている。これにより、最初から実際のユーザー要件を満たすことができる。助手席モデルは、広い室内空間と広い2,995 mmのホイールベースを採用し、多様な乗客ニーズに対応できる多様なシート構成を可能にしている。トランク容量は、1,330リットルから2列目シートを収納した場合の最大2,310リットルまである。最大出力120 kW、最大トルク250 Nmの電気モーターを搭載し、「PV5」は71.2 kWhのバッテリーで一回の充電で358 kmの走行が可能で、韓国産業通商資源部の認証を取得している。貨物モデルも同様に印象的で、広々とした貨物エリアと低い積載高さでビジネスオペレーションを最適化するように設計されている。全長4,695 mmのカーゴスペースは最大長2,255 mm、積載量4,420リットルである。同モデルは2つのバッテリーオプションを提供する:一回の充電で377 km走行可能な71.2 kWhの長距離モデルと、一回の充電で280 km走行可能な51.5 kWhの標準モデルがある。どちらのモデルも、350 kWの急速充電器を使用して約30分で10%から80%まで充電できるため、ユーザーのダウンタイムを最小限に抑えることができる。起亜自動車はまた、Android Automotive OS (AAOS) をベースにしたPBV専用インフォテインメントシステムや、サードパーティーアプリケーションのためのアプリマーケットなど、PBV専用の機能を「PV5」に統合した。また、「PV5」は現代自動車グループと42dotが共同開発した車両制御ソリューション「Pleos Fleet」を導入し、リアルタイムのテレマティクスにより複数の車両を効率的に管理することができる。PV5の価格は、基本モデルが約4,709万ウォン、プラスモデルが約5,000万ウォンからと競争力がある。カーゴモデルの価格は、標準モデルが約4,200万ウォン、長距離モデルが約4,470万ウォンからである。「PV5」は、韓国のEV税制優遇と政府補助金の適用を受けることができ、車両価格をさらに下げることができる。
重要性: 起亜自動車は、2022年に初モデル「ニロプラス」を発売し、PBV分野で躍進した。ロッテグローバルロジスティクス、クーパン、CJロジスティクス、DHLコリアなどの大手物流会社と提携し、持続可能な物流に特化した車両を開発している。これらの取り組みは、物流業界における持続可能な輸送ソリューションを推進するという起亜自動車のコミットメントを強調している。起亜自動車は、2030年までにPBV市場のリーダーになることを目指しており、2023年4月に初のEVのPBV専用工場の起工式を行い、その土台を作った。新しいPV5は、起亜自動車の自動車戦略を超えた野心的なプラットフォームの最初のモデルであり、卓越した柔軟性とモジュール性で多様な顧客ベースに対応するように設計されている。S&P Global Mobilityのライトビークルデータによると、起亜自動車の「PV5」の世界販売台数は今年約3,100台で、2026年には約17,000台に増える見通しであるという。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタとダイムラー・トラック、日野・三菱ふそうの合併契約を締結
2025年6月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本
日野自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、ダイムラー・トラック|合併・買収 (M&A)、施設・運営、生産、経費、企業、研究開発、JV/提携、コンポーネント、財務、販売、市場、中型&大型商用車、人事、製品、テクノロジー、パワートレイン、コーポレート
Ian Fletcher, Principal Analyst

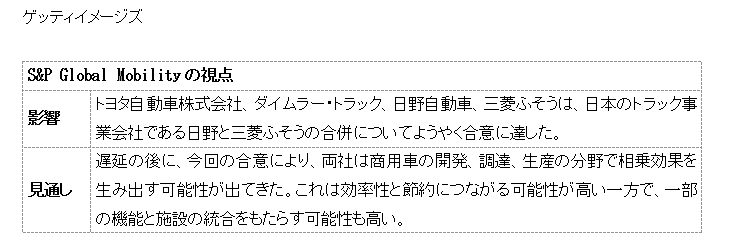
トヨタ自動車株式会社、ダイムラー・トラック、日野自動車、三菱ふそうは、日本のトラック事業会社である日野と三菱ふそうの合併についてようやく合意に達した。両社は共同声明で、今回の最終合意により、日野と三菱ふそうは「対等な立場で統合し、商用車の開発・調達・生産の分野で協力する」と述べた。この力の結集は、「すべての利害関係者の利益のために、新しい強力な日本のトラック大国を確立する」と付け加えた。
両トラックメーカーは新たに上場する持ち株会社に完全子会社化される。計画では、トヨタとダイムラー・トラックが25%ずつ持ち株会社を保有し、三菱ふそうの現CEOカール・デッペン氏が率いる。持株会社は2026年4月の営業開始を予定しており、東京証券取引所プライム市場 (TSE) への上場を予定している。新しい持ち株会社の名前を含む、提携の範囲と性質に関する詳細は、今後数ヶ月以内に発表される予定である。同取引には、関連する取締役会、株主、当局の承認も必要となる。
ダイムラー・トラックのCEOカリン・ラドストロム氏は声明で、「今回決定した三菱ふそうと日野自動車の統合は、本当に歴史的なものである。両社は、2つの強力なパートナーを統合して、さらに強力な企業を形成し、輸送の脱炭素化を成功させる」と述べた。「三菱ふそうと日野自動車は、ともに規模を活用する大きな可能性を秘めている-そして規模は、業界の技術的変革に勝利するための鍵である。」と同氏は付け加えた。さらにラドストロム氏は、「カール・デッペン氏は、当社のビジネスのバリューチェーン全体を理解している経験豊富で強力なリーダーであり、新会社を次のレベルに引き上げることができると確信している。」と述べた。
日野の小木曽聡社長も声明で、「4社のコラボレーションはまさに「千載一遇のチャンス」である。事業シナジーだけでなく、異なる文化や環境との出会いや融合による相乗効果は計り知れない。お互いに共感し合い、同じ志を持って社会に貢献する、強くたくましいチームになると確信している。日本に根ざした新しい商用車カンパニーとして、より良い未来を共に創っていく」と述べた。
見通しと影響
ついに署名された協定は作成に2年かかった。2023年5月には、トヨタ、日野、ダイムラー・トラック、三菱ふそうの間で、自動車の開発・調達・生産における日野と三菱ふそうの合併・協業や、様々な技術分野での協力に関する覚書(MoU)を締結したことを発表していた(日本:2025年5月31日:MFTBCと日野、業務統合、CASE技術で協力参照)。最終的な合意は2024年の第1四半期に署名され、2024年末までに完了すると予想されていた。遅れの一部は、2022年の第1四半期以来日野を悩ませてきたエンジン認証と排ガス問題の影響など、契約に関する複雑さに関連しているようである。
当然のことながら、両社が発表した声明は、合併後の事業の規模とリソースから得られるメリットを強調しようとしている。両社は、日野と三菱ふそうの統合により、車両開発、調達、生産の3つの重点分野で「事業の効率化を目指す」としている。両社は、「日本の商用車メーカーの競争力を大幅に高め、日本とアジアの自動車産業の基盤を強化することが期待される」と付け加えている。
しかしながら、想定されている大幅な効率化を達成するためには、取引後の数年間に影響が出る可能性が高い。確かに、当初は一部の機能を独立させたままにする可能性が高いが、特定の管理領域の統合によるコスト削減の機会は避けられないようである。一方、日野と三菱ふそうの製品ラインアップは、特に国内の軽・中・大型トラック分野で重複しているため、シャシー、キャブ、パワートレインなどの主要コンポーネントのエンジニアリングと開発が統合されるのは時間の問題である。これにより、日野と三菱ふそうは、特に多くの市場で法的環境が厳しくなっていることを考慮して、両社が持っているエンジニアリング予算でより多くのことを達成することができる。声明は、「新持株会社は、水素をはじめとするCASE技術(Connected(コネクティッド)、, Autonomous(自動化)、, Shared(シェアリング)、 Electric(電動化))の開発を通じて、持続可能で豊かなモビリティ社会の実現とグローバルな商用車事業の強化に努めるとともに、カーボンニュートラルや物流効率化など商用車を取り巻く課題の解決に貢献することで、顧客、様々なステークホルダー、自動車業界に誇りを持って貢献していく」と述べ、これが何をもたらすかについてのヒントを与えた。
生産面での協力は、日野と三菱ふそうの現在の足跡をある程度統合する可能性も示唆している。実際、日野は2025年に4工場で車両を生産しており、そのうち2工場ではバスと普通車を生産し、羽村工場では小型・中型トラックを、古河工場では中型・大型トラックを生産している。三菱ふそうは日本に2カ所の工場を持ち、1カ所ではバスを、川崎工場では小型・中型・大型トラックを生産している。この10年の初めから、両社は国内での生産が低迷している。S&P Global Mobilityは、日野の日本での生産台数が2021年の102,200台から2025年には58,400台に減少する一方、三菱ふそうの生産台数は2022年の61,900台をピークに、2024年の60,900台から2025年には47,300台に減少すると予測している。両社の生産は2028年まで2025年の水準を大きく上回る見込みである。しかしながら、将来的に自動車のエンジニアリングを共有することで、世界中のどこかで生産施設や組み立てパートナーシップを共有する可能性も出てくる。
市場での競争が減退するとの見通しが、特に日本での合意に向けた進展を遅らせる可能性があるかどうかは、まだ分からない。S&P Global Mobilityのデータによると、この提携により、日野と三菱ふそうからなる新持株会社は2024年に日本の中型・大型トラック市場の45.3%を占めることになる。しかしながら、2020年11月に完了したいすゞとUDトラックスの統合 (スウェーデン-日本:2020年11月2日:いすゞとボルボ、戦略的提携で最終合意参照) により、昨年の日本の中・大型トラック市場におけるいすゞとボルボのシェアは53.3%となり、残りは輸入台数の少ないスカニアとボルボのトラックが占めた。現時点で、当社は、2026年から2029年にかけて、日野と三菱ふそうの合併でマーケットシェアは増加するものの、50%未満にとどまると予測している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スズキのスイフト生産中止、中国レアアース規制の影響か-報道
2025年6月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土) -日本
スズキ株式会社|方針・規制、生産
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
ロイターは関係筋2人の話によると、スズキ株式会社が日本の相良車体工場で「スイフト」モデル (「スイフトスポーツ」を除く) の生産を一時停止したのは、中国のレアアース (希土類) 輸出規制が原因の可能性が高く、この問題による影響を受ける日本の自動車メーカーとしては初めてであるという。
重要性: スズキは、部品不足のため相良車体工場でのスイフト (スイフトスポーツを除く) の生産を5月26日から6月6日まで一時停止するが、どの部品が不足しているかは明らかにしていない。中国はレアアースの生産と加工を支配しているため、レアアース磁石の輸出規制強化は部品メーカーから始まり、最終的には自動車メーカーにも長期的な影響を及ぼすと予想されている。さらに、このサプライチェーンの混乱の影響は電気自動車 (EV) にとどまらない;レアアース磁石は、e-アクスル、センサ、ステアリングアッセンブリを含む内燃エンジン (ICE) 車両の様々な部品に不可欠である (米国:2025年6月2日:自動車業界団体がレアアース磁石不足の影響について警告–報道参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、横浜本社売却を検討リストラ資金調達へ-報道
2025年5月26日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
日産自動車株式会社.| 施設・運営
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日産自動車は、緊急のリストラの資金を調達するため、横浜市中心部のグローバル本社を売却することを計画していると報じられている。Automotive Newsによると、同社は2009年、当時のCEOカルロス・ゴーン氏が電気自動車 (EV)「日産リーフ」の発売と同時にこの22階建てのビルを落成させて以来、このビルに入居している。提案されている取引は、日産がオフィスと事業を維持しながら、リースを通じて敷地を使用し続けることができるセール・リースバック契約として構成される。にぎやかな横浜駅や東京湾に面した臨海部からほど近いこのビルは、日経とNHKの報道によると、約1,000億円 (6億7,000万ドル) と評価された。日産の広報担当者は、本社売却の可能性について「日産は業績回復に向けてあらゆる可能性を検討しているが、現時点で具体的な情報はない」と述べた。また、5月24日のテレビ東京の報道によると、日産は東京の北にある栃木工場とテストセンターの縮小または一部売却も検討しているという。
重要性: 本社は、日産の伝統とブランドアイデンティティの象徴であり、同社の歴史と価値観を体現している。日産はコスト削減、事業構造改革、資金繰り改善に注力しているが (日本:2025年5月14日:日産は2024-2025年度に6,709億円の純損失を報告し、Re:Nissanリカバリープランを明らかにしている参照)、本社の売却は従業員の不安を引き起こし、同社の将来の不確実性と格闘しているため、士気の低下につながる可能性が高い。さらに、このような重要な資産を手放すという決定は、一般の人々の認識を変え、ステークホルダー、顧客、投資家が日産の安定性と長期的なビジョンに疑問を抱くようになる可能性がある。日産は、2027~2028年度(FY)までに車両生産工場を17工場から10工場に削減する計画である。同社はまた、パワートレイン設備を最適化し、雇用の再構築、勤務シフトの変更、設備投資の削減を促進する。これには、日本の九州で計画されていたリン酸鉄リチウム (LFP) 電池工場の中止が含まれる。同自動車メーカーは、また、2024~2025年度と2027~2028年度の間に、従来発表していた9,000人の削減を含め、合計2万人の削減を目指す(日本:2025年5月19日:日産自動車、事務系職員の早期退職を7月から実施-報道参照)。最近の報道によると、日産は日本の2つの工場の閉鎖または縮小の可能性を検討している:横浜の南に位置する老朽化した追浜組立工場と、日産の子会社である日産車体が運営する湘南組立工場である。両施設は、横浜のすぐ南、東京に近い神奈川県内の貴重な土地に位置している。また、キャッシュを生み出す取り組みの一環として、日産の横浜エンジン工場の売却が検討されている (日本:メキシコ:2025年5月19日:日産、日本とメキシコの工場閉鎖を検討-報道参照)。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、東京に新本社を建設
2025年5月27日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本トヨタ自動車株式会社|施設・運営
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
トヨタ自動車は、2030年度(FY)の営業開始を目指し、東京都内に新本社ビルの建設に着手した。本社は、日本の主要交通拠点である品川駅の真正面に計画されているビルに置かれる。同自動車メーカーは、新本社がカーボンニュートラルの実現やモビリティの価値向上に向けた取り組みを主導する重要な役割を担うとの考えを示した。トヨタの佐藤恒治社長は、「新東京本社は、トヨタがモビリティカンパニーへと変革していくための重要な拠点となる。当社は、多様な人材が集い、創造性を発揮できる環境を整え、モビリティを通じた豊かな暮らしへの取り組みを加速させる。また、「BEST IN TOWN」を目指し、当社は、地域に根ざした品川駅周辺の更なる発展に貢献していく」と述べた。
重要性: 新本社は、文京区にあるトヨタの現在の本社に代わるものと見られている(日本:2024年3月25日:トヨタ、2030年までに新本社開設へ参照) 。トヨタによると、新本社はエンジニア中心の環境を醸成し、ソフトウェアや人工知能などの先端技術の開発ハブになるという。トヨタ自動車が新しい本社を建設している間に、日産自動車は緊急のリストラ努力の資金を調達するために横浜市中心部のグローバル本社を売却することを計画していると報じられていることは興味深い(日本:2025年5月26日:日産、リストラ計画の資金調達のために横浜の本社を売却することを検討-報道参照)。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
三菱、ルノー・アンペールへの出資計画を撤回-報道
2025年5月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-フランス-日本
ルノーSA、三菱自動車工業株式会社|ライトビークル、電動化
Stephanie Brinley, Associate Director
Automotive News Europeの報道によると、三菱はルノーの電気自動車 (EV) 事業、アンペールへの参画を見送ることを選択したという。報道によると、三菱は「同社は引き続き、ルノーとアンペールからOEM供給を受ける可能性のある車両を含め、継続的なコラボレーションの可能性を模索していく」との声明を発表した。
重要性: 関税コストの上昇や一部市場でのEV普及鈍化への懸念を背景に、今回の動きは全くの驚きではない。三菱がルノーとの関係を継続する例としては、7月1日に予定されているルノー「シンビオズ」をベースにした次期三菱「グランディス」の発売がある。また、三菱が次世代の「ローグ」と「アウトランダー」生産で日産から少し離れるのではないかという憶測もある (米国:2025年3月7日:次世代の三菱「アウトランダー」は日産から離れるかもしれない-報道参照)。三菱は米国でのEV生産拡大も検討している (米国-日本:2025年5月9日:三菱、米国生産を考慮して米国EVを確認参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
テスラ、ドイツの工場拡張計画に固執
2025年5月23日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ
生産、企業、ライトビークル、人員、製品
Tim Urquhart, Principal Analyst
Automotive News Europe(ANE) の報道によると、欧州での販売が減速しているにもかかわらず、テスラはドイツのグリューンハイデ工場の拡張計画を続けている。同社は今年初め、最も売れているの「モデル Y」のライフサイクル中期の更新に向けて設備を一新したため、生産ペースを落としたが、現在は週5,000台の生産に戻っている。テスラのドイツ事業開発責任者を務めるアレクサンダー・リーデラーは、「当社が現在行っているのは、工場でさらに成長できるようにするための準備である」と語った。
重要性: すべてのテスラ工場と同様に、グリューンハイデの経営陣は、ドイツ最大の労働組合IGメタルの最善の努力にもかかわらず、労働組合化に抵抗してきた。この工場では、労働条件や一般的な待遇について不満を述べる労働者の多くの報告に悩まされてきた。フォルクスワーゲン(VW)、ボッシュ、コンチネンタルなどは大幅な人員削減を進めており、早期退職や希望退職の申し出を受けた後も勤務継続を希望する労働者の供給は可能とみられるが、このため、現在進行中の工場拡張計画に向けた社員採用拡大が妨げられる可能性がある。S&P Gloabl Mobilityの最終的な年間生産能力は50万台であるが、2030年には「モデルY」が338,000台、「モデル3」が残りの554,000台を生産し、初めてこの水準に達する見通しである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、サウジアラビアで初の中東工場が着工
2025年5月16日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-サウジアラビア
現代自動車|市場分析、生産、経費、自動車、販売、ライトビークル、製品
Abby Chun Tu, Principal Research Analyst
現代自動車は、中東初の生産拠点であるサウジアラビア生産工場を着工した。同工場は、現代自動車とサウジアラビアの公共投資基金 (PIF) の合弁会社(JV)「ヒュンダイ・モーター・マニュファクチャリング・ミドルイースト(HMMME) 」によって運営される予定である。生産開始は2026年第4四半期を予定しており、生産能力は電気自動車 (EV) と内燃エンジンモデルを合わせて年間5万台である。
重要性: サウジアラビア合弁会社には現代自動車が30%、PIFが70%の株を握っている。買収は2023年10月に発表され、投資総額は5億米ドルを超えた。生産開始時期は当初発表されていた2026年第1四半期から数四半期延期されたようだが、現地生産能力を拡大して中東での影響力を拡大しようとしている現代自動車にとって、今回の起工式は大きな節目となる。S&P Glonal Mobilityは現在、現代自動車が2026年にサウジアラビアでEV「IONIQ 5」の生産を開始すると予想している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
一連のマイナーチェンジはMY2026にトヨタ「カムリ」、「カローラクロス」、「カローラハッチバック」を一新
2025年5月15日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国トヨタ自動車株式会社|販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン(ICE)、電動化
Stephanie Brinley, Associate Director
トヨタの3つの主要モデルは、2026モデルイヤー(MY)にマイナーチェンジと特別なトリムエディションを受けた。「カムリ」は、新しい「Nightshade Edition」にミッドナイトブラックを基調とした外観に加え、一部のトリムレベルに新色を採用した。「Nightshade Edition」には、専用のダークカラーの19インチホイールと、光沢のあるブラックのバッジが付いている。Nightshadeは「カムリ」のトリムレベルを5段階に増やし、すべて前輪駆動または全輪駆動構成で提供する。Nightshadeは現行のハイブリッドパワートレインオプションを踏襲しており、全輪駆動モデルの方がよりパワーがある。新型「カムリ」は2025年半ばに発売される。「カローラクロス」では、内燃エンジン (ICE) モデルとハイブリッドモデルの両方で、フロントの飾りが新しくなった。ハイブリッド車はフロントグリルとバンパーの組み合わせが新しくなり、ガソリン車はバンパーは同じであるが、グリルが新しくなった。その結果、ガソリンモデルはより頑丈に、ハイブリッドモデルはより洗練された外観になった。変更はわずかであるが、モデル間のコントラストを高めるために、基本的なグリルテクスチャの変更よりも多くの変更が加えられている。新しいフロントルックに加えて、新しいホイールデザインと新しいカラーがある;トヨタは「カローラクロス」の発売から5年ごとに新色を追加してきた。インテリアでは、フロントコンソールが再設計されてスペースが広くなり、「カローラクロス」では10.5インチのトヨタマルチメディアスクリーンがオプションで選択できるようになった;トリムに応じて、購入者は7インチのマルチインフォメーションディスプレイまたは12.3インチのデジタルゲージクラスターを手に入れることができる。暖房シート付きの寒冷地用パッケージはすでに発売されており、XLE AWDおよびハイブリッドXSEトリムレベルでは標準となっている。「カローラハッチバック」はMY 2026にも注目されており、車の価格が上昇する中でタイミングの良いものになるかもしれない。トヨタはカローラFXトリムレベルを追加し、過去のカローラFX16バージョンへのオマージュを意味している。「FX16」は以前のカローラをスポーティにしたもので、2026年の「カローラFXハッチバック」も同様のフォーミュラを踏襲している。2026年型「カローラFX」は、SEトリムレベルをベースに、ブラックのベント付きスポーツウィング、ブラックのラグナット付き18インチグロスホワイト仕上げアロイホイール、ヘリテージ風のリアバッジを追加している。内側には、スエードのインサートとオレンジのステッチがドアパネル、ステアリングホイール、シフターブーツに流れる新しいブラックのスポーツツーリングシートがある。FXエディションは三色で、限定1,600台である。
重要性: トヨタは通常、パワートレインや全体的な機能パッケージにほとんど変更がない場合でも、マイナーモデルチェンジによってモデルラインアップを押し上げたり、差別化を図ったりするのが得意である。このようなモデルチェンジは、購入者に今までとは違った楽しみを与え続け、数年前に発売された車がまだ新鮮であるように感じさせ、最も実用的な選択であっても、より多くの自己表現を好む購入者に提供し続けている。米国市場が2025年と2026年の下半期に入ると、米国の関税環境の影響により、市場全体の販売が困難になると予想される。これら3車種はすべて米国内で生産され、米国の購入者に提供されるが、部品は他の市場から調達されるため、トヨタのコストは影響を受ける。2025年4月のS&P Global Mobilityの米国ライトビークル販売予測では、トヨタの米国全体の販売台数は2024年と比較して比較的小幅な減少となる。トヨタの米国での販売台数は、2024年の199万台から2025年には198万台に達すると予測されている。

2026トヨタ・カムリ・ナイトシェード トヨタ

2026トヨタ・カローラクロス、カローラクロスハイブリッド トヨタ
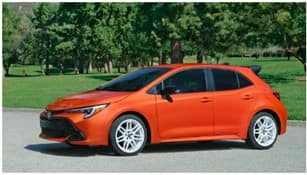
2026トヨタ・カローラFX トヨタ
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、フィリピンで長期レンタカーサービス向けにJoyRideと提携
5月8日2025-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-フィリピントヨタ自動車株式会社|企業、JV/提携、ライトビークル、コーポレート、ライドヘイリング/ライドシェアリング
Jamal Amir, Principal Research Analyst
トヨタ・モーター・フィリピン(TMP)は、進化する旅行者のニーズに応える戦略的な取り組みとして、 ライドヘイリング・サービスのJoyRideと提携し、長期レンタカーのソリューションを提供すると発表したとthe Philippine Starが報じている。トヨタ・モビリティ・ソリューションズ・フィリピンが運営するこの提携は、特にサービスが最初に開始されるマニラ首都圏において、顧客の交通手段の利便性を向上させることを目的としている。トヨタレンタカーは、セダンからスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)、バンまで幅広い車種を取り揃えており-10時間の短期レンタルから3年間の長期レンタルまで-顧客の旅行プランに合わせてレンタル時期を選択できる。レンタル期間の柔軟性は、ビジネスでもレジャーでも、さまざまな旅行のニーズに対応できるように設計されている。この提携は、レンタカーサービスをJoyRide Superappに直接統合することで、顧客体験の向上を目指すものである。この革新的なアプローチにより、ユーザーはアプリを通じて簡単に希望の車を予約することができ、プロセスを合理化し、従来のレンタカーサービスにしばしば伴う煩わしさを軽減することができる。初回利用者はトヨタレンタカーのウェブサイトで登録する必要があるが、2回目以降はアプリから予約できる。支払いは、電子財布、JoyRideプラットフォームを介したクレジットカードまたはデビットカード、およびトヨタレンタカーの店舗で直接現金またはカードでの支払いを選択できるので便利である。この多様性は、顧客が好みの支払い方法を選択できることを保証し、全体的なユーザーエクスペリエンスをさらに向上させる。
重要性: TMPは、この取り組みが単に車両を提供するだけでなく、より接続され、通勤しやすいフィリピンに貢献するものであることを強調している。マニラ首都圏の住民と複数の目的地を探索しようと計画している観光客の両方のニーズに応えることにより、トヨタレンタカーとJoyRideの提携は、同国のモビリティサービスの改善に向けた重要な一歩となる。パーソナライズされた柔軟な旅行体験への需要が高まる中、両社はこの提携がレンタカー業界に新たな基準を設定し、顧客が旅を快適に進めるために必要なツールを確実に提供することを期待している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
アウディ、F1パワートレインプログラムの責任者が相互合意のもとに辞任
2025年5月6日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ
フォルクスワーゲンAG|施設・運営、研究開発、ライトビークル、人事
Tim Urquhart, Principal Analyst
アウディはFormula1(F1)プログラムの経営構造を大幅に変更した;企業の声明によると、プロジェクトの統括責任者を務めるマッティア・ビノット氏がシャシーやエンジン設計を含む開発全般を統括する。ビノット氏の下での大きな変更点は、Audi Formula Racing GmbH (AFR) のCEOを務めていたアダム・ベイカー氏が退任することである。2026年の正式参戦に向け、アウディ初のF1パワートレインの設計、開発、製造を担当している。ベイカー氏はクリスチャン・フォイヤーに置き換えられ、Audi Formula Racing GmbH (AFR) の取締役会に新たに創設された役割の最高執行責任者 (COO) に加わった。同氏は、アウディF1プロジェクトの責任者という新しい肩書きを持つビノットの直属となる。同氏は以前、アウディがF1エントリーのシャシー要素を構築するために買収した老舗F1チーム、ザウバー・モータースポーツの最高執行責任者兼技術責任者を務めていた。アウディは声明の中で、「アウディはFormula1プロジェクトをファクトリーチームのシナジーと作業方法によりさらに一貫性を持たせている。マッティア・ビノット氏はアウディF1プロジェクトの責任者として、ヒンウィルとノイブルク・アン・デア・ドナウの施設、そして将来のイギリスのテクニカルセンターでの開発活動を担当する」と述べた。
重要性: アウディは少なくとも、以前は複雑でトップ中心の経営体制だった同プロジェクトの指揮系統を明確にする動きを見せた。この1年弱で2度目の大規模な経営陣の交代となる。しかしながら、エンジンプログラムには以前からある程度の管理の自主性があったようで、ビノット氏はシャシーとエンジンの両方についてプロジェクト全体の完全なコントロールを要求するために取締役会に行った可能性が高い。これはアウディのF1エンジンプログラムにとってあまり良い前兆とは言えない。元フェラーリのチームプリンシパルとして、ビノット氏は非常にペースの速い熾烈なF1の世界に慣れており、F1パワートレインの開発に関して見聞きしたことに満足していないようである。2026年に施行された新しいF1エンジンレギュレーションでは、パワートレイン全体のパフォーマンスに占める内燃エンジンとハイブリッドの割合が15%から50%に引き上げられ、F1パワートレインの設計と開発に携わるエンジニアにとって、非常に厳しい課題となっている。アウディは、フェラーリ、メルセデス・ベンツ、ホンダおよびフォード(レッドブルlパワートレインを装備) と同様に、2026年シーズンの新しいレギュレーションに対応するパワートレインを開発しているが、エンジン技術における大きなステップチェンジは、来年のチャンピオンシップの第1ラウンドにおいて、非常に公開されている技術とエンジニアリングの失敗をもたらす可能性がある。アウディがこのような経営構造の変更を行ったという事実は、新しいF1パワートレインの開発という点で、現時点でアウディが望んでいる状況ではないことを示唆している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
マルチ・スズキ、2024/2025年度は増益、戦略投資と新たな取り組みを発表
2025年4月28日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
スズキ株式会社|経費、施設・運営、貿易 (輸出入)、生産、企業、販売、ライトビークル、製品、コーポレート、内燃機関 (ICE)、電動化
Jamal Amir, Principal Research Analyst

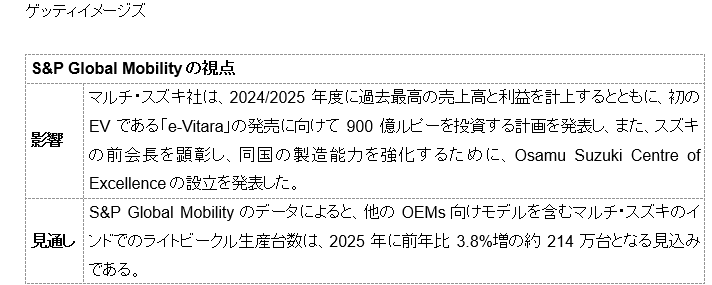
2024/2025年度第4四半期
ボンベイ証券取引所 (BSE) に提出された書類によると、マルチ・スズキ・インディア (MSIL) は、2024/2025年度第4四半期 (1月~3月) の純利益が371億1,100万ルピー (434,603,000米ドル) と、前年度同四半期の387億7,800万ルピーに比べて4.3%減少した。営業外収益は増加したものの、新工場関連費用や販売促進・広告宣伝費の増加、製造諸経費・管理費の増加などにより減益となった。今年2月には同自動車メーカーは、インドのハリヤナ州カルコダの新工場で商業生産を開始した(インド:2025年2月26日:マルチ・スズキ、カルコダ新工場で生産開始参照) 。3ヶ月間、同自動車メーカーの純売上は前年比5.9%増の3,884億8,800万ルピーで、2023/2024年度第4四半期の3,669億7,500万ルピーから増加した。営業EBITは前年比14.2%減の339億2,300万ルピーであった。
2024/2025年度第4四半期の販売台数は、(どの四半期より過去最高である)前年比3.5%増の604,635台であり、内訳は、国内販売が519,546台 (前年比2.8%増)、輸出が85,089台 (前年比8.1%増) であった。国内市場では、「アルト」や「Sプレッソ」などの軽乗用車セグメントにおける同自動車メーカーの販売台数が前年比14.9%減の36,128台であった。「バレーノ」、「セレリオ」、「ディザイア」、「イグニス」、「スイフト」、「ワゴンR」などの小型乗用車セグメントの販売台数は前年比1.9%増の222,089台である一方、第4四半期の「シアス」セダンなどの中型乗用車セグメントの販売台数は前年比77.2%増の2,541台であった。「ブレッツァ」、「エルティガ」、「フロンクス」、「グランビターラ」、「インビクト」、「ジムニー」、「XL6」などのユーティリティ・ビークルの販売台数 (UV:SUVおよびMPV)は、前年比5.2%増の191,223台、「イーコ」バンは前年比8.4%減の33,152台であった。小型商用車「スーパーキャリー」(LCV) の販売台数は前年比9.5%減の9,190台であった。2024/2025年度第4四半期の他OEMs向けに製造された車両の販売台数は、前年比64.3%増の25,223台であった。
2024/2025年度通期
MSILは、2024/2025年度の国内販売台数、輸出、売上高、純利益ともに過去最高を記録した。同自動車メーカーの2024/2025年度 (4月~3月) 通期の純利益は、2023/2024年度の1,320億9,400万ルピーと比較して前年比5..6%増の1,395億5,200万ルピーを記録した。2024/2025年度通期の売上高は前年比7.5%増の約1兆4,510億ルピーで、2023/2024年度の約1兆3,490億ルピーから増加を記録した。営業EBITは前年比9.3%増の1,462億5,900万ルピーであった。
2024/2025年度通期の販売台数は前年比4.6%増の約223万台で、国内販売が約190万台 (前年比2.7%増)、輸出が332,585台 (前年比17.5%増) であった。同自動車メーカーは、インドの乗用車輸出全体の43%近くを占め、4年連続で最大の輸出国となった。国内市場では、同年度の軽乗用車セグメントの同自動車メーカーの販売台数は前年比11.5%減の125,770台、小型乗用車セグメントの販売台数は前年比6.9%減の770,737台、中型乗用車セグメントの販売台数は前年比18.7%減の8,402台であった。UVの販売台数は、前年比12.1%増の720,186台、「イーコ」バンの販売台数は、前年比1.1%減の135,672台であった。LCV「スーパーキャリー」の販売台数は、前年比2.2%増の34,492台であった。2024/2025年度通期の他OEMs向けに製造された車両の販売台数は、前年比81.6%増の106,422台であった。
マルチ・スズキの取締役会は、2023/2024年度の一株当たり125ルピーに対し、過去最高の一株当たり135ルピー (一株あたり5ルピーの額面) の配当を推奨した。
マルチ・スズキ、900億ルピー投資で「e-Vitara」発売と事業拡大へ
マルチ・スズキは、今年度最大900億ルピーの投資計画を発表しており、事業拡大とEV市場への参入に向けた積極的なコミットメントを示している。MSIL会長R.C.バルガバ氏は、同自動車メーカー初のEV「e-Vitara」の生産を9月末前に開始する予定であることを明らかにした。年間約7万台を生産し、その大部分を日本や欧州などの海外市場に輸出するという野心的な目標を掲げている。
マルチ・スズキは、インド最大の自動車輸出国である同社にとって、「e-Vitara」を軸に、今年度20%増を目指す海外出荷台数の拡大を目指す。特に国内販売が停滞の兆しを見せる中、同社にとって輸出の重要性は高まっている。また、同自動車メーカーは、生産目標を達成するため、インド北部の製造施設の拡張計画も進めている。
「e-Vitara」に加えて、マルチ・スズキは今年後半に新しい燃焼エンジンSUVを発売する準備をしている。この動きは、消費者のSUV志向の高まりにいち早く対応した中小企業に奪われたマーケットシェアを取り戻す狙いがある。また、マルチ・スズキは、より安全なクルマを求める消費者の需要に応えるため、全車種に6つのエアバッグを搭載し、車両の安全性の向上に努めている。
バルガバ氏はまた、マルチ・スズキは現在米国に自動車を輸出しておらず、米政府による関税の影響を受けないと指摘した。この戦略的投資とEVへの多角化、安全性強化は、消費者の嗜好や規制環境が変化する中で、インドの自動車市場におけるリーダーの地位を維持するためのマルチ・スズキの積極的なアプローチを反映している。
レガシーの尊重:インドにおけるOsamu Suzuki Centre of Excellence」の設立
スズキ株式会社の前会長、故鈴木修氏への心からの追悼として、スズキ株式会社とMSILは重要な取り組みを発表した。ニューデリーのヤショブミで開催された追悼イベントで、両社は、「Osamu Suzuki Centre of Excellence」(OSCOE) をインドに設立するという両社の提案を明らかにした。この取り組みは、インドの自動車産業および製造部門にとって重要な節目となった2024年12月25日の鈴木氏の逝去を受けたものである。
提案されたOSCOEは、国の経済目標に沿ったいくつかの重要な目標を達成することを目的として、グジャラート州とハリヤナ州に設置される予定である。主な目的の一つは、世界競争力の文脈においてますます重要になっている製造業の高度成長に対するインドの野心を支援することである。OSCOEは、Tier 1、Tier 2、Tier 3サプライヤーを含む部品メーカーの水準を高めることで、インドのサプライチェーンの国際競争力を強化することを目指している。
さらに、OSCOEは、学術機関や産業界の利害関係者と協力して、インフラを構築し、プログラムを開発する上で重要な役割を果たす。このセンターは、日本のものづくりの哲学を、正式な授業、講義、討論、セミナーなどのさまざまな教育活動を通じて広めていく。重要なことは、OSCOEの取り組みは自動車分野に限定されないことである。同センターは、その影響力と取り組みを他の製造業分野に拡大し、より広範な経済効果を促進することを目指している。この包括的なアプローチは、鈴木氏のレガシーを尊重するだけでなく、世界の舞台でのインドの製造能力に大きく貢献するというコミットメントを強調している。
見通しと影響
2024/2025年度通期のMSIL財務業績が好調であったのは、販売台数の増加、その他営業利益の増加、営業外費用の増加、コスト削減努力によるものである。また、全体的なインフレや規制の影響をある程度相殺するために、同自動車メーカーは、また、昨年度に車両価格を引き上げた。しかしながら、当期中に販売促進費の増加や商品の価格の下落がマイナス要因となる可能性がある。2024/2025年度通期の同自動車メーカーの税引き前利益は前年比12.6%増の1,918億3,200万ルピーであった。 同自動車メーカーにより発表されたデータによると、2024/2025年度通期の材料費 (対売上高比率) は74.5% (10ベーシス・ポイント[bps]上昇)、人件費 (対売上高比率) は4.2% (10bps上昇)、その他費用 (対売上高比率) は13.7% (10 bps減少)、減価償却費 (対売上高比率) は横ばいの2.2%であった。2024/2025年度のその他の営業利益 (対売上高比率) は30 bps増加して4.7%であった。同自動車メーカーは、営業EBIT (対売上高比率) は10.1%で、2023/2024年度の9.9%から上昇した。支払利息 (対売上高比率) は横ばいの0.1%、営業外利益 (対売上高比率) は40 bps増の3.3%、税引前利益 (対売上高比率) は60 bps増の13.2%、税引後利益 (対売上高比率) は20bps減の9.6%であった。
MSILは機会と課題の両方に直面している。同自動車メーカーの効果的な輸出戦略が国内市場の低迷を緩和した;しかしながら、材料費の高騰や競争の激化が懸念されている。また、1月にはスズキグジャラートプライベートリミテッドとの合併が同自動車メーカーの取締役会で承認され、事業の合理化と効率化が期待されている。MSILはまた、ハリヤナとグジャラートにある製造工場を戦略的ビジネスユニット (SBU) に分散化し、業務の効率性を高め、競争力を強化するために努力している (インド:2025年4月9日:マルチ・スズキ、3月の生産台数は前年比17%増、工場の分散化による効率化を計画参照) 。
重要なのは、スズキ株式会社が最重要市場であるインドの販売目標の下方修正を発表したことである。2031年3月までのインドでの販売目標は、2023年10月時点の300万台から約250万台に下方修正した。スズキもインドでのEV発売計画を縮小し、当初予定していた6車種から4車種に絞る。スズキは、2031年3月までにインドでの総販売台数に占めるEVの割合を15%、そのうちハイブリッド自動車 (HEV) が25%、圧縮天然ガス (CNG) 車が35%、エタノール混合燃料対応車が25%とする目標を掲げている。
今回の下方修正は、インドの自動車業界における競争激化を反映したもので、特にSUVセグメントを中心に機能豊富な製品で勢いを増しているタタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラ (M&M)、現代自動車などとの競争が激化している。今年初めに述べたように、スズキの現地法人マルチ・スズキのインド乗用車セグメントにおけるマーケットシェアは、ピークであった2020年3月の約51%から41%に低下した。2026年3月までに50%のマーケットシェアを回復するという野心的な目標は、2031年3月に延期された。このリキャリブレーションはこれまでスズキが得意としてきた小型車から-スズキが対応が遅いとされるマーケットセグメント中型SUVへと、消費者の嗜好がシフトしていることが背景にある。 こうした課題を抱えながらも、スズキはインドへの注力を継続し、SUVラインアップを強化し、2030年度までに計画している投資額2兆円の60%をインド市場に振り向ける計画である。同自動車メーカーは、年間約200万台の生産能力を適切な時期に400万台に増強し、インドを世界輸出向けの重要な生産拠点とすることを目指している。スズキは当初、2031年3月までに生産台数を400万台に拡大する計画であった。
その目的に沿って、MSILは最近、カルコダの新施設で商業生産を開始した。同工場の年間生産能力は25万台で、現在はコンパクトSUV「ブレッツァ」を中心に生産している。同自動車は、同地区に第二工場を建設中で、年間生産台数を25万台増やす計画である。また、カルコダに第3の車両製造工場を建設することも発表し、これにより、年間25万台の生産能力が追加される。マルチ・スズキはまた、3,820億ルピーを投じてグジャラート州に新工場を建設し、同州の既存施設に新たな生産ラインを追加する計画である。
S&P Global Mobilityのデータによると、他のOEMs向けモデルを含むマルチ・スズキのインドでのライトビークル生産台数は、2025年に前年比3.8%増の約214万台となる見込みである。これは今後さらに増加し、2030年には約260万台に達すると予想されている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日野と三菱ふそう、合併合意へ-報道
2025年4月22日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
ダイムラー・トラック、日野自動車|合併・買収 (M&A)
シニアアナリスト、ニティン・ブディラジャ-自動車
日野自動車と、ダイムラー・トラックのドイツ子会社である三菱ふそうトラック・バス (MFTBC) が、合併契約の最終合意に向けて詰めていると、Nikkei Asiaの記事を引用してロイターが報じた。情報源を明らかにしなかった報道によると、両自動車会社はトラック部門の持株会社を設立し、2026年4月までに東京証券取引所プライム市場に上場する計画であるという。日本経済新聞社によると、公正取引委員会による独占禁止法違反の審査がほぼ終了し、5月にも合併契約が締結される可能性がある。取引後、新しく作られた同持株会社が日野自動車と三菱ふそう両社の完全子会社となる。トヨタ自動車とダイムラー・トラックにロイターはコメントを求めたが、営業時間外でまだ回答は得られていない。
重要性: この報道は、両社が以前に発表した内容と一致している。2024年2月、MFTBCは、日野とダイムラー・トラックが対等合併し、商用車 (CV) など分野においての開発・調達・生産などで協業する方針を発表した。MFTBCと日野が合併して誕生した上場持株会社に、ダイムラー・トラックとトヨタの両社が対等に出資し、世界に通用する日本のCVメーカーを目指すことが目標である。当初、2024年3月末までに合併の正式な契約を締結し、同年末までに統合を完了する予定であったが、競争法上の許認可や、日野のエンジン認証問題に関する調査などがあり、合併に向けたプロセスが遅れていた。両社の合併は、グローバルCV市場でより効果的に競争できる強力な企業を創出するための相乗効果をもたらす可能性が高い。この合併は、生産、調達、運営における規模の経済につながり、最終的にはコストを削減し、収益性を向上させることができる。さらに、研究開発の取り組みで協力することで、電気自動車や自動運転車の進歩を含むCV技術のイノベーションを加速することができる。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
3月のトヨタグループグローバル生産台数は前年比10.3%増
2025年4月24日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|生産、販売
シニアアナリスト、ニティン・ブディラジャ-自動車

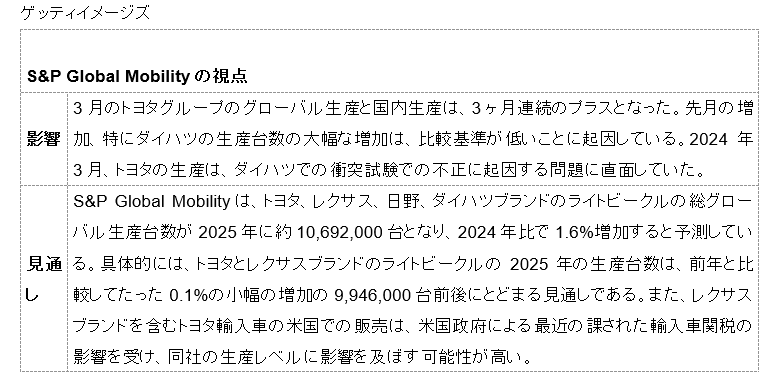
子会社のダイハツと日野を含むトヨタグループは、3月のグローバル生産台数が前年比10.3%増の977,241台になったと発表した。これは、年初来の累計値 (YTD)におけるグローバル生産台数 が275万台となり、2024年同期に比べて11.7%増加したことを意味する。3月の数値の内訳は、トヨタブランド (レクサスを含む) が前年比9.1%増の880,476台、ダイハツが前年比32.6%増の86,143台を記録した。一方、日野の生産台数は前年比24.8%減の10,622台となった。3月のグループ全体の国内生産は、前年比12.2%増の365,894台であり、 YTD国内生産は前年比29.9%増の1,055,000台であった。3月の国内生産台数は、トヨタブランド (レクサスを含む) が前年比6.9%増の303,301台であった。ダイハツの国内生産台数は78.0%増の54,202台、日野の国内生産台数は前年比29.1%減の8,391台であった。また、3月の海外生産は、前年比9.1%増の611,347台となり、内訳は、トヨタ車およびレクサス車が577,175台 (前年比10.3%増)、ダイハツ車が31,941台 (前年比7.5%減) であった。先月の日野の海外生産台数は、前年比2.7%減の2,231台であった。YTDのトヨタグループの海外生産は、2.7%増の1,694,000台であった。
3月のトヨタグループのグローバル販売台数は前年比10.9%増の1,043,000台であった。YTD販売台数は前年比7.5%増の2,715,000台に達した。3月の販売台数にはトヨタとレクサス車が含まれ、前年比7.9%増の968,442台であった;ダイハツ車が前年比96.9%増の63,533台;および日野車が前年比2.2%減の11,448台であった。同月のトヨタグループの国内販売台数は、前年比35.8%増の208,956台、YTD国内生産台数は37.3%増の557,353台であった。3月の海外販売台数は前年比6.0%増の834,467台であり、YTD海外販売台数は前年比1.8%増の2,158,000台であった。
見通しと影響
3月のトヨタグループのグローバル生産と国内生産は、3ヶ月連続のプラスとなった。先月の増加、特にダイハツの生産台数の大幅な増加は、比較基準が低いことに起因している。2024年3月、トヨタの生産は、ダイハツでの衝突試験での不正に起因する問題に直面していた(日本:2023年12月20日: ダイハツ、衝突試験で新たに不正が判明したため、全車両の出荷を停止参照) 。
2025年3月、トヨタのグローバル生産・販売は力強い回復を見せた。レクサスを含むトヨタブランドの北米-カナダ、メキシコおよび米国-生産は、トヨタブランド車の強い需要に加え、1月の降雪の影響からの回復もあり、前年比12.4%増の199,577台であった。欧州では、同社の生産はフランスの環境税改正による市場低迷もあり、前年比4.9%減の68,256台であった。英国ではゼロエミッション車 (ZEV) 義務化に伴い、生産台数は前年比5.1%減の7,708台となりました。トルコでの生産は前年比8.1%増の17,079台、一方、フランスでは前年比6.3%減の24,764台であった。アジアにおける3月のトヨタ生産は、タイで48,445台 (前年比13.8%増)、インドネシアで21,423台 (前年比16.3%増) であり、前年比12.4%増の268,128台であった。インドネシアでは「アバンザ」、タイでは「ハイラックス」が好調に推移した。しかしながら、景気減速や自動車ローン規制の厳格化で一部相殺された。一方、中国では、現地ブランドとの競争が激化する中、政府の自動車購入補助金政策に沿った販売促進戦略により、同グループの中国における生産は回復の兆しを見せた。中国での生産台数は前年比18.7%増の136,651台であった。
S&P Global Mobilityは、トヨタ、レクサス、日野、ダイハツブランドのライトビークルの総グローバル生産台数が2025年に約10,692,000台となり、2024年比で1.6%増加すると予測している。具体的には、トヨタとレクサスブランドのライトビークルの2025年の生産台数は、前年と比較してたった0.1%の小幅の増加の9,946,000台前後にとどまる見通しである。また、レクサスブランドを含むトヨタ輸入車の米国での販売は、米国政府による最近の課された輸入車関税の影響を受け、同社の生産レベルに影響を及ぼす可能性が高い。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、新型「リーフ」を栃木工場で生産へ
2025年4月14日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本日産自動車株式会社|施設・運営、生産、製品
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日産自動車は、新型電気自動車(EV)「リーフ」を栃木工場で生産し、今年度(FY)中に発売すると発表した。日刊自動車新聞によると、これまで神奈川県の追浜工場で生産していた現行モデルの生産を中止した。国内EV生産を栃木工場に集約することで、同社は、生産効率の向上を目指す。リーフの生産移管後、追浜工場は「ノート」とノートの派生モデル「ノートオーラ」の2モデルに注力する。しかしながら、日産は将来的には海外生産車を導入する方針を示している。新型「リーフ」は、栃木工場で生産しているEV「アリヤ」と同じ「CMF-EV」プラットフォームを採用する。
重要性: 日産は、日本の栃木工場の生産ラインを、ニッサンインテリジェントファクトリーの先進技術で更新した;次世代自動車の製造やゼロエミッション化生産システムの実現に活用している。栃木工場は国内EVの主要生産拠点として効率的な生産体制を確立する(日本:2021年10月11日:日産、栃木工場の生産ラインを更新、生産におけるカーボンニュートラルに向けたロードマップを発表参照) 。S&P Global Mobilityのライトビークル生産台数予測によると、栃木工場は6月からCMF-EVプラットフォームをベースにした次世代「リーフ」の生産を開始し、2025年に約32,600台、2026年に約59,000台を生産するという
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
タタ・モーターズが2024~25年度に記録的な特許・意匠出願を達成
2025年4月18日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
タタ・モーターズ|企業、研究・開発、コンポーネント、ライトビークル、中型&大型商用車、テクノロジー、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
企業のプレスリリースによると、タタ・モーターズは2024~2025年度に250件の特許と148件の意匠出願を行い、単年度の最高記録を達成した。この成果は単なる統計ではない;これは、コネクティビティ、電動化、持続可能性、安全性 (CESS) などの主要な自動車メガトレンドとのタタ・モーターズの戦略的提携を反映しており、水素ベースの自動車や燃料電池などの新興技術にも注力している。これらの申請は、バッテリー技術、パワートレインの革新、ボディとトリムの設計、サスペンションシステム、ブレーキ、HVAC、エミッションコントロール技術など、重要な車両システムを網羅している。この包括的なアプローチは、今日の急速に進化する自動車業界において最も重要な、車両性能と安全性の向上に対するタタ・モーターズのコミットメントを示している。さらに、タタ・モーターズは知的財産権の分野でも躍進を遂げ、81件の著作権出願を行い、68件の特許を取得し、これにより、タタ・モーターズが取得した特許の総数は918件に達した。
重要性: タタ・モーターズの社長兼最高技術責任者であるラジェンドラ・ペトカー氏は、業界の変化に対応しながら、顧客に持続的な価値を提供することを目的とした同自動車メーカーのイノベーション戦略を強調した。このマイルストーンは、タタ・モーターズの卓越性の絶え間ない追求と、より環境に優しく、より安全で、より効率的な車を生産するという長期的なビジョンを反映していると同氏は述べた。2024年度~2025年度にかけて国内外で5つの栄誉ある賞を受賞したタタ・モーターズの知的財産権の優秀性が認められ、自動車イノベーションにおけるグローバルリーダーとしての地位がさらに強固なものとなった。タタ・モーターズは、モビリティの未来を開拓し続けており、その取り組みは、顧客とコミュニティの進化する願望に応えることにしっかりと根ざしている。タタ・モーターズは、革新的な技術のポートフォリオを拡大し、自動車産業を形成するだけでなく、持続可能なソリューションと最先端のイノベーションへのコミットメントを通じて国づくりに貢献している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、2026年に次世代インテリアを発表、物理ボタンは維持
2025年4月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国
現代自動車|企業、コンポーネント、ライトビークル、製品、コーポレート
Jamal Amir, Principal Research Analyst
現代自動車は「2025ソウルモーターショー」でサイモン・ロースビー副社長 (デザイン担当) が発表したように、2026年に発売予定の次世代デザインの導入で自動車のインテリアに革命を起こそうとしている、とAutocarは報じている。この新しい設計哲学の重要な側面は、物理的なボタンを保持することに重点を置いており、これは、安全性を向上させ、ドライバーの注意散漫を減らすことを目的とした決定である。インフォテインメントシステムがますます複雑になっている時代に、現代自動車のアプローチは際立っている。ロースビー氏は、インフォテインメントディスプレイの小型化とタッチスクリーンインターフェースの簡素化の可能性を強調した。
重要性: この戦略的な動きは、より広範な業界トレンドに沿ったものであり、特にフォルクスワーゲン (VW) などの他の主要メーカーも同様の傾向を示しており、VWもまた、車両により多くのアナログ制御を再導入することにコミットしている。これらのメーカーに共通する目標は、ドライバーが運転に集中できるようにすることで、大型の中央画面に関連する注意散漫を最小限に抑えることである。現代自動車のデザイン責任者であるリュック・ドンカーヴォルケ氏は、この取り組みをさらに詳しく説明し、複雑なメニューでドライバーが圧倒されて運転に集中できなくなるのを防ぐために、最適な画面サイズを見つけることの重要性を強調した。頻繁に使用する機能のための物理的なコントロールと、追加機能のためのデジタルディスプレイのバランスは、テクノロジーとユーザー体験の思慮深い統合を表している。現代自動車は、物理的なボタンの保持を優先することで、ドライバーがハンドルに手を置いて道路を見続けることができるようにし、安全性を高めることを目指している。この取り組みは、消費者の嗜好に応えるだけでなく、自動車業界がユーザー中心の設計哲学に大きくシフトしていることを反映している。メーカー各社が現代技術を統合しながら運転体験を向上させようと努力している中、現代自動車は伝統的な制御と先進的なシステムを融合させることへのコミットメントを強調している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
アウディの「Q5」ベストセラーモデル、米国で52.5%の関税に直面-報道
2025年4月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-メキシコ-米国
フォルクスワーゲンAG|経費、政策・規制、貿易 (輸入/輸出)、企業、市場、ライトビークル、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
アウディの北米事業に近い情報筋の話としてAutomotive Newsが伝えたところによると、アウディの米国でのベストセラーモデルは米国市場で52.5%の関税の対象になるという。現在、「Q5」は米国市場での競争力のある最低価格は45,400米ドルであり、これを維持することは不可能である。「Q5」は、メキシコのプエブラで製造されているため、25%の自動車輸入関税が適用される。また、メキシコの国境管理の欠如を理由に米国政府が課した、メキシコからの輸入品に特に課される25%の追加関税もある。ドナルド・トランプ大統領も1期目に、NAFTA自由貿易協定を順守していないとして2.5%の追加関税を交渉した。
重要性: OEMsは正確な関税に関する詳細なガイダンスを待っているが、アウディの経営陣は、メキシコ製「Q5」には少なくとも52.5%の関税がかかると想定している。トランプ氏は4月9日に「相互」関税の大半を90日間停止したが、自動車業界を対象とした一律10%の基本関税は維持した。報道によると、アウディは正確な関税が決まるまで、他のモデルを通関手続きを経て正式に輸入する前に米国の港で留め置いているという。名目上の52.5%の関税にもかかわらず、アウディの経営陣はメキシコ製「Q5」を米国市場に投入し、顧客にとって魅力的なものにすることにコミットしていると言われている。しかしながら、52.5%の関税引き上げによるコストを吸収するには膨大な量であり、かなりの量を最終的には顧客に転嫁する必要があることは間違いない。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、SUV「ローグ」生産シェアの一部を米国に移管へ-報道
2025年4月7日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本-米国
日産自動車株式会社|施設・運営、生産
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日経新聞の報道を引用してロイターが報じたところによると、日産自動車は、ドナルド・トランプ米大統領が各国に課した関税の引き上げを受けて、米国向け自動車の国内生産の一部を米国内に移す可能性を検討している。同紙によると、情報源は明らかにされていないが、日産は関税の影響を緩和するため、今夏から西日本にある福岡工場の生産を縮小し、スポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)「ローグ」の一部生産を米国に移管する意向だという。米国市場の主力モデルである「ローグ」は、現在福岡と米国で生産されている。同自動車メーカーは、テネシー州スマーナ工場で「ローグ」の生産シフトを2シフト継続する計画を発表しているが、1月には、2シフトのうち1シフトを今月中に終了すると発表していた。
重要性: 米国によるすべての自動車輸入に対する25%の関税の発表 (米国:2025年3月27日:米国大統領、自動車と自動車部品に25%の関税をかけると発表参照) は、米国外に工場を持つ米国メーカーを含む世界の自動車業界に衝撃を与えた。自動車分野は日本経済の重要な構成要素であり、自動車は米国向け輸出のかなりの部分を占めている。S&P Global Mobilityのデータによると、昨年米国で924,000台を販売したインフィニティブランドの日産の輸入シェアは45.2%で、日本からの輸入シェアは14.1%を占めているに過ぎない。当社のデータによると、米国で販売されたSUV「ローグ」の31.0%は日本から輸入され、残りはスマーナ工場で製造されている。日産は米国市場での販売が伸び悩む中、2024年後半から米国での生産をほぼ縮小している (米国:2024年9月12日:日産、米国で「ローグ」と「フロンティア」の生産を削減-報道および米国-日本:2025年2月18日:日産、米国での生産を減らし、次世代「ローグ」の輸入を増やすことを検討-報道参照)。このモデルの日本での同モデルの生産の一部を米国に移管するという報道が正しければ、日産は生産が削減されていたのでスマーナ工場の従業員に生産削減に伴うバイアウトを提案した後、スマーナ工場の従業員を再雇用する必要があるかもしれない (米国:2025年4月4日:自動車輸入に対する米国の25%関税に対する初期の対応には、生産停止、拡大が含まれる-報道参照)。
ホンダ、ステップワゴンの新型2車種を発表
2025年4月3日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
本田技研工業株式会社|製品
Nitin Budhiraja. Sr. Analyst – Automotive
ホンダは、5月にステップワゴンラインアップに2つ新型グレードを発売する予定である:ステップワゴン「AIR EX」とステップワゴン「SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION」。現在、全国のホンダカーズで予約を受け付けている。ステップワゴン「AIR EX」は、本革巻ステアリングホイール、1列目シートヒーター、2列目オットマン、全席USBチャージャー、トリプルゾーンコントロール・フルオートエアコンディショナー、パワーテールゲート、ブラインドスポットインフォメーションなどを装備している。また、スポーティなステップワゴン「Spada」の最上級グレードである「Spada Premium Line」は、さらに上質感を高めた新型の「PREMIUM LINE BLACK EDITION」にアップグレードされている。フロントグリルのガーニッシュとアルミホイールをブラックに仕上げ、より洗練された個性的な外観に仕上げた。「Spada Premium Line Black Edition」は、e:HEV専用モデルである。
重要性: ホンダのステップワゴン (日本:2022年5月26日: ホンダ、新型ステップワゴンの詳細を発表参照) は、日本市場で20年以上販売されている「HA」プラットフォームをベースにしたDセグメント多目的車 (MPV) である。S&P Global Mobilityのライトビークル販売台数予測データによると、日本での同モデルの販売台数は2021年の約39,200台から2024年には55,100台に増加したという。当社は、2025年の同モデルの日本の販売台数は合計約44,600台を見込んでいる。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スズキ、国内工場の操業を再開
2025年4月4日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
スズキ株式会社|施設・運営
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
スズキは、「アルト」、「ワゴンR」、「ラパン」、「スイフト」、「ソリオ」、「クロスビー」などのモデルを生産している日本の湖西第2工場と相良四輪車体工場の全面操業の再開を決めた。
重要性: 愛知県豊田市の藤岡工場内にある中央発條の第3工場の冷間コイルラインの集塵機の爆発により、これらの工場の生産はここ数週間影響を受けている。この事故により、トヨタ、ダイハツ、スズキへの部品供給が滞り、生産が停止した。S&P Global Mobilityの3月31日時点の予測によると、この問題により、スズキ18,500台、ダイハツ28,000台、トヨタ約9,200台の合計約55,700台の生産損失を計上している。ダイハツも最近、影響を受けた日本の工場の通常操業を再開した。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、日本人従業員の賃上げを発表、サプライヤー問題で生産ラインのさらなる停止を確認
2025年3月17日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|施設・運営、生産、ライトビークル、人事
Ian Fletcher, Principal Analyst
トヨタは毎年行われる労使交渉の結果、日本人従業員の賃金を引き上げる、とCar Watchは報じている。同自動車メーカーは、9,950円から24,450円の間の昇給と7.6ヶ月分のボーナスを支給すると述べた。 これとは別に、ロイターは共同通信社の報道として、トヨタが3月15日朝、ここ数週間に中央発條工場で起きた事故の影響で、日本の堤工場の2つの生産ラインを停止したと伝えた。なお、本日 (3月17日) より生産を再開する予定であった。
重要性: トヨタが国内工場の従業員の賃金を全面的に引き上げるのは、これで5年連続となる。交渉は、全日本自動車産業労働組合総連合会、全トヨタ労働組合連合会、トヨタ労働組合だけでなく、サプライヤーのデンソー、アイシン、トヨタ紡織にも及んだ。この協定は、2月に始まった4回の交渉で合意されたもので、労働者が公正に報酬を受けることを保証するだけでなく、研修や表彰などの他の側面もカバーすることになる。一方、トヨタの堤工場では、愛知県豊田市の藤岡工場内にある中央発條第3工場の冷間コイルラインの集塵機の爆発事故の影響で、同国の工場での車両生産に支障が出ている。これまではスズキとダイハツの生産の一部車種のみが影響を受けていると報じられていた (日本:2025年3月14日:スズキ、日本の工場での操業停止を発表、ダイハツは操業停止を延長)、この混乱の衝撃は波紋を広げ続けている。堤工場は現在、「カムリ」、「カローラ」、「クラウン」、「プリウス」を生産しているが、これによりどの製品が影響を受けたかは不明である。しかしながら、トヨタは減産分を補う措置を講じる可能性が高い。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
テスラのドイツ労働者が労働条件をめぐる請願書に署名
2025年3月21日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ
テスラ|施設・運営、生産、企業、ライトビークル、人事、製品、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
ロイターの報道によると、テスラの労働者たちが、同社のグリューンハイデ(ドイツ)工場の労働条件改善を求める請願書に署名したという。工場の従業員3,000人以上が請願書に署名した;現在の職員数11,000人の約27%。請願書は「休憩時間の増加、人員配置の改善、管理職の脅迫戦術の廃止」を求めている。嘆願書にはまた、工場の従業員はすでに過労状態にあり、この状況は次期改訂「モデルY」が発売されればさらに悪化するだろうと書かれている。グリューンハイデで働くIGメタルのメンバーは、共同声明で「飲み物を飲んだりトイレに行ったりする時間さえないことが多い。定年までこのままでは誰もやっていけない。」と述べた。
要性: テスラのCEOであるイーロン・マスク氏は常に自社の労働組合結成に反対しており、労働組合の多いドイツの工場でもその姿勢は変わっていない。同国内最大の労働組合であるIGメタルは、テスラが同労働組合を完全に認め、テスラの全組合を持つことを許可するために戦っているが、これが認められるのは今までになく遠いようである。IGメタルはテスラの従業員にメンバーになることを奨励し、テスラの従業員と入社を考えている人の両方にアドバイスを提供している。IGメタルのメンバーはテスラの労働評議会で最大の単一グループを形成しているが、過半数には達していない。声明が言及している「いじめと脅迫」は、病気手当をめぐる論争とIGメタルへの参加を従業員に思いとどまらせようとする試みに焦点を当てているようである。マスク氏は昨年、グリューンハイデという小さな町にある工場での高い欠勤率を調査していると述べた。さらにテスラは、工場で働く約11,000人の従業員のうち約7,500人を対象に、仕事に満足しているかどうかを調査したと述べた。テスラの声明によると、従業員の約80%が満足しており、5%が不満を抱いており、残りはどちらとも言えないと答えたという。S&P Global Mobilityの予測によると、テスラのドイツでの今年の生産台数は22万台と予想され、新型「モデルY」の発売にもかかわらず2024年に製造された212,000台をわずかに上回る程度であるという。これは、2026年には272,000台に増加する予定である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
BMW、研究・開発部門の新責任者を任命
2025年3月14日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ
BMW AG|企業、研究・開発、ライトビークル、人事、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
BMWは、幹部の大幅な交代を発表し、ベテランのヨアヒム・ポスト氏が、6月1日付で新しい最高技術責任者に就任する。同自動車メーカーのソフトウェアデファインド電気アーキテクチャ「ノイエ・クラッセ」の量産化に成功した後、前CEOのフランク・ウェーバー氏が退任する。フランク・ウェーバー氏は、BMWが電気自動車 (EV) を開発する上で重要な役割を果たしてきた。彼の指揮の下、同社は重要なマイルストーンを迎えた:ノイエ・クラッセの最初の中型クロスオーバー車が、BMWの新たに設立されたハンガリーの工場で今年生産される予定である。このアーキテクチャは、新世代のEVを支え、電動化が進む市場でのブランドの競争力を高めることが期待されている。ヨアヒム・ポスト氏は、2022年から購買部門の責任者を務めた後、この重要な役割を引き継ぐ。BMWがEVラインアップの拡充を目指す中、同氏は同社での経験を生かし、今後のモデル開発をリードしていく。現在ロールス・ロイスを含むBMWのラグジュアリークラスの製品ラインを統括しているニコライ・マーティン氏を新たな購買責任者に任命したことは、ハイエンド市場への注力を継続しつつ、モビリティの未来も受け入れるという同社の戦略的提携を示している。
重要性: ポスト氏の開発責任者就任は、単なる定期的な人事異動ではない;急速に進化する自動車分野へのBMWの戦略的対応を反映している。従来の内燃機関が電気自動車やハイブリッド車に取って代わられる中、自動車メーカーは新しい技術や消費者の期待に迅速に適応しなければならない。ポスト氏のような経験豊かな幹部 を開発責任者に据えることで、BMWはEV市場で強い競争力を維持する意向を示している。また、ウェーバー氏の退任時期は、経営の移行に関するBMWの社内方針と一致している。同社の関係者は、こうした変化は経営陣の不和によるものではなく、重要なプロジェクトの完了後に起こることが多いと指摘している。これにより、継続性が確保されるだけでなく、新しいアイデアやアプローチでリーダーシップを一新することができ、これは、急速な技術進歩が特徴の業界では不可欠である。ポスト氏のリーダーシップの下でBMWが前進するにつれ、いくつかの重要な分野が開発努力の焦点となるであろう。「ノイエ・クラッセ」のアーキテクチャは、モジュール性と効率性を重視して、さまざまなEVをサポートするように設計されている。この柔軟性により、BMWは市場の要求や技術の変化に迅速に対応し、競合他社に対して有利なブランドを確立することができる。さらに、BMWが複雑なサプライチェーン管理、特にEV生産に不可欠な部品の確保に取り組む際には、ポスト氏の購買部門の経験が役立つであろう。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、新社長兼CEOを決定
2025年3月12日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
日産自動車株式会社|コーポレート
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst - Automotive

ゲッティイメージズ
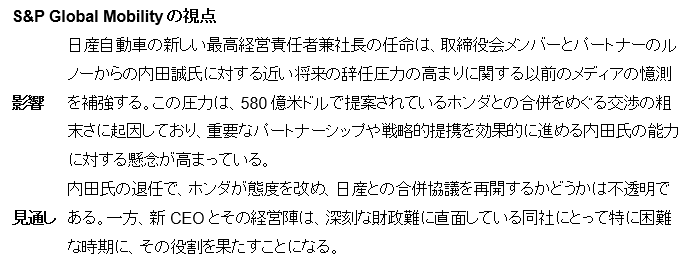
日産自動車株式会社は、長期的な成長に向けた基礎固めを行うとともに、同社の短中期的な目標を達成するため、上層部経営陣の大幅な人事異動を発表した。4月1日付で、取締役会は代表執行役および執行役の新しい役職および担当分野を承認した。現最高企画責任者のイヴァン・エスピノサ氏は、内田誠氏の後任として代表執行役社長兼CEOに就任する。
この移行に伴い、日産はエスピノサ氏の直属となる執行委員会の大幅な変更を実行する。AMIEOのチーフ・パフォーマンス・オフィサーであり経営委員会の委員長であるギヨーム・カルティエ氏は、グローバル・マーケティングとカスタマー・エクスペリエンスを担当するようになる。最高技術責任者兼執行役員には、中畔邦雄氏の後任として、現在の車両計画・車両要素技術開発本部を担当する常務執行役員の赤石永一氏が就任する。また、坂本秀行氏の後任として、現在、車両生産技術開発本部を担当する常務執行役員の平田禎治氏が、チーフ・モノづくり・オフィサーに就任し、生産・サプライチェーン管理を担当する。また、最高財務責任者のジェレミー・パパン氏も執行役員に任命される。中国マネジメントコミッティの議長、スティーブン・マー氏;チーフクオリティオフィサー、安徳光郎氏;チーフHRオフィサーの井原 徹氏は引き続き現職を務める。内田氏と坂本氏は6月の定時株主総会まで取締役にとどまる。
また、山﨑庄平日本・アセアン マネジメントコミッティ議長を中心に、山﨑 庄平は、日本・アセアン マネジメントコミッティ議長に加え、関係会社管理も担当する。アメリカズマネジメントコミッティ議長、クリスチャン ムニエ氏は、引き続き在任する。第二製品開発のCVP、富田達三氏は、R&Dで赤石氏の職務を引き継ぎ、さらにTdC (Total delivered Cost)トランスフォーメーション チーフとして、エスピノーサ氏にレポートする。現在、購買を担当するCVPの坂根学氏は、ストラテジーアクセラレーションチーフに就任し、エスピノーサ氏にレポートする。
エスピノサ氏は記者会見で、日産がホンダとの合併協議を再開するか、他の企業との提携を模索するかなど、同社の改革計画に関する具体的な質問を避けた。「この人事を知らされたばかりなので、考える時間が必要である。」と同氏は述べたとAutomotive Newsは報じている。しかしながら、同氏は、米国における「ラインアップの強化」の必要性を強調し、北米での業務への包括的アプローチにぜひ取り組みたい考えを示した。中国では、日産は、先般発売したセダン「N7」をベースに、現地向け電気自動車の開発に注力する。「当社はシステム全体を見るつもりである」とエスピノサ氏は述べた。また、同氏は「日産が再び輝くために、内田さんの仕事を続けていくことをとても楽しみにしている。日産には、今よりもはるかに大きな可能性があると信じている」。と内田氏の尽力を続ける熱意を伝えた。 一方、ジャパンタイムズが報じたように、内田氏は辞任を決意した理由について社内外から責任を問われていると説明した。同氏は、「社員が一丸となって課題に取り組める環境づくりが必要である。」と述べた。同氏は「しかしながら、一部の社員の信頼を失ったため..できるだけ早く新しい経営陣に交代して再出発することが最善の策だと思う」と認めた。
見通しと影響
日産自動車の新しいCEO兼社長の最近の任命は、取締役会メンバーとパートナーのルノーからの内田氏に対する近い将来の辞任圧力の高まりに関する以前のメディアの憶測を補強する。この圧力は、580億米ドルで提案されているホンダとの合併をめぐる交渉の粗末さに起因しており、重要なパートナーシップや戦略的提携を効果的に進める内田氏の能力に対する懸念が高まっている。内田氏は当初、ホンダとの合併を強く支持する人物と見られていたが、ホンダが日産の再建努力の遅さと財務上の課題の深刻さに不満を表明したため、ホンダのCEOである三部敏宏氏との間の緊張が高まった。最終的には、持株会社を設立する代わりに日産が完全子会社になることをホンダが主張し、日産が受け入れられなかったため、合併協議は決裂した。内田氏の退任を受けて、ホンダが態度を改め、日産との合併交渉を再開するかどうかは注目される(日本:2025年2月18日:ホンダは、日産の前CEOが辞任すれば日産との合併交渉再開の可能性がある-報道参照) 。
新CEOとその経営陣は、深刻な財政難に直面している同社にとって特に困難な時期に、その役割を果たすことになる。最近、日産は2024/25年度の当第3四半期の親会社株主に帰属する当期純利益は、前年比98.4%減の51億4,800万円 (約3,370万米ドル) と発表した。これらの課題に対応するため、日産は、財務の安定性と経営効率の向上を目的とした大規模な再生計画を開始した。しかしながら、組織の再構築、製造プロセスの最適化、および業務の合理化の複雑さは、即時の改善を達成することが困難であることを示唆している。同社が実質的な費用対効果を実現するまでには数年かかる可能性がある。販売不振が続く中、日産は再生に向けた取り組みを支え、市場の圧力が続く中で事業を安定させるために十分なキャッシュフローを生み出すことに注力しなければならない。新しい経営陣は、ステークホルダーの信頼を回復し、自動車メーカーにとって持続可能な道筋を描くために、断固とした行動をとる必要がある(日本:2025年2月14日:日産は2024~25年度の当第3四半期の所有者に帰属する当期利益は、前年比98.4%減となったを報告している参照)。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スズキ、日本の工場の操業停止を発表、ダイハツ、操業停止を延長
2025年3月14日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
スズキ株式会社、トヨタ自動車株式会社| 施設・運営、生産、コンポーネント、ライトビークル
Ian Fletcher, Principal Analyst
スズキは先週、サプライヤー供給元の中央発條で事故が発生したことを受け、日本での生産を一部停止した。ロイターは当初、日本経済新聞の記事を引用して、同自動車メーカーの湖西工場で3月10日と11日に一時操業停止が実施されていると報じた。しかしながら、その後、ロイターは日刊自動車新聞を引用し、スズキが日本の2工場で一部の生産ラインを3月19日まで停止すると報じた。これとは別に、ロイターは、また、トヨタグループの工場は今週から続いているダウンタイムの影響を受け続け、ダイハツの京都工場の操業は3月17日から19日の間停止されたままであると報じている。
重要性: 先週、愛知県豊田市の藤岡工場にある中央発條第3工場の冷間コイルラインの集塵機で爆発があった。この事故は当初、トヨタ自動車の一部の生産拠点への部品供給に影響を与えたと報じられたが、スズキに関するニュースは、その影響がより広範囲に及んでいることを示唆している。 影響を受けたトヨタの一部拠点では既に生産が再開されており、高岡工場は昨日 (3月13日) に操業を再開したが、トヨタ・RAV4を生産している豊田自動織機長草工場も部品を確保したと報じられている(日本:2025年3月13日:トヨタ、国内工場の生産再開スケジュールを発表参照) 。ダイハツの京都工場は3月17日に操業を再開する予定であったが、、一貫した部品供給を確保したいため、現在は数日延期することを決定した。影響を受けた工場が復旧すれば、自動車メーカーは生産の遅れを取り戻すための措置を講じる可能性が高い。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、国内工場の追加生産停止を発表
2025年3月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|生産
トヨタ自動車株式会社は本日、先週発生したばね部品メーカー、中央発條の藤岡工場での爆発事故に関連して、追加生産を停止すると発表した。日刊自動車新聞によると、トヨタは(「ハリアー」と「RAV4」を生産する)高岡工場の2ラインのうち1ライン、「RAV4」を生産する豊田自動織機長草工場の両ライン、ダイハツ工業京都工場の「プロボックス」の1ラインをの業務を一時停止する。休業期間は3月10日の第2シフトから3月11日の第1シフトまでである。その後の業務については、3月11日の正午頃に決定する。
重要性: 先週、藤岡工場(愛知県豊田市)にある中央発條第3工場の冷間コイルラインの集塵機で爆発があった。これはトヨタ自動車への部品供給に影響を与えた。当社は、今回の生産停止がトヨタの生産に与える影響については現在精査中であるが、日刊自動車新聞によると、トヨタは「当社は、将来的には減産分の穴埋めを検討するため、現段階では予測できない。」と述べた。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
三菱、次世代アウトランダーを日産から分離か-報道
2025年3月7日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本
三菱自動車工業株式会社、日産自動車株式会社|生産、JV/提携、ライトビークル、製品
Stephanie Brinley, Associate Director
現在の三菱・アウトランダーは、日産・ローグとプラットフォームを共有している;次世代はそうではないかもしれないという報告もある。 Automotive Newsが「工場に詳しい人物」の話として報じた。三菱はコメントを控えた。現在の「アウトランダー」は、ルノー・日産共同のコモン・モジュール・ファミリー (CMF) プラットフォームを採用している;次世代機は2027年に発売予定で、現行機はフェイスリフトしたばかりである。
重要性: 報道されたこの動きは、日産と三菱の距離をさらに縮めた。日産が介入して三菱の株式を取得し、2016年にルノーとの提携に持ち込んだ (日本:2016年5月26日:三菱、日産と戦略的アライアンス契約締結、経営陣刷新を発表参照) 。それ以来、両社の間ではほとんど活動が行われておらず、三菱は、ホンダと日産を統合するための合併の試みに参加することを拒否したが、それはホンダと日産の以前の了解覚書 (MOU) の一部であった(MOU;日本2025年1月24日:三菱自動車、ホンダと日産の合併に参加しないことを決定-報道および日本:2024年8月2日:ホンダ、日産、三菱は、ビークルインテリジェンスと電動化に関するMOUに署名参照)。「ローグ」は、米国市場で「アウトランダー」のプラグインハイブリッドパワートレインのバージョンを使用することを目指しているが、それは2026年まで計画されていない (米国:2024年10月18日:日産はPHEV「ローグ」の発売を認めている参照) 。日産と三菱は2024年中にいくつかのプロジェクトを発表しているが、日産は三菱への出資比率を引き下げている。発表されたプロジェクトには、1トンのピックアップトラックと自動運転車のジョイントベンチャー (JV) が含まれる(JV;米国-日本:2024年4月1日:日産と三菱、電動化を視野に入れた将来の1トンピックアップトラックで提携および日本:2024年11月2日:日産と三菱、自動運転システムと蓄電池に特化したJVを設立へ-報道参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、ウーブン・シティの第1段階を発表
2025年2月24日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|テクノロジー、トレンド・進化
トヨタは、先進的なモビリティ技術を実証するために日本の中部で開発されている先駆的な実証都市であるウーブン・シティの第一段階を開始した。静岡県裾野市に位置するこの革新的な都市には、自動地上移動のための専用道路と、物流サービスの自動化実験のために設計された地下道である「物流ストリート」がある。ジャパンタイムズによると、第一段階は47,000平方メートルの広さで、昨年完成した14の建物のうち8棟が含まれており、主に居住用の建物で、インベンターと居住者の交流センター、エネルギービルなどがあるという。現在、水素パイプラインなどのインフラや内装工事を進めている。市内には歩行者用と自動運転車用を含む3つの地上道路があり、歩行者と車の流れを監視するさまざまなセンサーを備えた信号機が設置される。ウーブン・シティは最終的に約70万平方メートルに拡張され、トヨタグループ内外の約2,000人の住民を収容する予定である。今秋にもトヨタの従業員ら約100人が移転する見通しである。
重要性: 先日、コンシューマーエレクトロニクスショー (CES) 2025において、トヨタはウーブン・シティ研究開発プロジェクトのフェーズ1の完了を発表した。同社はまた、フェーズ2の作業が開始されたことを明らかにし、最初の「インベンター」グループは今年後半に入居する予定である。ウーブン・シティのビジョンは、5年前のCESで発表された (米国-日本:2025年1月7日:CES 2025:トヨタ、ウーブン・シティ・プロジェクトのフェーズ1を完了、米国ロケットメーカーへの投資に合意、米国2020年1月7日:CES 2020:トヨタ、日本でプロトタイプ研究都市を計画中および日本:2021年2月23日:トヨタ、ウーブン・シティプロジェクトを着工参照) 。ウーブン・シティの核となるのは、トヨタがロボット工学や自動運転車、コネクティビティの開発を研究室からより自然な日々の交流を研究できる場所に移すためのスペースを提供することである。トヨタはこの都市の主要な電力源を水素にする計画である。2,000人の居住者には、ホームロボティクスや入居者の健康をチェックするセンサーベースのAIなど、最新のヒューマンサポート技術を導入する計画である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、内田誠CEOの交代を検討-報道
2025年2月27日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
本田技研工業株式会社、日産自動車株式会社|コーポレート
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst - Automotive
ブルームバーグが関係筋の話として報じたところによると、日産自動車株式会社は業績不振と本田技研工業株式会社との合併交渉の決裂を受けて、CEO交代の準備を進めている。日産の取締役会は、入社22年で2019年末からCEOを務めている内田誠氏の後任候補を探している。関係筋は、協議の機密性を考慮して匿名を希望した。日産はこの件に関してコメントを差し控えている。ロイターによると、同社は3月12日に経営陣の再編を発表する予定だが、事情に詳しい3人の関係者によると、内田氏はこの時点では留任する可能性があるという。
重要性: これは、580億米ドルのホンダとの合併契約をめぐる交渉の失敗を受けて、内田氏が取締役とパートナーのルノーから数ヶ月以内に辞任するよう圧力を受けているという最近の報道を裏付けている。しかしながら、内田氏は2026年まで現職にとどまる意向を示している。最新の報道によると、内田氏は日産とホンダの交渉が決裂した要因の1つであり、重要なパートナーシップや戦略的提携を通じた同社の舵取りにおける同氏の有効性について、取締役の間で懸念が高まっている (日本:2025年2月18日:ホンダは、日産のCEOが辞任すれば日産との合併交渉再開の可能性がある-報道参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ、日産のe-Power技術撤退要求が合併交渉決裂の理由
2025年2月20日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
本田技研工業株式会社、日産自動車株式会社|合併・買収 (M&A)
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
本田技研工業が日産自動車を事実上買収して子会社化することを要求したことが、両日本の大手自動車会社の合併を頓挫させた主な要因だったが、ホンダも同様に受け入れがたい要求をしたという。Automotive Newsによると、読売新聞から報道を参考にし、ホンダは日産のハイブリッド技術「e-Power」シリーズを放棄し、自社のハイブリッド技術を採用することを望んでいたという。ホンダ幹部は読売新聞に、「当社はHV [ハイブリッド車]では日産に一歩リードしているのは明らかである。」という公式見解を出した。事情に詳しい情報筋がAutomotive Newsに語ったところによると、日産の研究開発 (R&D) 幹部は、日産が20億米ドル以上を投資した自社開発技術を破棄するというホンダの要求を受け入れることは容認できないと考えたという。「エゴのぶつかり合いだった」と関係筋は述べた。
重要性: ホンダと日産のような巨大グローバル企業の合併は、それぞれの経営陣の間でかなりのイデオロギーの違いに直面する可能性が高い。各組織には通常、独自の確立された企業文化、価値観、戦略的優先事項があり、合併後にスムーズに統合されない可能性がある。例えば、2社はイノベーション、持続可能性、市場戦略に対するアプローチが異なり、製品、技術、マーケティング戦略、グローバルプレゼンスに関連する意思決定プロセスにおいて潜在的な衝突を引き起こす可能性がある。フィナンシャル・タイムズの最近の報道によると、ホンダは日産の内田誠CEOが退任した場合、日産との買収交渉を再開する用意があるという。この報道によると、内田氏は日産にとってホンダとの提携を最も強く支持してきた人物の1人だという。しかしながら、ホンダが日産のリストラのペースと財務問題の深刻さに不満を募らせているため、内田氏とホンダのCEOである三部敏宏氏との間の緊張は高まっている (日本:2025年2月18日:ホンダは、日産の元CEOが辞任すれば日産との合併交渉再開する可能性がある-報道参照) 。ホンダと日産の合併交渉が決裂したと報じられて以来、フォックスコンやKKRなどの企業が日産株の取得を模索していると報じられている。フィナンシャル・タイムズによると、ドナルド・トランプ米大統領の関税政策を管理するために国内生産能力を強化しようとしている米国の自動車メーカーの参加も検討中であるいう(日本:2025年2月12日:フォックスコン、日産の株式取得への関心を確認および日本-米国:2025年2月17日:米国のプライベート・エクイティ企業KKRが日産に投資-報道参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、降雪で国内生産を一時停止
2025年2月19日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
トヨタ自動車株式会社|設備・業務
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日刊自動車新聞によると、トヨタ自動車株式会社は本日(2月19日)、降雪による高速道路の通行止めを受け、国内10工場20ラインの生産を一時停止すると発表したという。対象ラインは、高岡工場1・2ライン、堤工場1・3ライン、田原工場1・3ライン、豊田自動織機長草工場、トヨタ車体富士松工場、ダイハツ工業株式会社の京都工場である。これらの20ラインの生産は、現地時間の今晩の第2シフト中に再開される見込みである。また、トヨタ自動車九州、トヨタ自動車東日本宮城大衡工場、トヨタ自動車東日本岩手工場、日野自動車羽村工場-の4工場の6つの生産ラインを本日夕方から停止し、現地時間の明日(2月20日)朝から稼働を再開する予定である。
重要性:気象専門家は、日本の北から西日本の日本海側を中心に、今日も大雪警報を出している。住民は交通機関の乱れや雪崩の危険性に警戒するよう求められている。大雪はすでに交通に影響を及ぼし始めている。この混乱は、住民の移動を妨げるだけでなく、地域の生産施設の正常な稼働にも影響を与えている。悪天候により、原材料のタイムリーな配送や完成品の輸送が妨げられ、多くの企業がサプライチェーンの課題に直面している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
VW、元メルセデス幹部を最高ブランド責任者に起用
2025年2月14日-Autointelligence|ヘッドライン分析–ドイツ
フォルクスワーゲン AG|企業、人事、コーポレート
Tim Urquhart, Principal Analyst
フォルクスワーゲン (VW) は、クリスティン・ウォルバーグ氏を新しいチーフ・ブランド・オフィサーに任命したと発表した。この新たに創設された役割は、競争が激化する自動車業界でブランドプレゼンスの再活性化とマーケティング戦略の再編成を目指すVWにとって極めて重要である。メルセデス・ベンツの元幹部であるウォルバーグ氏は、豊富な経験と新鮮な視点をもたらし、VWは2030年までに技術面で世界をリードする量産メーカーになるという野心的な目標に向けてブランドを推進することを期待している。
重要性: ウォルバーグ氏の任命は、自動車の手頃な価格の問題、金利の上昇、顧客の期待の変化など、自動車業界が重大な課題に直面している時期に行われた。こうしたプレッシャーにより、VWを含む多くの自動車ブランドは戦略の転換を迫られている。同社は、現在の急速に変化する市場環境では、既存の戦略を改善するだけでは不十分であることを認識している。その代わりに、ブランドのエンゲージメントとマーケティングを包括的に再考することが不可欠である。ウォルバーグ氏は新しい役職で、前最高マーケティング責任者のスーザン・フランツ氏の職務を引き継ぐことになり、フランツ氏は、わずか1年で同社に部署替えされた。VWはフランツ氏の新しいポジションを明らかにしていないが、今回の異動は、ブランド戦略を有能な人材の手に委ねるという同社のコミットメントを示している。ウォルツ氏は、VWブランドのCEOであるトーマス・シェーファー氏の直属となり、組織内での同氏の役割が戦略的に重要であることを示している。同氏は、世界で最も有名で象徴的な自動車ブランドの一つを再活性化する責任を負うことになり、このブランドは、新しい競合他社が脚光を浴び、そして、いくつかの期待外れの製品がそのイメージをある程度傷つけたため、近年、ポジティブな光を浴びることに苦労している。ウォルバーグ氏の主な課題は、品質とデザインという伝統的なブランド価値を融合させ、より若くテクノロジーに精通したオーディエンスに向けてブランドの方向性を変えることである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産が2億1,100万ユーロを拠出、ルノーグループの2024年のリ利益に貢献
2025年2月14日-Autointelligence|ヘッドライン分析-フランス-日本
日産自動車株式会社、ルノー|JV/提携、財務、ライトビークル、コーポレート
Ian Fletcher, Principal Analyst
ルノーグループは、日産が2024年の利益に2億1,100万ユーロを拠出すると発表した。当期の平均為替レートを1ユーロ162.5円として算出している。
重要性: ルノーは過去1年ほどの間に、提携関係の変更の一環として日産に株式の一部を売却したが、現在も日産の資本の35.71%を保有している。17.05%を直接保有し、残りの18.66%をルノーが最終的に売却するまでのルノーが受益者となるフランスの信託会社に移している。日産は昨日(2025年2月13日)、2024/25年度第3四半期決算を発表した。この結果、ルノーグループの2024年第4四半期の純利益は約5,900万ユーロとなりましたが、日産の当期純利益は前年比98.4%減の51億4,800万円となった (日本:2025年2月14日:日産は2024~25年度当第3四半期の所有者に帰属する当期純利益は、前年比98.4%の減益となったと報告し、事業再生対策を説明している参照)。ルノーグループは2月20日に2024年の決算を発表する。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、ホンダとの合併交渉打ち切り報道で新たなパートナーを模索-報道
2025年2月7日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
本田技研工業株式会社、日産自動車株式会社 |合併・買収 (M&A)
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
フィナンシャル・タイムズ(FT) の報道によると、日産のCEOの内田誠氏がホンダのCEOに合併協議を打ち切ると伝えたことを受け、同社は技術分野での戦略的パートナー探しを開始したという。その事情に詳しい2人の関係者によると、新たな提携の模索は自動車分野以外にも広がりそうだという。さらに、一部の取締役会メンバーは、台湾のiPhone受託製造会社フォックスコンとの協業を検討するという考えをどうやら受け入れているようだ。
重要性:さまざまな報道によると、日産はホンダとの合併協議を打ち切ることを選択したが、これは合併提案に関する支配権をめぐる対立が原因だという。フィナンシャル・タイムズ (FT) は、ホンダが経営不振の同自動車メーカーを再生させるため、日産の完全支配権を取得するよう株主や社内から圧力を受けていたと報じた。その結果、ホンダは日産の子会社化に関心を示したが、日産はこの提案を拒否した。さらに記事は、日産は当初、グループ内の異なる派閥にホンダとの合併を説得するための「対等合併」として取引を提示したが、ルノーに関係する筋は、提案された取り決めは基本的にはホンダが支配権を獲得するものであると主張したと指摘している (日本:2月5, 2025:日産、ホンダとの合併協議中止-報道参照) 。今回の動きで、フォックスコンは日産株の取得競争に復帰したようである。2024年12月の報道によると、フォックスコンは日産に同社株の購入について接触していたという。さらに台湾の中央通訊社は、フォックスコンの電気自動車 (EV) の最高戦略責任者である関潤氏がフランスに行き、日産における大株主であるルノーと交渉したと報じた。記事によると、フォックスコンは日産に株式取得への関心を「直接表明した」が、「日産が同意しなかった」後、焦点をルノーに移したという。17.05%が直接出資、18.66%がフランスの信託を保有する同自動車メーカーの株式35.7%を現在保有しており、日産が新たな戦略的パートナーを模索する上でルノーは重要な役割を果たすとみられる。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、新型「GRカローラ」の受注を開始
2025年2月4日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
トヨタ自動車株式会社|ライトビークル、製品、内燃機関 (ICE)、展示・発売、電動化
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
トヨタ・ガズー・レーシング (TGR) は、モータースポーツ競技の世界観を取り入れたデザインに改良した「GRカローラ」の受注を開始した。本日(2月4日)より日本全国のトヨタ販売店にて予約受付を開始し、3月3日より正式販売を開始する。トヨタは「「進化した」GRカローラ」について、「スーパー耐久シリーズ」などで培ったノウハウを活かし、高速コーナリング性能や加速性能、冷却性能などを向上させたとしている。最新の「GRカローラ」には、進化した「GRヤリス」にも搭載されている新開発の8速「GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (GR-DAT) 」を採用している。また、現在「GRカローラ」の所有者には、進化したの「GRカローラ」のコンポーネント購入して装着することで、走行性能の向上を楽しむことができる。
重要性:「GRカローラ」は、トヨタの日本におけるレース活動とパフォーマンスチューニングを象徴する「ガズーレーシング」からの名前の「GR」に由来している。このモデルは、2024年8月2日に米国で最初に導入されたが、日本の市場要件に合わせてカスタマイズされている (米国:2024年10月18日:トヨタGAZOOレーシングノースアメリカがレース対応の「GRカローラ」を発表(/document/show/phoenix/5751299?connectPath=AutoIntelligenceLandingPage&searchSessionId=a8ffcea0-062f-4dec-bf61-afd6e5c18678%20)参照)。TGRは、2月7日~9日に開催される「大阪オートメッセ2025」に、日本市場向けに改良した「GRカローラRZ」を出品する。価格はマニュアル車が568万円、オートマチック車が598万円である。この車両はターボチャージャーとインタークーラーを備えた1.6リッター直列3気筒エンジンを搭載し、最高出力224kW、ピークトルク400ニュートンメートルを発生する。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車グループ、1月の世界販売台数が減少、韓国で「アイオニック9」の予約を開始
2025年2月4日-Autointelligence|ヘッドライン分析-韓国
現代自動車株式会社|会社、販売、ライトビークル、中型&大型商用車、製品、コーポレート、内燃機関 (ICE)、電動化
Jamal Amir, Principal Research Analyst
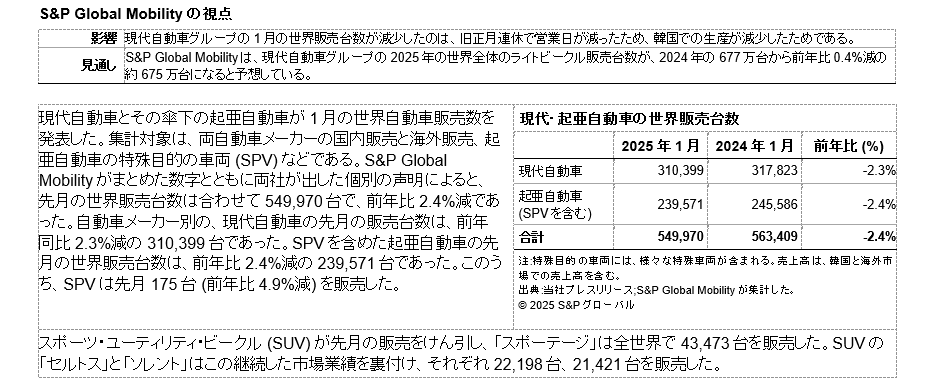
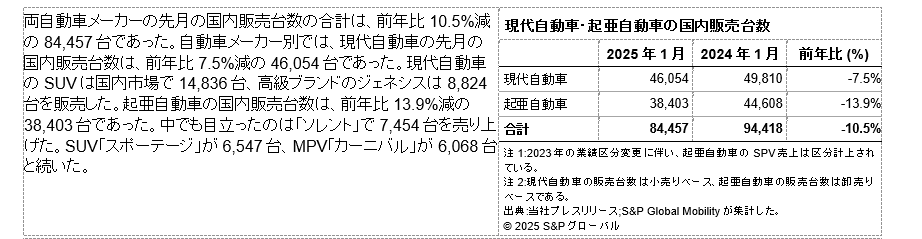
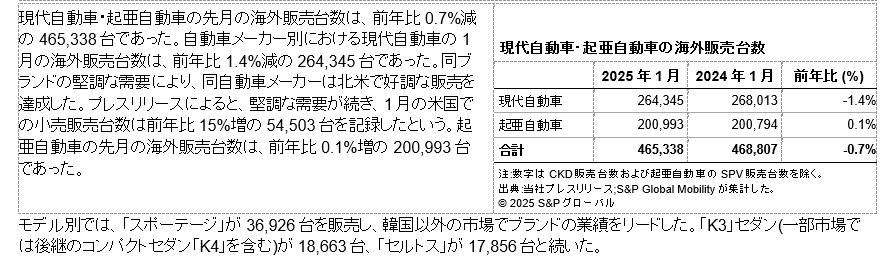
モデル別では、「スポーテージ」が36,926台を販売し、韓国以外の市場でブランドの業績をリードした。「K3」セダン(一部市場では後継のコンパクトセダン「K4」を含む)が18,663台、「セルトス」が17,856台と続いた。
現代自動車、韓国で「アイオニック9」の予約受付を開始
聯合ニュースによると、現代自動車は韓国初の大型電気SUV「アイオニック9」の予約受付を正式に開始した (韓国-米国:2024年10月30日:現代自動車、3列シート電気自動車「アイオニック9」のティーザー映像を公開参照)。110.3 kWhのバッテリーを搭載し、後輪駆動バリアントでは1回の充電で532kmの航続距離を達成する。現代自動車グループのエレクトリック・グローバル・モジュラー・プラットフォーム(E-GMP)をベースにしている。「アイオニック9」のデザインは、「高級船の洗練された船体」からインスピレーションを得ており、大型SUVの中でクラストップの空気抵抗係数0.259を誇る滑らかな空気力学的プロファイルを実現している。これにより、車両の効率が向上し、車内が広くなる。「アイオニック9」には、6人乗りと7人乗りの両方の構成がある。「アイオニック9」の価格は政府補助金を除く6,715万ウォン (45,628米ドル) から7,941万ウォンである。現代自動車は、「アイオニック9」を電動SUVのフラッグシップモデルとして位置づけ、航続距離の拡大と先進的なデザイン、快適性を融合させ、国内外の市場にアピールする。S&P Global Mobilityのデータによると、「アイオニック9」の世界販売台数は2025年に約33,000台、2026年には約66,000台に増加する見込みであるという。米国が同自動車の最大の市場で、韓国がそれに続く。
見通しと影響
現代自動車グループの1月の世界販売台数が減少したのは、旧正月連休で営業日が減ったため、韓国での生産が減少したためである。
現代自動車は今後、グローバル販売戦略の強化と生産プロセスの最適化を通じて、財務・オペレーショナル・リスク管理能力を積極的に強化する計画である。今後もハイブリッド車やEVの新モデルを投入し、世界の顧客から信頼されるトップブランドとしての地位を確立し、持続可能な自動車ソリューションで世界市場をリードしていくことを目的としている。起亜自動車は今年、「タスマン」ピックアップトラックや「シロス」SUV、「PV5」パーパスビルトビークル(PBV)、フル電動化「EV4」、「EV5」などの新モデルを戦略的に発売し、世界販売の勢いを維持する計画である。
現代自動車・起亜自動車は、2025年の世界販売台数を前年比2.2%増の約739万台とする2025年の目標を掲げている。現代自動車 (ジェネシスを含む) は、地域ごとに最適な製品ポートフォリオと車両供給管理を展開し、全体販売台数417万台 (前年比0.8%増) を目指す。国内市場は前年比0.7%増の71万台、海外市場は前年比0.8%増の346万台を見込んでいる。起亜自動車は、今年の世界販売目標を322万台 (前年比4.1%増) としている。国内市場は前年比1.8%増の552,000台、海外市場は前年比4.6%増の266万台を見込んでいる。
S&P Global Mobilityは、減災自動車、起亜自動車、ジェネシス、ロシアのみのソラリス、ベトナムのみのタコなど現代自動車グループのグローバルライトビークル販売台数が、2024年の677万台から2025年には前年比0.4%の675万台に減少すると予想している。当社は現代自動車ブランドの今年の世界販売台数は前年比0.8%減の約366万台、起亜自動車は前年比0.6%増の約286万台と予想している。ジェネシスブランドの2025年の販売台数は約215,000台 (前年比5.6%減) を見込んでいる。2025年のロシア専売ブランドソラリスの販売台数は前年比11.9%減の約13,000台、ベトナム専売ブランドタコの販売台数は前年比8.0%減の約8,300台を見込んでいる。
当社のライトビークル予測は、乗用車と小型商用車のみを含む。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ、新型「フリードe:HEV」発売へ
2025年1月20日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
本田技研工業株式会社|製品
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
本田技研工業は、世界的な原材料・物流コストの上昇を受け、改良型「フリードe:HEV」を2月6日に発売すると発表し、メーカー希望小売価格 (MSRP) を引き上げた。今回の改良では、外装塗装に新塗装を採用するとともに、塗装に使用するクリア素材を変更し、車両のボディの光沢感を向上させるとともに、耐久性を1.5倍以上向上させている。また、これまで「Air EX」と「クロスター」の6人乗りモデルに限定していた「アダプティブドライビングビーム」、「後退出庫サポート」、「マルチビューカメラシステム」、「LEDアクティブコーナリングライト」などの安全装備や運転支援技術を、顧客の声を反映して「Air EX」と「クロスターの全車種およびスロープ装備車に拡大し、顧客の選択肢を広げた。
重要性: 「フリード」はホンダの国内ライトビークル販売の11.9% (2024年) を占める人気車種の1つである。GSP2プラットフォームを搭載したBセグメント多目的乗用車 (MPV) は、S&P Global Mobilityのライトビークル販売データによると、2021年の約69,600台から2024年には約80,800台へと、ここ数年順調に販売台数を伸ばしている。今後、2025年には国内で約87,000台の「フリード」販売を見込んでいる。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
北米トヨタCOO退任
2025年1月23日-Autointelligence|ヘッドライン分析-米国
トヨタ自動車株式会社|会社・ライトビークル・人事
Stephanie Brinley, Associate Director
北米トヨタ (TMNA) のジャック・ホリス最高執行責任者 (COO) が退任した;後任には長年トヨタの幹部を務めてきたマーク・テンプリン氏が就任する。トヨタの声明によると、ホリス氏は1月22日付けで退任し、テンプリン氏が1月27日にCEOに就任する。テンプリン氏は現在、Toyota Financial ServicesとToyota Insurance Management Solutionsの責任者であり、Toyota Motor Credit CorporationとToyota Financial Savings Bankの取締役会長でもある。テンプリン氏は今後もToyota Financial Servicesのグローバルな役割を担う。ホリス氏と同様、テンプリン氏もTMNAの社長兼CEOであるテッド・オガワ氏の直属となる。オガワ氏は声明で、「先日、ジャックから引退の意向を伝えられた。ここでの勤務中、ジャックはワールドクラスのセールスおよびマーケティングチーム、優れたディーラー関係の構築に貢献し、オリンピックとパラリンピックの真のブランド提唱者としての役割を果たした。彼のトヨタへの献身に感謝し、健闘を願っている。」と述べた。テンプリン氏は、北米におけるトヨタおよびレクサスブランドの両方の販売、マーケティング、トヨタ・レーシング・デベロップメント、製品企画、カスタマーサービス、需給、製造、製品サポートを統括する。テンプリン氏は以前、米国でサイオンとレクサスのブランドを率いていた。
重要性: ホリス氏のトヨタでのキャリアは33年に及ぶが、同氏は2022年にボブ・カーター氏からCOOの座を引き継いだ (米国:2022年6月7日:北米トヨタが退任、経営陣の交代を発表参照) 。
声明の中でホリス氏は、「トヨタが私に与えてくれた素晴らしい機会に感謝しており、世界中の偉大なディーラーだけでなく、トヨタの多くの素晴らしいチームメンバーと共に働けたことを光栄に思っている。退任するのに完璧なタイミングはないが、新しい年の始まりを考えると、ちょうどいいタイミングである。私は新たな挑戦を続けるトヨタの未来に自信を持っている。」と述べた。この動きは意外なようだが、トヨタには経験豊富な幹部がいる。ホリスの退任の具体的な理由は明らかではないが、彼の声明は彼が新しい役割に移ることを示唆している。64歳のテンプリン氏は、58歳のホリス氏よりも年上である;この要因は、テンプリン氏の任期が5年を超えず、それ以下になる可能性が高いことを示唆している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
いすゞタイランド、新型ディーゼルエンジン「D-MAX」「MU-X」発売へ
2024年11月21日-Autointelligence|ヘッドライン分析-タイ
いすゞ自動車|市場分析・展示会・新製品発表会
Isha Sharma - Research Analyst
企業プレスリリースによると、いすゞ自動車は、新型1トン積みピックアップトラック「D-MAX」と7人乗り乗用車「MU-X」をタイで発売し、11月28日に発売すると発表したという。このモデルは、新開発の2.2リッター2164ccディーゼルエンジン「RZ4F」、出力120 kW、トルク400ニュートンメートル( N・m)を搭載し、8速ATと組み合わせることで、性能と燃費を大幅に向上させている。D-MAXは全長5,280 mm、重量1,895 kg、最小回転半径6.1 mを持つ。MU-Xは、全長4,860 mm、エンジン仕様はD-MAXと同じであるが、重量は2,045 kg、回転半径は5.6 mと小型化し、広さとパワーを両立した。 重要性: いずれも加速性や始動性の向上を重視しており、カーボンニュートラル社会の実現に向けたビジョンの一つである電気自動車や燃料電池車の開発など、自動車の動力源技術にマルチパスウェイで取り組んでいる。S&P Global Mobilityのライトビークルデータによると、2024年のタイにおけるD-MAXの販売台数は62,709台 (前年比45.7%減)、MU-Xの販売台数は前年比43.3%減の11,805台を見込んでいるという。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
シンガポールの物言う株主、日産株取得
2024年11月13日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
日産自動車株式会社|合併・買収 (M&A)
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst - Automotive
日産の急速な業績悪化は、日本の著名な物言う株主の関心を引き、同社の回復戦略に新たな不確実性をもたらした。ロイターの報告によると、エフィッシモ・キャピタル・マネジメントは問題を抱える同自動車メーカーの株式を取得した。11月11日の規制当局の発表では、9月末時点でケイマン諸島に登記されたECMマスター・ファンドが日産株式の2.5%を保有していることが明らかになった。SECへの提出書類によると、ECMマスター・ファンドはエフィッシモと関連がある。
重要性: このニュースは、日産が時代遅れの製品ラインアップ、高額なディーラー奨励金、北米でのハイブリッド車不足のために利益と販売が激減している時に発表された。この状況は、同日本自動車メーカーのグローバル生産能力を20%削減と9,000人の人員削減を余儀なくされた。経営不振企業への投資で知られるシンガポールのヘッジファンドが日産株を取得したことで、日産の財務の安定性と将来の見通しにさらなる懸念が生じている。日産は最近、業績を改善し、市場の変化に迅速に対応できる、より機敏で回復力のある事業を構築するために、直ちに行動を起こしていると述べた。持続的な成長を実現するため、同社は2026年度までに350万台の年間売上を目指し、継続的な収益性とキャッシュフローを確保する体制を構築する計画である。「The Arc」経営計画を着実に推進するとともに、日産はルノーグループ、三菱自動車工業(MMC) および本田技研工業 (株)との戦略的アライアンスにより、投資効率の向上と商品競争力の強化を図るつもりである。日産は、2024年度比で固定費を3,000億円 (19億米ドル)、変動費を1,000億円削減し、健全なフリーキャッシュフローを確保する計画である(日本:2024年11月8日:日産、2024~25年度上期決算発表、9,000人削減、通期予想下方修正参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ、ユーティリティ・ビークル「パスポート」の第4世代を米国で発売
特集
2024年11月15日-Autointelligence|ヘッドライン分析-米国
株式会社本田技研工業|販売・軽自動車・商品・展示・発売・内燃機関 (ICE)
Stephanie Brinley, Associate Director

アメリカン・ホンダ
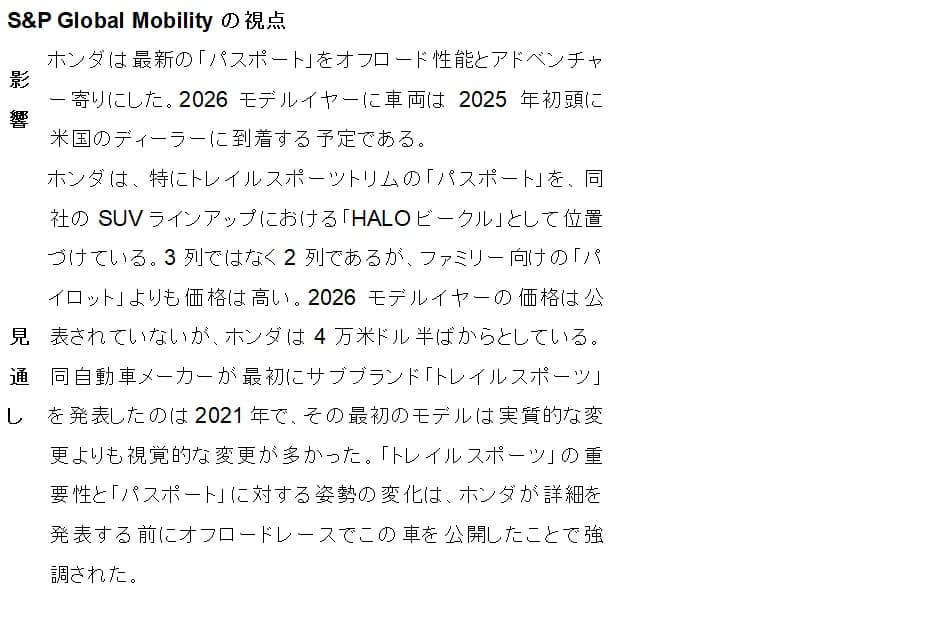
この第4世代「パスポート」で、ホンダは「トレイルスポーツ」モデルにさらなる能力を与えることで、オフロードとアドベンチャーの性能を強化した。「パスポート」は「パイロット」と機械的な関連性を維持しているが、「パスポート トレールスポーツ」のオフロード機能は設定を一歩進めている。最新の「パイロット」は、2023モデルイヤーに導入される(モデルイヤー;米国:2023年1月17日:ホンダ、2023年モデルで「パイロット」を改良、「トレイルスポーツ」を強化参照) 。ホンダ・ナショナル・オート・セールス担当アシスタント・バイスプレジデントのジェシカ・ローダーミルク氏は声明の中で、「再設計された「パスポート」は、ホンダのタフなデザインと機能を、タフな新しいスタイルで完全に再定義し、日常の運転の快適さを失うことなく楽しい冒険のためにオフロードのパフォーマンスを大幅に向上させる。その上に、ホンダの頑丈なデザインと性能を完全に表現するために開発された当社のトレイルスポーツコンセプトの究極の検証である新しい「パスポート トレイルスポーツ」、「HALOオフロード車」がある。」と述べた。

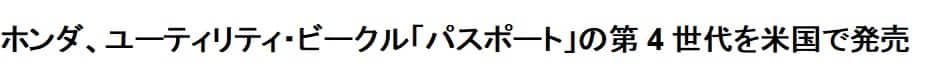
新しい「パスポート」は、カリフォルニアのホンダがデザインし、オフロード性能の向上、乗り心地とハンドリングの改善、全体的なリファインに重点を置いたエンジニアリングと開発を行った。フロント横剛性は72%、リアねじれ剛性は50%向上している。サスペンションも新しくなり、強化された鍛造スチール製サスペンションアームと鋳鉄製ナックル、再調整されたフロントのマクファーソンストラット、全く新しいマルチリンク式リアサスペンションを採用している。可変ステアリング比を変更して素早い反応のためにステアリングを改善している。ホンダは、この変更により、街中ではよりシャープなハンドリングと俊敏性が得られ、曲がりくねった道でもより楽しめるようになると述べた。新しく剛性の高いステアリングコラムと剛性の高いトーションバーにより、ステアリングフィードバックとステアリングフィールが向上した。フロントブレーキローターの大型化とキャリパーの大型化によりストッピングパワーが向上し、新しい標準ヒルディセントコントロールシステムにより、ドライバーは7%までの急な下り坂で時速2マイルから12マイルの速度を設定できる。この「パスポート」も、吸音材のレベルを上げて、より静かになる可能性がかなり高い。新しい「パスポート」はホイールベースが長くなり、2.75インチ伸びて113.8インチ (「パイロット」と同じ) になった。前後トラックの幅広化によりコーナリングの安定性を向上する。
「トレイルスポーツ」は「ホンダ史上最もオフロードが可能なSUV」である
「トレイルスポーツ」と「トレイルスポーツ エリート」のトリムレベルを区別し、性能をアップグレードするために、オフロード用に調整されたサスペンション、拡張された全輪駆動 (AWD) システム、スチール製スキッドプレート、ヘビーデューティリカバリーフック、特別に設計されたオールテレーンタイヤが装備されている。リカバリーフックは、車両の定格車両総重量 (GVWR) の2倍の定格があり、腐食に耐えるように粉体塗装されており、前面衝突時に破損するように設計されている。「トレイルスポーツ」モデルには、7ピンコネクタを備えた標準的なリアトレーラーヒッチも装備されている。「トレイルスポーツ」のトリムレベルには、オフロードでのロール、ピッチ、仰角も表示される。また、光沢のあるブラックのグリルとエクステリアトリム、オレンジ色のデイタイムランニングランプ (DRL)、メタリックシルバーのフロントとリアのスキッドガーニッシュ、「トレイルスポーツ」バッジも装備される。フロントフェイシャは「トレイルスポーツ」トリム専用で、LEDフォグランプが標準装備され、オフロードプロテクションのためにフェイシャの高い位置に取り付けられている。「トレイルスポーツ」モデルには、Generalタイヤの275/60R18サイズのGeneral Grabberオールテレーンタイヤを採用した、濃い色の仕上げの18インチホイールが用意されている。すべての「パスポート」モデルは、最低地上高(8.3インチ)を増やし、フロントオーバーハングを短くしてアプローチアングル(23.0度)を拡大したほか、トレイルを保護するリアフェイシアに排気チップを隠している。「トレイルスポーツ エリート」には、「TrailWatch」と呼ばれる標準的なオフロードカメラシステムも搭載されている。TrailWatchは4つのカメラビュー(フロント、リア、サイド、360)を提供し、タイヤの位置をグラフィック表示する。トレイルモードでは、フロントビューは時速15マイル以下では自動的にオンになり、時速15マイル以上ではオフになる。
「トレイルスポーツ」モデルのサスペンションは、専用のスプリングレートとダンパーバルブチューニング、最適化されたスタビライザーバーによってオフロード用にチューニングされている。オイルパン、トランスミッション、ガスタンクを覆うスチール製のスキッドプレートがある。これらのスキッドプレートは、岩に衝突する車両の全重量を支えるのに十分な強度がある。「トレイルスポーツ」モデルは、フルサイズの予備の品と一緒に注文することもできる。
設計:「Born Wild」のコンセプトにインスパイアされた

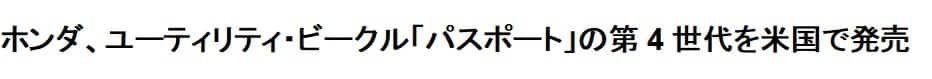
新しい「パスポート」はホンダのカリフォルニアのデザインスタジオによってデザインされたが、それはこの製品の最も重要な市場である北米にふさわしいものである。「パスポート」には、「RTL」、「トレイルスポーツ」、「トレイルスポーツ エリート」の3つのトリムレベルが用意されており、この世代では「トレイルスポーツ」の構成が大幅に増えることになる。S&P Global Mobilityの米国ライトビークル登録データによると、2024年1月~9月の「パスポート」登録台数に占める「トレイルスポーツ」の割合は32%で、2023年通年とほぼ同じである。これらの期間のテイクレートの一貫性は、次世代の「トレイルスポーツ」のテイクレートが需要ではなく可用性によって制限されていたことを示唆している。
「Born Wild」のグランドコンセプトは「「パスポート」が提供する頑丈な態度と冒険能力を設定する野心的な価値観」とホンダは語った。これは、肩幅の広い逞しい外観を意味し、その拡張された能力と自信を伝えるとともに、兄弟である「パイロット」とは明らかに異なる、より攻撃的な外観を取る。より堅牢なCピラー、より強固なルーフレール、ブラックアウトされたカーゴベイがある。標準の「パスポート」と「トレイルスポーツ」には新しいシグネチャーDRLが搭載されているが、「トレイルスポーツ」バージョンにはオレンジ色のライトが搭載されている。すべての「パスポート」には、フレアフェンダー、ワイドトラック、18インチのホイールと31インチのタイヤが装備されている。ダッシュボードとアクスルの比率を長くしてよりスポーティなデザインにし、ルーフスポイラー、新しいLEDテールランプ、リアルーフにはマットブラック仕上げを採用した。一般的なふかひれ型ルーフアンテナの代わりに、アンテナは助手席側のリアガラスに統合されている。RTLのトリムレベルは、ブラックのトリムとグリル、マットブラックのロッカートリムとルーフスポイラー、シルバーのスキッドガーニッシュがフロントとリアに装備されているが、「トレイルスポーツ」のオールテレーンタイヤではなくオールシーズンタイヤが装着される。

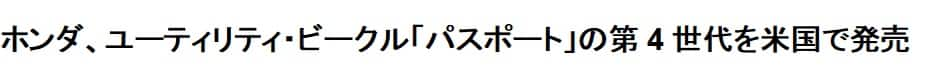
インテリアは全く新しいキャビンだが、ここで3列シートの「パイロット」とこの車両の関連性がより明確になる。ホンダはトリム仕上げやアクセントで2つを区別しているが、基本的なレイアウトは引き継がれている。ホイールベースが長くなったことで、「パスポート」のカーゴスペースは広くなった。2023年モデルイヤー「パイロット」に搭載された、車体を安定させるパワーを調節できる暖房付きシートを採用し、ホイールベースが長くなったことで、2列目乗客の足元のスペースが現行モデルより1.3インチ広くなった。「RTL」トリムには革のふちどりが施された内装とパワーテールゲートが標準装備され、「トレイルスポーツ」には掃除しやすい合成皮革の内装とスライド式パノラマサンルーフが採用されている。「トレイルスポーツ」のロゴとオレンジ色のコントラストステッチも、「RTL」と「トレイルスポーツ」を区別するのに役立っている。「トレイルスポーツ エリート」には、穴の開いたレザーシート、通気性の高いフロントシート、暖房付きステアリングホイール、リアクライムコントロール、リアドアシェード、アンビエント照明の強化、新しいインテリアに合わせた12スピーカーのBoseオーディオシステムが搭載されている。ホンダは室内に小さなスペースを増やし、広いカーゴには前輪を外したフルサイズのマウンテンバイク2台またはフルサイズのゴルフバッグを収納できるようになった。「パスポート」には10.2インチのデジタル楽器ディスプレイと12.3インチのセンタースタックスクリーンが標準装備されている。ホンダの最新のコネクティビティソフトウェア、Googleのビルトイン、Apple CarPlayとAndroid Autoに対応したワイヤレス、5G-LTE WiFiホットスポット、そしてQiワイヤレス15W充電器を搭載している。ホンダは、「Googleアシスタント」「Googleマップ」「Google Play」アプリなど、グーグルに組み込まれている機能を利用するための無料の3年間無制限データプランを所有者に提供している。センターコンソールの前には、標準の60W 3.0A USB-Cポートが2つある;「トレイルスポーツ」モデルは、センターコンソールとカーゴエリアに110ボルトの電源コンセントを追加した。
「パスポート」には「パイロット」と同じ285馬力のDOHC 3.5リッターV6エンジン、10速オートマチックトランスミッションが搭載されている。オールアルミニウム製のV6は、よりコンパクトなロッカーアームと油圧式ラッシュアジャスターデザインにより薄型シリンダーヘッドを実現し、高タンブルポートと狭い35度のバルブアングルを備えている。カムシャフトベアリングキャップもバルブカバーに直接組み込まれている。エンジンは引き続き可変シリンダー管理を使用する。このモデルは電動化されておらず、大型の「パイロット」にも当てはまる。「パスポート」には、「パイロット」で発売されたホンダの第2世代i-VTM4 AWDシステムも採用されている。より強力なリアドライブユニットは、40%のトルクを処理し、30%の高速応答を提供する。最大70%のトルクをリアアクスルに送ることができ、そのトルクの100%を右または左の後輪に送ることができる。「パイロット」と同様に、オフロード性能を最適化する新しい「トレイル」モードなど、より多くのドライブモードが用意されている。牽引モードも「パスポート」の新機能で、5,000ポンドの牽引能力を利用できる。
先進運転支援機能「Honda Sensing」は、視野角90度の新型カメラと視野角120度の広角レーダーにより、それぞれ40度と70度拡大した。死角情報もレーダーの射程距離を伸ばした。「パスポート」は、交通渋滞支援や交通標識の認識も標準にしている。ホンダによると、アダプティブクルーズコントロールとレーンキーピングアシストは、より自然な反応をするという。
見通しと影響
ホンダは、特に「トレイルスポーツ」トリムの「パスポート」を、同社のSUVラインアップにおける「HALOビークル」として位置づけている。3列ではなく2列であるが、ファミリー向けの「パイロット」よりも価格は高い。2026モデルイヤーの価格は公表されていないが、ホンダは4万米ドル半ばからとしている。ホンダは2021年にサブブランド「トレイルスポーツ」を初めて発表したが、最初の製品は実質的な変更よりも視覚的な変更が多かった (米国:2021年9月6日:ホンダ、堅牢なトラックのサブブランド「トレイルスポーツ」を発表参照)。「トレイルスポーツ」の重要性と「パスポート」に対する姿勢の変化は、ホンダが詳細を発表する前にオフロードレースでこの車を公開したことで明らかになった (米国:2024年10月14日:ホンダ、米国オフロード競技で「2026年型パスポート トレイルスポーツ」を初登場させる参照) 。
ホンダの「パスポート」は、トヨタの全く新しい「4ランナー」とほぼ同時期に発売されるが、ユニボディの「パスポート」よりも機能的で大胆であることは間違いない。アドベンチャースピリットに身をゆだねることで、「パイロット」のファミリー志向とコンパクトなCR-Vの都会的な雰囲気を補完している。もちろん、ホンダは現在、ユーティリティセグメントにおける電気自動車 (BEV) のニーズに対応するための「プロローグ」を提供している。2024年の数ヶ月間、「プロローグ」は「パスポート」よりも高価になったが、「プロローグ」は「パスポート」よりも売れた。こうした市場パフォーマンスの一部は、ホンダの典型的なモデルチェンジの慎重な管理によってもたらされたのかもしれない;最新の「パスポート」が完全に利用可能になった後も、この状態が続くかどうかは不明である。
販売するユーティリティ・ビークルのラインナップが充実していることと、ショールームの拡大により「パスポート」の販売台数が減少する可能性があることから、ブランドは「パスポート」のラインナップをより集中させた。さらに、「パスポート」の付属品に新たに焦点を当てたことは、大きな変化である (米国:2024年10月31日:SEMA 2024:フォードとホンダ、付属品事業を拡大参照) 。付属品事業を創設することで、顧客は幅広いコンテンツを指定し続けることができる。付属品の多くはディーラーが設置することが予想されるため、Hホンダの工場が複雑になることはない;付属品部門がうまく運営されていれば、組織に利益をもたらす貢献ができる。
「RTL」は基本的に、前世代の「EX-L」と「ブラックエディション」のトリムを組み合わせ、生産を簡素化しながら、顧客が興味を持つパッケージを提供する。前世代の「パスポート」には、「ブラックエディション」「エリート」「EX-L」「トレイルスポーツ」が用意されていた。しかしながら、2024年半ばまでに「エリート」トリムレベルは生産が減少し、2023年全体の約18%と比較して、2024年1月~9月の登録の2%未満を占めている。2024年上半期の登録台数は25,000台弱で、2023年通年では約43,000台、2023年上半期は約33,000台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
マツダ、新型ガソリンエンジン「SKYACTIV-Z」を2027年に発売へ-報道
2024年11月14日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
マツダ株式会社|テクノロジー、トレンド、進化
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日刊自動車新聞によると、マツダは燃焼効率を高めたガソリンエンジン「SKYACTIV-Z」を2027年に発売する計画である。このエンジンは、2028年から欧州で施行されるユーロ7規格などの環境基準に適合する。同社はまた、プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) に電気自動車 (EV) 専用シャーシの採用を検討している。ハイブリッド車の人気が高まる中、マツダは走行性能と燃費性能を両立させたエンジンを開発し、市場のニーズに応えていく。4気筒エンジンのSkyActive-Zは、初の圧縮点火ガソリンエンジンであるSkyActive-Xの後継であり、将来的には直列6気筒構成に適合する可能性がある。また、マツダは、エンジンモデルの開発も段階的に効率化していく予定である。同社は、2025年から独自のハイブリッド車を発売する計画である。電動化戦略の最終段階である「フェーズ3」(2028~2030年) では、EV専用プラットフォームをPHEVにも適用する。このアプローチは、投資コストを削減しながらパフォーマンスを向上させることを目的としている。
重要性: 大半の自動車メーカーが内燃機関や自動車への投資を停止し、そのリソースを電動化オプションに振り向けているのに対し、マツダは異なるアプローチをとっている。この革新的な「SKYACTIV-Z」エンジンは、北米の既存の「SKYACTIV-G」エンジン、およびその他のグローバル市場の「SKYACTIV-X」エンジンの後継として設計されている。「SKYACTIV-Z」エンジンは、毎分低回転から高回転までの幅広い回転数でスーパーリーンバーン燃焼を行い、高い熱効率を実現する理論的手法である「ラムダワン燃焼」を採用している。この設計により、環境性能とドライビングダイナミクスの両方が向上する。欧州ではユーロ7規格、米国ではLEV4/Tier 4などの厳しい環境基準に適合したこのエンジンを2027年に発売する予定である。マツダは、今後も内燃機関への需要があることを認識し、性能と効率を高めていく方針である。マツダは、先進的な燃焼効率向上技術に注力することで、規制基準や消費者の好みに応え、電動化が進む業界で独自のポジションを確立していく。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、第2四半期は前年比24.7%増益を発表
2024年7月26日-Autointelligence|ヘッドライン分析-韓国
Isha Sharma, Research Analyst
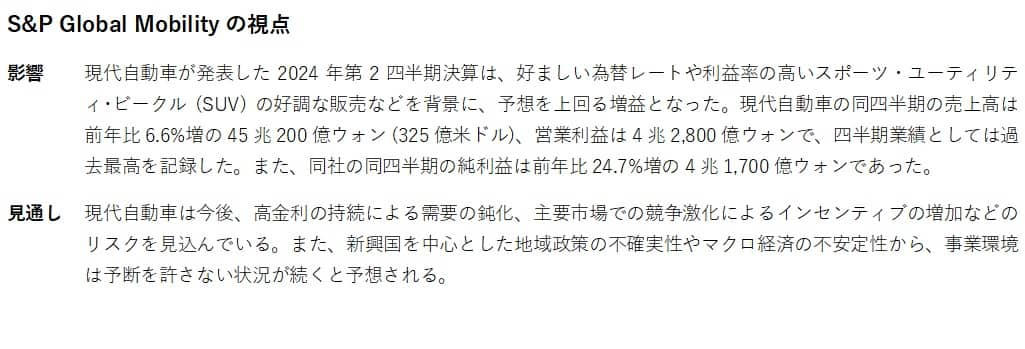
企業のプレスリリースによると、現代自動車が2024年第2四半期の決算を発表し、様々な分野でプラス成長を示したという。現代自動車の同四半期の売上は前年比6.6%増の45兆200億ウォン (325億米ドル) で、四半期売上としては過去最高を記録した。この成長は、先進国市場でのセールクミックスの改善、平均販売価格 (ASP) の改善、高付加価値車の販売増加による良好な為替環境によって牽引された。ちなみに、2023年同四半期の売上高は42兆2,300億ウォンであった。第2四半期の平均ウォン・ドル相場は1米ドル=1,371ウォンで、前年比4.3%上昇した。営業利益は前年比0.7%増の4兆2,800億ウォンで、四半期過去最高を記録した。営業利益率は9.5%であった。非支配持分を含む純利益は前年比24.7%増の4兆1,700億ウォンであった。
売上原価率は、原材料費の減少により、前年同期比0.5ポイント低下の78.4%であった。売上高に対する販売管理費比率は、人件費の増加により前年同期比1.1ポイント増の12.1%であった。現代自動車の関係者は、「高金利の継続による需要低迷や主要市場での競争激化によるインセンティブの増加傾向など不透明な事業環境が続く中、当社は高付加価値車を中心とした販売と為替の影響により営業利益率は9%超と安定した収益性を維持している。」と詳しく説明した。

現代自動車の2024年第2四半期の世界販売台数は1,057,168台 (卸売ベース) で、前年比0.2%減であった。一方、中国を除くグローバル販売は、北米地域が好調に推移し、前年比15.2%増の31万台となり、前年比2.2%増であった。韓国国内市場は、電気自動車 (EV) の需要鈍化や消費マインドの冷え込みにより、前年比9.6%減の185,737台であった。一方、スポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) や新型「サンタフェハイブリッド」などのハイブリッド車の販売比率は引き続き拡大した。海外では、新型「サンタフェ」や「サンタフェハイブリッド」、新型「ジェネシスGV80」など収益性の高い新車の販売が好調で、台四半期において前年比2.0%増の871,431台を販売した。同自動車メーカーは環境対応車 (商用車を含む) の世界販売台数は前年比0.2%増の192,242台、ハイブリッド車は26.4%増の122,421台で、EVは前年比24.7%減の58,950台と拮抗した。
2024年上半期の現代自動車の販売台数は2,063,934台、売上高は85兆6,700億ウォン、営業利益は7兆8,300億ウォンであった。
見通しと影響
現代自動車は、2024年第2四半期の売上高と営業利益で、四半期ベースで過去最高を記録した。売上増加の主な要因は、物量増加 (7,130億ウォン)、ミックス&インセンティブ増加 (2,030億ウォン)、為替レートの上昇 (5,720億ウォン) などで、合計して1兆3,000億ウォンになった。営業利益は、販売数量の増加1,530億ウォン、プロダクトミックスとインセンティブ効果950億ウォン、為替の追い風4,000億ウォン、財務利益1,360億ウォンなどが寄与した。このようなプラス要因が他の要素の損失7,530億ウォンを相殺した。
現代自動車は今後、高金利の持続による需要の鈍化、主要市場での競争激化によるインセンティブの増加などのリスクを見込んでいる。また、新興国を中心とした地域政策の不確実性やマクロ経済の不安定性から、事業環境は予断を許さない状況が続くと予想される。環境対応車市場と関して、現代自動車は世界電気自動車市場が一時的に低迷していることから、短期的にはハイブリッド車の需要が伸びると予想している。しかしながら、中長期的には、主要国の環境規制や環境インフラへの投資拡大を背景に、電気自動車需要がエコフレンドリーな市場の成長を牽引すると予想される。このような状況を受け、現代自動車は、電気自動車専用ブランド「IONIQ」のラインアップ拡充、「キャスパーエレクトリック」 (海外名「インスター」) のグローバル発売、ハイブリッド技術の開発とラインアップ拡充など、環境対応車の販売拡大に力を入れる計画である。同社はまた、生産・販売の最適化による売上高の最大化と、SUVや高付加価値モデルへの注力による収益性の向上を目指す。
現代自動車は今年初め、2023年通期決算を発表した際に2024年の財務ガイダンスを公表した (韓国:2024年1月26日:現代自動車、2023年の純利益は前年比53.7%増、2024年の業績見通しを発表参照) 。同自動車メーカーは、新興国市場を含むマクロ経済の不透明感や為替レートの変動、販売関連コストの増加などにより、今年の事業環境は全般的に厳しい状態が続くと予想している。しかし、2024年には世界で約424万台 (前年比0.6%増) の販売を目指し、連結売上高は前年比4%増~5%増を記録する計画である。営業利益率は、販売台数の増加、新型車のプロダクトミックスの強化、平均販売価格の上昇、コスト革新を背景に、8.0%~9.0% (2023年は9.3%) と控えめに予想している。これらの利益は、上記の事業環境の悪化要因によって相殺される。現代自動車も2024年に12兆4,000億ウォンを投資する計画で、2023年の12兆ウォンから3.3%増加する。このうち研究開発 (R&D) は4兆9,000億ウォン (前年比19.5%増)、資本的支出 (キャペックス) は5兆6,000億ウォン (前年比13.9%減)、戦略投資は1兆9,000億ウォン (前年比35.7%増) であった。今年の世界の自動車市場は様々な不確実性があるが、同自動車メーカーはEV専用ブランド「IONIQ」の世界的な認知度を高めるとともに、ハイブリッド車のラインアップをさらに強化することで、電気自動車の販売を拡大する計画である。また、SUVのラインアップと「ジェネシス」のプレミアムモデルで市場シェアを拡大しながら、販売と収益性を最適化する予定である。
S&P Global Mobilityは、2024年の現代自動車ブランドの世界販売台数が前年比2.6%減の約371万台になると予想している。「ジェネシス」ブランドは今年、前年比6.2%増の約229,223台の販売を見込んでいる。当社の軽自動車販売予測には、乗用車と小型商用車が含まれている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ、生産能力最適化の一環として広州工場を閉鎖へー報道
2024年7月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土)
Abby Chun Tu, Principal Research Analyst
ロイターがホンダの広報担当者の話として報じたところによると、ホンダは販売減少に対応するため、中国の自動車メーカー、広州汽車集団 (GAC) と共同で運営する工場を閉鎖するほか、東風汽車との別の合弁会社 (JV) が運営する別の工場での車両生産も停止する予定である。広州にあるGACホンダJVの工場の一つが10月に閉鎖される予定である。東風ホンダJVの生産停止の影響を受けるのは、年間生産能力24万台の拠点である。中国での同社の年間生産能力は149万台から120万台に縮小すると広報担当者は述べた。同社は広州汽車、東風汽車との合弁で現在建設中の二つのEV工場で生産を開始し、最大144万台を生産する計画である。同社は、両新工場での年内の生産開始を目指している。
重要性: ホンダは合弁工場の減産や人員削減、自動車輸出事業の拡大などを通じて、中国事業の最適化を目指している。また、同日本自動車メーカーは中国で新エネルギー車 (NEV) の販売を拡大するため、広州汽車、東風汽車とそれぞれEVモデルの開発計画に取り組んでいる。同日本自動車メーカーは、電気自動車 (EV) 市場への移行と小型車・中型車市場での中国自動車メーカーの台頭で打撃を受けている。小型・中型車セグメントは、「アコード」、「CR-V」、「ヴェゼル」などホンダの内燃エンジン (ICE) モデルの主要な販売セグメントである。ホンダの中国両社の合弁会社は、2024年後半にホンダのEV「Yeシリーズ」の生産を開始し、消費者を引き付けることを目指している。ホンダの最新の販売報告によると、6月の中国販売台数は前年比39%減の68,966台であった。2024年上半期の中国販売台数は前年比22%減の415,906台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
いすゞ、GVW15メトリックトン超の新型車発売
2024年7月24日-Autointelligence|ヘッドライン分析–日本
Nitin Budhiraja, Sr.Analyst – Automotive
いすゞ自動車はこのほど、中型トラックラインアップ「FORWARD (日本国外Fシリーズ) 」に新型車を投入した。これらの新モデルは、車両総重量 (GVW) は15メトリックトン(16メトリックトン、20メトリックトン及び22メトリックトン)を超え、6.7リットル直列6気筒ディーゼルエンジンDB6Aを搭載している。カミンズと共同開発したDB6Aエンジンは、最高出力220kW (300ps)、最大トルク1,081ニュートンメートル(N.m) または110 kgf-mを発揮する。このエンジンの特筆すべき特徴は、従来の6気筒エンジンよりも軽量であることである。いすゞはまた、シャシーのフレームも改良し、プラットフォームの基本構造を海外モデルと統一した。ホイールベースを変更し、重量配分の最適化と高い積載能力を実現した。また、DB6Aエンジン搭載車では、いすゞの商用車の運用をサポートするいすゞ独自のコネクテッドソリューションサービス「PREISM」を利用できる。
重要性: シリーズのメインモデル (2DG-FVZ26U4) は、全長9,980mm、全幅2,480mm、全高2,880mmで、最大積載量は11,900kgである。このモデルは定員2人で、9速オートメーテッドマニュアルトランスミッション (AMT) を搭載している。また、いすゞは先日発表した新中期経営計画「ISUZU Transformation-Growth to 2030 (IX) 」において、2030年の商用モビリティソリューションカンパニーへの飛躍を目指している。中核事業である小型商用車 (LCV) と商用車 (CV) の販売に加え、同計画では将来の成長に向けて3つの主要分野に注力していく:自動運転車 (AV) ソリューション、コネクテッドサービス、カーボンニュートラルソリューション。既存事業の強化を図りつつ、これらの領域を優先させることで、2031年度までに売上高6兆円 (388億米ドル)、営業利益率10%以上を目指す。このうち、LCV・CVの売上高は5兆円、3大成長領域の売上高は1兆円である(日本:2024年4月3日:いすゞ、新中期経営計画を発表「ISUZU Transformation - Growth to 2030 (IX)」参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ「オデッセイ」、米国市場向けに2025年モデルの一新でさらなる技術を提供
2024年7月22日-Autointelligence|ヘッドライン分析-米国
Stephanie Brinley, Associate Director
ホンダは2025年モデルのホンダ「オデッセイ」を、外装のマイナーチェンジ、利用可能性と標準技術の拡充、パワートレインのキャリーオーバーで一新した。米国での販売は2024年7月23日からである。「オデッセイ」は、新しいグリル、アップデートされたフロントとリアのフレーム、新しいホイールを手に入れた。フロントの鼻隠しは、黒いフォグライトの周囲が大きくなると、より攻撃的になる;リアバンパーには2代目「アキュラNSX」と同じ垂直反射板を採用している。ほとんどの技術は引き継がれているが、新しい7インチのデジタル楽器ディスプレイが標準装備され、より高速なプロセッサを搭載した9インチのタッチスクリーンが搭載され、背面のエンターテインメントシステムにはより大きな12.8インチの高解像度スクリーンが搭載されている。2025年モデルでは、スマートフォンのワイヤレス充電、スマートフォンのワイヤレス接続、そしてより多くのUSB-Cポートも標準装備されている。EXトリムレベルを廃止し、本革シートのEX-Lを標準車とする。すべてのオデッセイには、フレキシブルな2列目シート「マジックスライド」と後部座席リマインダーシステムが付いている。Sport Lは、テールライトとホイールをブラックアウトした外観に加え、グリル、ヘッドライトトリム、フォグライトサラウンド、ドアミラー、Bピラー、Cピラー、テールライトトリムなど、より光沢のあるブラックのエクステリアトリムで大きく差別化されている。内装にはブラックレザーとレッドのコントラストステッチを使用している。ただし、標準ナビゲーション、「CabinWatch」リアシートカメラビューシステム、アップデートされたリアエンターテインメントシステムを手に入れるには、ツーリングトリムにステップアップする必要がある。オデッセイは出力280馬力のV6と10速オートマチックトランスミッションを組み合わせただけで、最新モデルイヤーでも変更はない。
重要性:ホンダは2024年1月のビジネスブリーフィングで、ミニバンのアップデートが予定されていることを示唆していた (米国:2024年1月19日:ホンダ、米国事業の最新情報を発表、アキュラ小型CUVの計画を確認参照) 。ユーティリティービークルの人気と3列シートオプションの増加に伴い、ミニバンは人気を失い続けているが、一般的には家族や物を移動するのに最も効率的なソリューションであることに変わりはない。2017年の米国のミニバン販売台数は約485,000台;2023年には台数わずか305,000台であった。セグメント規模は小さいが、30万台数以上を保有すると予想されており、エントリー数は他のセグメントよりも少ない。2024年後半には、初の電気自動車ミニバン「Volkswagen ID Buzz」が米国に登場する。ホンダの現行の「オデッセイ」は伝統的なパワートレインを踏襲しているが、トヨタの「シエナ」はすべてハイブリッドに移行し、「クライスラーパシフィカ」はプラグインハイブリッドのオプションを提供している。起亜自動車のカーニバルは2025年モデルにもハイブリッドオプションを追加した。クライスラーは引き続きこのセグメントをリードし、「パシフィカ」とフリート志向、バリュープロポジションを伴う「ボイジャー」の両方を提供する。しかしながら、ホンダの「オデッセイ」は毎年、このセグメントで2番目によく売れている車である。セグメントと立ち位置のための合理的な販売で、操作性の分野に焦点を当てた一新した活動への適度な投資によって、現行世代は2018モデルイヤーに至った (米国:2017年5月15日:ホンダ「オデッセイ」、より巧みな2列目シート、2018年モデルイヤーにさらなる技術を手に入れる参照)。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
上海汽車とVW、中国でPHEV・BEV発売へ技術協力協定
2024年6月28日
S&P Global Mobilityの視点
影響
フォルクスワーゲン(VW)はここ数カ月、中国での競争が高まる中、製品投入を加速させるため、中国のパートナーとの提携を強化している。VWブランドの全ての新型BEVは、VW安徽 (VW Anhui)、JACとの合弁会社 (JV)、上汽フォルクスワーゲンJVが導入する。このドイツの自動車メーカーはまた、Xpeng Motorと2つの新製品を開発しており、Xpengの電気自動車アーキテクチャを活用する予定である。
見通し
S&P Global Mobilityによると、VWグループのBEVとPHEVを合わせた中国での生産台数は、数年以内に2023年の23万台弱から2026年には872,000台超に著しく増加する見通しである。
上海汽車の声明によると、フォルクスワーゲン (VW) グループ、上海汽車集団、上汽フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲンチャイナテクノロジーカンパニー (VCTC) は、中国における新エネルギー車 (NEV) 技術開発での協力を推進するいくつかの協定に調印した。
両自動車メーカーは、両社の技術ノウハウを合併会社に提供することで、上汽VW合併会社(JV)を引き続き強化していく予定である。同JVは、中国ではプラグインハイブリッド車 (PHEV) 3車種と電気自動車 (BEV) 2車種の計5車種のNEVを開発することを計画している。これらの新製品は2026年から市場に投入される予定である。上海汽車のチェン・ホン社長によると、同社がVWとの提携を深めたことは、自動車業界における中国の役割が「追随者」から「主導者」へと変化していることを明確に示した。同氏のコメントは、上汽VWが中国でVWの製品ラインアップを充実させるために計画している新型NEVの開発でSAICが主導的な役割を果たすことを示唆している。
上海汽車とVWブランドのアウディは5月、新たなデジタルプラットフォーム「Advanced Digitalized Platform」の開発を中国で開始した。この新しいアーキテクチャを採用したアウディの最初のモデルは、2025年に中国市場に投入される予定である。
見通しと影響
VWはここ数カ月、中国での競争が高まる中製品投入を加速させるため、中国のパートナーとの提携を強化している。VWブランドの全ての新型BEVは、VW安徽、JACとの合弁会社、上汽VW合弁会社が導入する。このドイツの自動車メーカーはまた、Xpeng Motorと2つの新製品を開発しており、Xpengの電気自動車アーキテクチャを活用する予定である。中国汽車工業協会 (CAAM) からのデータによると、VWブランドの5月の販売台数は前年比21%減の135,009台であった。アウディの5月の販売台数も前年比6%減の49,507台であった。中国で急成長しているPHEV市場で、VWグループのプレゼンスが弱かったことが主因である。S&P Global Mobilityの軽自動車販売データによると、2023年のBEVブランドの販売ランキングで中国ブランドは8位を占め、中国以外のOEMブランドはテスラ、上汽通用五菱汽車、VWの3社だけであった。PHEV市場では、2023年の販売台数上位5位は中国ブランドで、BYDのシェアは50%を超えている一方、航続距離延長型EV市場では、日産が「e-Power」モデルを展開する唯一のグローバルな自動車メーカーとなっている。
VWが上海汽車と技術契約を締結したことは、上海汽車とVWの合併会社の発展に新たな一章を刻むものであり、上海汽車は中国における新しい電気自動車モデルの開発においてより重要な役割を果たすことになると思われる。上汽VWの賈健旭総経理は4月の北京モーターショーで、VWがスマートカー技術の導入で中国自動車メーカーに後れを取っていることを認めた。同氏は、航続距離の長いプラグインハイブリッド車や新しい航続距離延長型電気自動車を市場に投入し、NEVのラインアップを拡充する方針を確認した。これらの新モデルは、上汽集団の技術力を活かしたEVアーキテクチャで開発される。S&P Global Mobilityによると、VWグループのBEVとPHEVを合わせた中国での生産台数は、数年以内に2023年の23万台弱から2026年には872,000台超に著しく増加する見通しである。VWグループの中国でのPHEV生産は、2023年には32,000台に満たなかったが、2026年には新型車の追加により18万台に達する見通しである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、韓国全州工場をFCEVハブに転換ー報道
2024年6月25日
韓國経済新聞が関係筋の話として伝えたところによると、現代自動車は全州の商用車 (CV) 工場を水素燃料バスやトラックの生産拠点に転換する計画である。現代自動車のイ・ドンソク社長兼国内生産責任者は最近、同社の労働組合幹部らとの会議で同社の計画を明らかにした。新しい戦略下において、全州工場では、現代自動車の水素自動車「エクシエント」をベースにした自動車輸送トラック、冷蔵トラック、燃料電池トラクターなどを生産する計画だと同報道は付け加えた。また、同工場は2027年までに新型の水素燃料高速バスや低床首都圏シャトルバスの開発・生産を行う予定である。
重要性: 全州工場は現在、電気バス、中型トラック、水素燃料で走る通勤車を生産している。現代自動車は水素燃料電池車 (FCEV) に力を入れることで、現在40%程度の工場稼働率を引き上げる方針であると報道は付け加えた。この動きは、低価格の電気バスでの中国の優位性とトラック市場での欧州ブランドの強い存在感による競争の激化に対応するものである。補助金制度を通じて国内生産を支援する努力にもかかわらず、中国の電気バスは2023年も韓国のバスを上回った。それにもかかわらず、2023年6月、現代自動車は環境部、ソウル市、SK E&S、Tマップ・モビリティとの間で、2026年までに低床・高床の水素バス1,300台を供給する契約を締結した (韓国:2023年6月8日:現代自動車、2026年までソウルに水素バス1,300台を供給する契約を締結参照) 。2024年初めには、現代自動車が今年、水素バスの生産を600%増やす計画だと同様の報道が伝えた (韓国:2024年4月15日:現代自動車、今年中に水素バスの生産を拡大へー報道参照) 。また、現代自動車は6月初めには現代モービスの水素燃料電池事業の買収に成功した (韓国:2024年6月10日:現代自動車、水素燃料電池事業を統合参照) 。今回の買収により、これまで分離していた水素燃料電池事業の研究開発 (R&D) 部門と生産部門を現代自動車に統合し、技術競争力と生産品質の向上を図る。S&P Global Mobilityのデータによると、現代自動車全州バス工場の2023年の生産台数は、前年比10%減の23,346台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、EV生産にギガキャスティング手法採用へ
2024年5月31日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
Jamal Amir, Research Analyst
日産自動車はテスラに続き、電気自動車 (EV) の生産にギガキャスティング方式を導入する計画である、とAutomotive Newsは報じている。ギガキャスティングは、EVモデルの自動車の部品数やコスト、全重量を減らすための先進的な製造技術である。大型アルミ部品のギガキャスト化により、日産はEV部品のコストを10%、重量を20%程度の削減を目指す。これらの改良は、2027年から発売される日産の新世代モジュラーEVに搭載される予定である。これらの新しい生産技術は、約30%の総コスト削減につながると同自動車メーカーは述べた。
重要性: EV生産にギガキャスティングを活用するという日産の決定は、ボルボ・カーズ、トヨタ、フォード、現代自動車といった他の自動車メーカーによる同様の計画と時を同じくしている。ギガキャスティングでは、最大100個の部品で構成される大きなアンダーボディ・ユニットを生産する。これらの部品はアルミ鋳造によって1つの下部ユニットに統合することができ、大型のギガプレスを必要とする。日産は6,000トンのプレスを使って次世代EV用のアルミ鋳造ユニットを製造する計画である、と報道は強調している。日産のモジュール設計・製造アプローチは、開発コストを50%削減し、トリム部品を最大70%削減するなど、大幅なコスト削減が見込まれている。日産は、ギガキャスティング手法を活用することで、今後数年間で5つのモデルファミリのために10億米ドル近い開発コストの削減を見込んでいる。S&P Global Mobilityのデータによると、日産の世界の電気自動車生産台数は2023年の135,000台から2030年には約892,000台に急増する見通しである。当社の軽車両データには、乗用車と小型商用車が含まれている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ジェネシス、初のハイブリッドモデルを2026年に量産へ-報道
2024年5月31日-Autointelligence|ヘッドライン分析-韓国
Isha Sharma, Research Analyst
現代自動車がジェネシス自動車メーカーで初のハイブリッド車を2026年に発売すると、毎日経済新聞が消息筋の話として報じている。JKaと名付けられたこのプロジェクトには、北米市場向けのスポーツ・ユティリティ・ビークル (SUV) GV70のハイブリッドバージョンの開発が含まれている。このモデルは、バッテリーとプラグインEVの要素を組み合わせた航続距離延長型電気自動車 (EREV) システムを採用する予定である。また、航続距離を伸ばすためのレンジエクステンダーも備えている。ハイブリッド「GV70」は、米ジョージア州にある現代自動車グループのメタプラントアメリカ (HMGMA) 工場で生産される予定である。
重要性: 「GV70」は現代自動車モデルで初めてEREVシステムを採用すると報道は付け加えた。EREVはEVのサブタイプで、バッテリーEVとプラグインEVの両方の特徴を融合させたものである。主に電気モーターで動作し、航続距離を伸ばす補助動力装置であるレンジエクステンダーで補完される。レンジエクステンダー- 通常は小型の内燃機関は-発電機に電力を供給し、バッテリーとモーターに電力を供給する。これらのエクステンダーはバッテリーを充電し、バッテリーが消耗したときに航続距離を延長するため、したがって、排出ガスの発生からハイブリッド車に分類される。現代自動車がジェネシスにハイブリッドモデルを投入したのは、ハイブリッドが台頭している自動車市場の急速な進化に対応した戦略的対応である。この戦略はまた、電気GV70の既存の構造を維持し、より小さなエンジンを組み込むことによって、生産コストを削減し、プロセスの変更を制限するのに役立つ。現代自動車グループの2024年第1四半期のハイブリッド販売台数は、前年比16.6%増の約98,000台と好調であった (韓国:2024年4月25日:現代自動車の第1四半期の純利益は販売減で前年比1.3%減参照) 。同社は、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車 (BEV)、燃料電池電気自動車 (FCEV) などの電気自動車の販売台数は、前年同期比4.8%減の153,519台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
三菱自動車・日産・マツダ、最新の軽トラックを発表
2024年5月30日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
Ian Fletcher, Principal Analyst
三菱自動車が「ミニキャブトラック」の改良を発表した。発表によると、この車両は現在、5速マニュアルトランスミッションの全モデルにストップスタート機能が追加されたことで便益となり、世界統一試験サイクル (WLTC) の下で燃費が約3%向上するという。同時に、新しい安全機能も搭載した。これらには、すべてのモデルにリアパーキングセンサーとインジケータライトが含まれており、上位仕様の「G」と「みのり」のトリムレベルには、リアクロストラフィックブレーキアシストが追加されている。また、「G」トリムにはLEDヘッドランプ、オートマチックリトラクトドアミラー、新しいカラーオプションから便益となる一方で、下側仕様Mトリムレベル「みのり」のトリムレベルにはキーレスエントリー、セントラルロック、電動窓を標準装備として備えている。同車両は消費税10%込の1,103,300円から1,590,600円 の価格を設定する予定である。同時に、日産は三菱「ミニキャブトラック」の兄弟車である「NT100クリッパー」の名称を「クリッパートラック」に変更すると発表した。日産の声明によると、「クリッパートラック」は、ストップスタート、インテリジェント緊急ブレーキ、ペダル誤作動防止アシスト、後部駐車センサー、坂道発進アシストなどの独自のアップグレードの恩恵を受ける。同様に、三菱「ミニキャブ」に関連するマツダ「スクラムトラック」も同じアップデートの恩恵を受ける。
重要性: 三菱「ミニキャブ」、日産「クリッパートラック」、マツダ「スクラム」は、スズキからOEM供給を受けている。今回の発表は、他の3車種すべてのベースとなっているスズキ「キャリー」のアップデートが発表されてから1カ月後に行われた。日本の軽自動車カテゴリーにおけるこのような取り決めは珍しいことではなく、単一のOEMが単独で投資してこの種の製品を製造した場合よりも高い投資収益率、効率性、規模を達成することができる。S&P Global Mobilityによると、2023年の国内の4車両の総販売台数は70,500台で、スズキ「キャリー」はその約80%を占めた。2024年の販売台数は66,600台となり、スズキ「キャリー」のシェアは2023年を若干上回る見込みである。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
スバル、トヨタ、マツダが電動化とカーボンニュートラルに焦点を当てた新型エンジンを開発
2024年5月28日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
スバル、トヨタ、マツダは、電動化とカーボンニュートラルに向けて設計された新しいエンジンの開発を計画している。これらのエンジンは、モーター、バッテリー、その他の電気駆動ユニットと最適に統合される予定である。次世代エンジンは、個々のエンジン性能を向上させるだけでなく、電気駆動ユニットとの融合を最大化する予定である。効率的でパワフルな新型エンジンは、よりコンパクトになることで、自動車のデザインに革命をもたらす予定である。これにより、フードを低く設計することが可能となり、設計の柔軟性、空力性能、燃費性能が向上する。エンジンの開発は、より厳しい排出ガス規制への対応を優先し、化石燃料からe-fuel、バイオ燃料、液体水素などの様々な代替燃料に対応し、したがってカーボンニュートラル燃料の普及を促進する。この開発について、スバルの代表取締役社長である大崎篤氏は、「当社は電動化技術に磨きをかけるとともに、水平対向エンジンも強化し、将来的なカーボンニュートラル化を目指す。今後も、志を同じくする3社は、日本のクルマづくりにおけるサステナブル・エクセレンスを追求していく。」と述べた。また、マツダ株式会社代表取締役社長の茂籠勝弘氏は、「ロータリーエンジンは、電動化やカーボンニュートラル燃料との親和性が高く、広く社会に貢献できる技術として、共創と競争を通じて技術の開発を継続するつもりである。」と述べた。
重要性: 世界経済が汚染レベルの上昇に取り組む中で、水素とバイオマス燃料の採用は排出量を削減するための重要な解決策として浮上している。水素はクリーンな燃焼分子であるため、削減の達成が困難な部門の脱炭素化において重要な役割を果たすことができる。発電、自動車の動力源、建物の暖房などに利用でき、排出量はほとんどない。一方、植物などの有機物を原料とするバイオマス燃料は、気候変動の緩和に大きな可能性を秘めている。これらのバイオ燃料は再生可能であり、消費時に放出されるのと同じ量の二酸化炭素を成長中に吸収することができ、バランスのとれたCO2サイクルを生み出す。さらに、ますます厳しくなる排出ガスと燃費基準に対応して、世界の自動車メーカーは、e-fuelで走行できるより小さく、より効率的なエンジンの開発に力を注いでいる。これは、2050年までにカーボンニュートラル社会を実現し、温室効果ガスの排出をゼロにするという日本の目標にも合致している。今週初め、トヨタは、出光興産、ENEOS株式会社、三菱重工業と協力して、カーボンニュートラル燃料の実現と普及を模索すると発表した (日本:2024年5月27日:トヨタ、カーボンニュートラル燃料で他社3社と提携 参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、カーボンニュートラル燃料で3社と提携へ
2024年5月27日-Autointelligence|ヘッドライン分析-日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst - Automotive
トヨタ自動車は、出光興産、ENEOS株式会社、三菱重工業と協力し、カーボンニュートラル燃料の導入と普及を検討している。これらの燃料は、カーボンニュートラル社会への一歩である自動車の脱炭素化に不可欠である。供給・技術・需要面でそれぞれ大きな役割を担う四社は、2030年までに日本でのこれらの燃料の導入を目指している。同4社の焦点は、カーボンニュートラル燃料を日本の自動車市場に統合するための戦略を策定し、市場参入に必要なシステムを確立することである。また、同4社は日本のエネルギー安全保障などを考慮し、生産可能性を評価する予定である。
重要性: これは、2050年までにカーボンニュートラル社会を実現し、温室効果ガスの排出をゼロにするという日本の目標と一致している。この新しい政策の第一の重点は、発電における化石燃料への依存を減らすことである。カーボンニュートラル燃料とは、製品のライフサイクルを通じてCO2排出量を最小化する燃料のことである。この用語には、水素とCO2を用いて製造される合成燃料 (e-fuel) と、光合成によってCO2を隔離する植物などの原料から得られるバイオ燃料が含まれる。液体カーボンニュートラル燃料は、そのエネルギー貯蔵および輸送能力により特に有益であり、輸送に理想的である。世界経済が深刻化する汚染レベルを減らそうと努力する中、水素とバイオマス燃料の使用は間違いなく排出量の削減に貢献するだろう。それにもかかわらず、この技術はまだ発展途上であり、大きな影響を与えるためには、政府からの財政的および規制的支援だけでなく、重要な研究開発が必要である。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
起亜自動車、米ジョージア工場で電気スポーツ・ユーティリティ・ビークル「2025 EV9」の組み立てを開始
2024年5月31日|ニュース|沿革
Amit Panday, Senior Research Analyst
EV9は、起亜の「テルライド」、「ソレント」、「スポーティージ」などのSUVに加わることになり、これらのSUVは現在、起亜自動車の工場で現地において組み立てられている
韓国の自動車メーカー起亜自動車が、完全電動の3列シートスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)、「起亜EV9」の組み立てを開始した、と同社は5月30日に発表した。
「2025 EV9」モデルは、現代自動車グループ傘下の起亜自動車が米国で現地で組立した初の販売用電気自動車 (BEV) である。同行事には、起亜ノース・アメリカと起亜アメリカのショーン・ユン社長兼CEO;起亜ジョージアのジェイムズ・ワトソン生産副社長;およびジョージア州知事ブライアン・ケンプ氏をはじめとする数人の代議員が出席したように、起亜の米ジョージア州ウェストポイント組立工場で電気自動車モデルが組み立てられている。
「EV9」は、起亜の「テルライド」、「ソレント」、「スポーティージ」などのSUVに加わることになり、これらのSUVは現在、起亜自動車の工場で現地で組み立てられている。同社によると、「EV9 BEV」のジョージア工場での現地組み立ては、2億ドル以上を投じた生産能力拡大の結果であり、同工場で約200人の雇用を創出した。これらの投資は、既存の組立ラインを柔軟に活用し、EVと内燃機関車の両方を同工場で生産できるようにするために行われた。
ユン社長は「EV9」の米国現地組立について、「「起亜EV9」のジョージアでの発売は、起亜の米国市場とジョージア州へのコミットメントを示す最新の事例である。起亜はプランSを通じて、今後数年間、eモビリティ分野のリーダーになる準備をしている。世界カー・オブ・ザ・イヤー、世界EV・オブ・ザ・イヤー、北米ユーティリティ・ビークル・オブ・ザ・イヤーなどの栄誉ある賞を獲得した「EV9」は、起亜ジョージアのチームメンバーと素晴らしい関係を築き、受賞歴のある世界的に有名な製品を組み立ててきた彼ら/彼女らの実績が物語っている。」と述べた。
また、起亜ジョージアのスチュアート・カウンテス社長は、「起亜ジョージアチームは、挑戦を機会に変えるというマインドを持ち続け、相変わらず力強く走っている。当社は起亜のフラッグシップEVを当社の工場に加え、起亜ジョージアの新時代に入り、ここウェストポイントで世界最高の車を組み立てるというこれまでと同じ品質重視の姿勢で臨めることに興奮している」と述べた。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
タタ、インドでJLR EVの輸入を計画-報道
2024年4月19日-Autointelligence|ヘッドライン分析-インド
Jamal Amir, Research Analyst
タタ・モーターズは、現地に製造拠点を設立する意思のある企業に対して輸入税を大幅に軽減するというインド政府の新政策の下、JLRの電気自動車 (EV) をインドに輸入することを計画していると伝えられているとET Autoが報じている。この動きが実現すれば、タタはEVの利用拡大を目的としたこの政策を採用する最初の現地自動車メーカーとなる。タタの広報担当者は同自動車メーカーが述べたことは憶測だとしてコメントを控えた。また、米国のEVメーカーテスラもインドからの車の輸入を開始し、同国への投資を行うと予想されていることも注目に値する (インド:2024年4月4日:テスラ、EV工場をインドに建設へ―報道参照) 。
重要性: インド政府は先月、EVの輸入関税を大幅に引き下げると発表した。新しいEV政策の下では、原価・保険・輸送費 (CIF) 価格が35,000米ドル以上の輸入EVに対して、五年間継続して、輸入関税を100%からわずか15%に引き下げる。ただし、この削減にはいくつかの条件がある: 例えば、各メーカーは最低5億米ドル以上を投資して三年間以内に現地生産工場を設置し、EVの商業生産を開始し、三年目までに国内付加価値 (DVA) 25%、五年内に少なくとも50%を達成することなどが求められる (インド:2024年3月18日:インド政府、EVの条件付き輸入関税引き下げを発表参照) 。インド政府は、さまざまな自動車業界の代表者と協議しながら、政策の枠組みを積極的にまとめている。タタが当初、国内業界を保護するために関税を引き下げないようインド政府に圧力をかけていたことは興味深い。しかしながら、同自動車メーカーは現在、EV政策の下でインセンティブを申請することを検討している。この戦略の一環として、タタは英国からJLRのEVを輸入することを計画していないだけでなく、インドのタミル・ナードゥ州に建設予定の10億米ドル規模の工場でJLR車を生産する計画である(インド:2024年4月4日:タタ・モーターズ、インドのタミル・ナードゥ州に新工場を計画参照) 。タタはインド内外のEV市場で足場を拡大するとともに、EVをより入手しやすくすることを目指している。同自動車メーカーはインドの電気自動車市場では70%以上のシェアを占め、MGモーターやマヒンドラ&マヒンドラ (M&M) と競合している。S&P Global Mobilityのデータによると、タタ・グループの2023年のインドにおけるEV乗用車生産台数は約76,000台で、2022年の約38,000台から増加した。これは、2025年には約171,000台、2030年には約375,000台に拡大するト予想されている。現在の当社のデータでは、インドのプネ工場でランドローバーEVの生産を2026年から、ジャガーEVの生産を2028年からマハラシュトラ州で開始する。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
テスラとタタ・エレクトロニクス、半導体分野で戦略的提携
2024年4月17日-Autointelligence|ヘッドライン分析-インド
Jamal Amir, Research Analyst
テスラは、同社のグローバル事業で使用する半導体チップを調達するため、タタ・エレクトロニクスと戦略的合意に達したとビジネストゥディが報じている。提携に詳しい関係者が詳細を明らかにしたが、両社とも正式にコメントしていないため、合意の具体的な条件や金額は明らかにされていない。この動きは、サプライチェーンを多様化し、インドでの基盤を強化するテスラの計画の一環と見られている。
重要性: タタ・グループの半導体製造分野の先頭に立つタタ・エレクトロニクスは、トップレベルの幹部を擁して人員を増強し、これまでにこの事業で140億米ドルを投資している。同社は、ホスール、ドレラ、アッサムに半導体製造工場を建設し、事業を拡大する計画である。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者 (CEO) は近くインドを訪問し、ナレンドラ・モディ首相と会談し、インドでの電気自動車 (EV) 生産工場建設など投資の可能性について話し合うとみられている。テスラはインドにEV製造工場を建設するために20億米ドルから30億米ドルを投資する予定である (インド:2024年4月4日:テスラ、EV工場をインドに建設へ-報道参照) 。インド政府がEVの輸入関税を大幅に引き下げると発表したことを受けて、最近同EVメーカはインド市場に攻め込んでいる。新しいEV政策の下では、原価・保険・輸送費 (CIF) 価格が35,000米ドル以上の輸入EVに対して、五年間継続して、輸入関税を100%からわずか15%に引き下げる。ただし、この削減にはいくつかの条件がある:例えば、中でも、各メーカーは最低5億米ドルを投資して三年間以内に現地生産工場を設置し、EVの商業生産を開始し、三年目までに国内付加価値 (DVA) 25%、五年内に少なくとも50%を達成することなどが求められる (インド:2024年3月18日:インド政府、EVの条件付き輸入関税引き下げを発表参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
BYDのオフロードブランド「方程豹」、3車種を発表; ホンダ、中国市場向けEV「Ye」を発表
2024年4月17日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土)
Abby Chun Tu, Principal Research Analyst
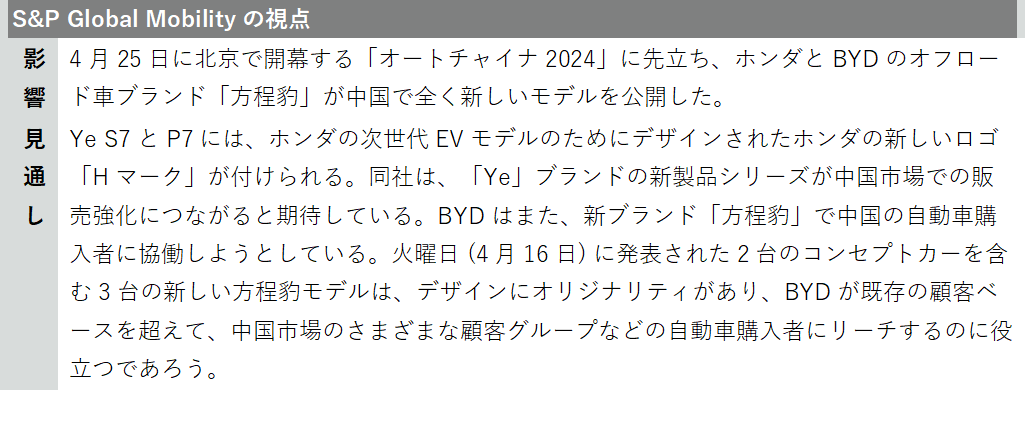
ホンダとBYDのオフロード車ブランドである方程豹は、4月25日に北京で開幕するオートチャイナ2024に先立ち、中国で全く新しいモデルを公開した。
火曜日(4月16日)、ホンダは中国市場向けに開発したこの新ブランドから全く新しいモデルと共に同社の新電気自動車(EV)ブランド、Yeブランドを販売した。「Ye」ブランドで中国市場に投入する最初のモデルは、クロスオーバー・ユティリティ・ビークル(CUV) の「P7」と「S7」である。ホンダによると、Yeブランドは2027年までに中国で合計六つの電気自動車モデルをラインナップする。ホンダはまた、この新しいモデルラインを消費者に紹介するために、Yeの今後の製品のデザインの方向性を示す「Ye GT Concept」を公開した。これらの全く新しいモデルは来週北京で開催される「オートチャイナ2024エキスポ」で披露される。
ホンダの全く新しい「Ye P7」と「Ye S7」は、同社が新たに開発したEV専用プラットフォームをベースに開発され、2種類が用意されている:1モーター後輪駆動モデルと2モーター4輪駆動モデル。いずれも「走る歓び」を追求したモデルであると同社はいう。
ホンダは2車種の内装を発表しなかったが、オートチャイナエキスポで明らかにされる可能性が高い。両EVは2024年第4四半期に市場に投入される予定である。
BYDのオフロード車ブランド、方程豹は火曜日 (4月16日) に3つの全く新しいモデルを公開した。スポーツ用多目的車 (SUV)「バオ8」、CUVのコンセプトモデル「スーパー3」、スポーツカーのコンセプトモデル「スーパー9」が、4月16日のライブストリーミングイベントでデビューした。バオ8はBYDのDMOプラットフォームで開発されたEセグメントモデルである。このモデルはオフロードSUV用に開発されたBYDのプラグインハイブリッドシステムが搭載される。中型SUV「バオ5」では、このハイブリッドシステムは、最高出力505 kW、ピークトルク760 Nmを実現した。小型のスーパー3はSUV市場の若い消費者をターゲットにしたコンセプトモデルで、スーパー9はバタフライドアを備えた2人乗りの高性能スポーツカーである。BYDは、バオ8の仕様や内部構造を明らかにしなかった。主力SUV「方程豹」は2024年に販売を開始する予定である。
見通しと影響
Ye S7とP7には、ホンダの次世代EVモデルのためにデザインされたホンダの新しいロゴ「Hマーク」が付けられる。同社は、「Ye」ブランドの新製品シリーズが中国市場での販売強化につながると期待している。中国では2027年までに、ホンダのが先にバッテリー式電気を提供した「e:N」シリーズを含め、ホンダブランドの計EV 10モデルを、中国のバッテリー式電気自動車 (BEV) の購買者に販売する予定である。これらの新モデルは、2035年までに中国での販売に占めるEVの割合を100%にするというホンダの目標を支援する。
BYDはまた、新ブランド「方程豹」で中国の自動車購入者に協働しようとしている。4月16日に発表された2台のコンセプトカーを含む3台の方程豹の新しいモデルは、BYDの下でこの若いブランドを構築するのに役立つ特有なデザイン要素で形作られている。これらの製品は、BYDが中国市場でさまざまな顧客グループに接触するのにも役立つであろう。BYDは昨年、「方程豹」ブランドを導入した際、「デンツァ」、「仰望」、「BYD」ブランドに続き、この新しいブランドが多様なブランドマトリックスに有意に加わることになると説明した。バオ 5の販売データは肯定的な市場の反応を示している。バオ 5は2023年11月の納入開始以来、顧客に2万台近くが納入された。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
現代自動車、今年から水素バスの生産を拡大-報道
2024年4月15日-Autointelligence|ヘッドライン分析-韓国
Isha Sharma, Research Analyst
現代自動車が2024年に水素バスの生産を600%増やす計画であると毎日経済新聞がこの件に詳しい者の話として報じた。バスと大型商用車の生産拠点である現代自動車の全州工場は、水素バスの年間生産能力を2023年の500台から3,000台に増やしたという。この増加能力により、現代自動車は2023年の1,500台に比べ、今年は四倍以上の水素バスを生産・販売できると見込んでいる。国土交通部の資料によると、現代自動車は2023年に約370台の水素バスを販売した。環境部は水素バスの購入補助金を1,720台に引き上げ、2023年の目標である700台の倍以上となった。政府の目標が達成されれば、現代自動車の水素バス事業の売上高は2024年に1兆ウォン (7億2370万米ドル) を超える可能性がある。
重要性: 今回の増産は、現代自動車のバス1工場の水素バス生産に焦点を当てた工場を最近整備した結果である。2023年まで、水素バスは主にバス1工場での試験運転後、バス2工場で量産されていたと報道は付け加えた。この動きは、また、2023年に中国製の電気バスの販売台数が初めて国内のものを上回ったことと時を同じくしている。2023年6月、現代自動車は環境部、ソウル市、SK E&S、Tマップ・モビリティとの間で、2026年までに低床・高床の水素バス1,300台を供給する契約を締結した (韓国:2023年6月8日:現代自動車、2026年までソウルに水素バス1,300台を供給する契約を締結参照) 。韓国政府は、輸入石油への過度な依存度を下げるために、水素関連ビジネスを韓国経済の将来の主要な成長ドライバーの一つとして育成しようとしている (韓国:2021年9月9日:韓国、e-モビリティを推進するための予算12兆韓国ウォンを発表参照) 。2022年11月、政府は民間企業四社と液体水素のサプライチェーン構築に関する合意事項の覚書 (MOU) を締結した。同自動車メーカーは現在、水素バス「エレックシティ」、燃料電池バス「ユニバース」、燃料電池トラック「エクシエント」、燃料電池車「ネッソ」を販売している(韓国:2023年6月9日:現代自動車、ネッソFCEVを韓国で発売参照) 。S&P Global Mobilityのデータによると、現代自動車全州バス工場の2023年の生産台数は、前年比27%増の8,396台であった。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
ホンダ、米EV生産の進捗状況の更新を説明
2024年4月15日-Autointelligence|ヘッドライン分析-米国
Stephanie Brinley, Associate Director
ホンダは、電気自動車 (EV) 生産を組み込むため、以前に発表した米国オハイオ州の工場の変更を行っている (米国:2023年3月15日:ホンダはEVへの道を開くため米国での生産を調整参照) 。製造開始は2025年を予定していると同社は最新情報を提供した。同社は「EVの技術と生産に関する知識と専門知識を北米の他のホンダの工場と共有する」と強調したが、変更の時期や順序に関する詳細は明らかにしなかった。最初にEVを生産するのはメアリーズビル自動車工場 (MAP) で、2025年になる予定だが、ホンダはオハイオ州にEVハブを建設中で、同州には車両とパワートレインの工場がある。ホンダはEVハブで300人を採用し、メアリーズビル工場でインテリジェントパワーユニット (IPU) の組み立てを行う300人の訓練を行う。ホンダによると、IPUケースはアンナエンジン工場 (AEP) で生産され、MAPに供給される。MAPはホンダジョイントベンチャー(JV)電池工場からバッテリーモジュールを設置しする予定である(米国:2022年10月12日ホンダ-LG JV、米国に計画された電池工場の場所を発表;ホンダ、オハイオ州に7億米ドルを投資参照)。ホンダは声明の中で、「EV Hubは、MAPとELPでのEV生産を超えて、ホンダの関係者がEV生産の知識と専門知識を開発する場所であり、今後数年間でホンダの北米の自動車生産ネットワーク全体で共有される。EV Hubは、北米および世界におけるホンダの電気自動車生産の標準となるであろう。」と述べた。 MAPでは、ホンダはEVと内燃エンジン (ICE) 製品を同じラインで生産する。MAPでの主な変更点は、2つの生産ラインを統合し、EVとICEを1つのラインで可能にするためにライン2の大部分を取り払うことである。また、車両品質領域を拡大し、ソフトウェア依存の車両機能を検証する。AEPでは、ホンダはIPUケースをメガキャストする6,000トンの高圧ダイカスト・マシンを設置する;2つにダイカストで鋳造し、摩擦撹拌溶接で溶接する。IPUケースのスペースを確保するため、AEPはエンジン部品の生産をアラバマ州の自動車工場に移した。ホンダ・イーストリバティ工場 (ELP) では、EVの生産を単一の生産ラインで行う。ホンダによると、今回の変更は、ソフトウェアに依存する機能のための車両の品質の同様の拡大と同様に、より重いEVに対応することに重点を置いている。
重要性: この更新はホンダの以前の投資発表に続くもので、進捗を再確認するものである。ゼネラルモーターズ (GM) がホンダ向けに生産するEV (アキュラZDXとホンダ・プロローグ) を除くと、ホンダの北米EV生産は、2024年3月のS&P Global Mobilityのパワートレイン予測における2030年の433,000台に達し、ホンダの北米生産台数の約37%を占める。その時点で、MAPは232,000台近くを占め、2030年のELP EV生産は172,000台弱になると予想されている。また、当社はホンダのアラバマ州リンカーン工場、メキシコのセラヤ、オハイオ州のPerformance Manufacturing Centerでも少量のEV生産を見込んでいると予測している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、欧州BEV目標を設定
2024年3月28日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-フランス-ドイツ-イタリア-スペイン-英国
Tim Urquhart, Principal Analyst
オートモーティブニュース・ヨーロッパ (ANE) の報道によると、日産は欧州市場で最も厳しい世界のバッテリー式電気自動車 (BEV) 販売目標を設定している。同社は最近、中期経営企画を発表し、CEOの内田誠氏によると、2027年3月までに売上高の 「40%以上」 をBEVにするという目標を掲げた。日産は、世界全体でのBEVの総売上を2030年までに40%に引き上げることを目指し、その時点で20%の割合を占めると予想している。
重要性: 日産の欧州でのBEV普及販売率は非常に高いように見えるが、この地域における同社の広範な企業戦略は、やや矛盾したシグナルを送っている。日産は同日、ガソリンと電気のハイブリッドシステム第3世代の「e-Power」 を欧州で発売すると発表した。これは、同社が昨年9月、2030年までに欧州での全販売を完全電動化することを目指していると述べた後である。同社は3月25日に発表した最新のグローバル戦略で、この主張を繰り返さなかった。日産は以前、欧州向けに4台の新型BEVの計画を発表していたが、発売期間も明らかにしていなかった。中期計画の目標終了日である2027年3月31日までに少なくとも3件が見込まれている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、 「The Arc」 事業計画を発表
2024年3月26日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析 -日本
Nitin Budhiraja, Sr.Analyst – Automotive
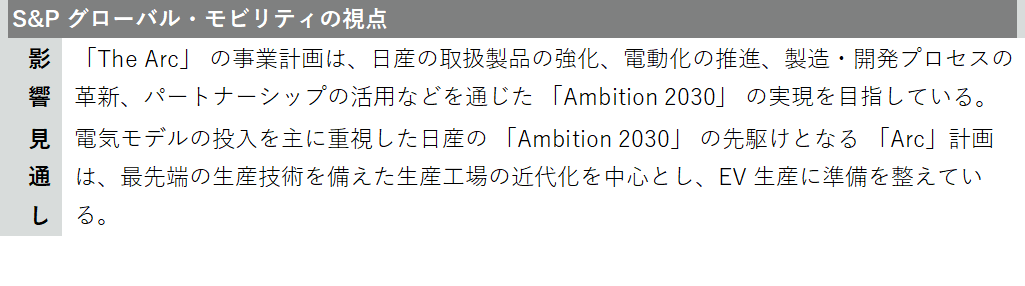
日産は、 「Ambition 2030」 ビジョンの実現に向けて、取扱製品の強化、電動化の推進、製造・開発プロセスの革新、パートナーシップの活用などを目指す新たな事業戦略 「The Arc」 を発表した。The Arcは、2020~23事業年度(FY)の日産NEXT変革計画と長期計画 「Nissan Ambition 2030」 をつなぐ役割を果たす。
この戦略は、2024~26年の中期目標と2030年までに及ぶ中長期的新たな取り組みに分けられており、製品提供の拡大、電動化の強化、革新的なエンジニアリングと製造方法の採用、新技術の統合、グローバルな売上と収益性を高めるための戦略的提携の活用に焦点を当てている。
2026年事業年度までの第一段階では、地域別戦略による販売台数の増加と、電気/ICE混合製品ポートフォリオ、主要市場の成長、財務の慎重さを背景としたEVへの早期移行に向けた準備を進める。第2段階では、戦略的パートナーシップ、EV競争力の向上、独自のイノベーション、新たな収益源の支援を受けて、EV移行を促進し、持続的な収益性の高い成長を達成することを目指している。2030年事業年度には、日産は新規事業による収益の見込みを2兆5000億円と予測している。
以下に、計画の主なアクションプランを要約する:
売上高を2023年事業年度と比較して100万台増加させ、2026事業年度末までに営業利益率6%以上を達成する。
2026事業年度までに新型30車種を発売し、そのうち16車種を電動化する。
2024年事業度から2030事業年度までに全セグメントで34電動化車種を投入する。日産は、2026事業年度までに世界のモデルミックスに占める電気自動車の割合を40%とし、2030年には60%に拡大すると見込んでいる。
日産の乗用車モデル「ICE」 の60%を2026事業年度までに更新する。
2030事業年度までに次世代EVのコストを30%削減し、EVとICE車のコストパリティを達成することで、EVの競争力を強化する。
次世代EVの大幅なコストダウンを 「ファミリー」開発で実現し、このアプローチに基づき生産を2027事業年度から開始する。
技術、製品ポートフォリオ、ソフトウェアサービスにおける日産の戦略的パートナーシップを拡大する。
配当と自社株買いによる株主総利回りを30%以上を達成する。
新規事業により2030事業年度までに2兆5000億円の追加収益の可能性を引き出す。
また、総合目標の達成に向けて、2026事業年度までの目標を含む地域戦略を策定している。南北アメリカ大陸では、同自動車メーカーは、2026事業年度までに販売台数を2023事業年度の販売台数を比較してで33万台改善し、米国での顧客体験向上のために2億米ドルを投資し、米国とカナダで7車種の新型車を発売し、米国での乗用車ラインアップの78%を練り直したいと考えている。中国では、2026事業年度までに販売台数100万台を達成するため、73%の車種を更新し、8台の新エネルギー車 (NEV) を発売する計画だ。2025年には中国からの車の輸出も開始する計画だ。日本国内市場では、2026事業年度までに新型車5車種の投入、既存の乗用車ラインナップの80%の刷新、乗用車ラインナップの70%の電動化を計画している。また、同社は、2026事業年度には2023事業年度比9万台改善の60万台の販売達成を計画している。欧州では2026事業年度までに新型車6車種を投入し、EV乗用車製品構成40%を達成する計画であり、中東では同自動車メーカーは、2026事業年度までに新型SUV 5車種を投入する計画である。インドでは、2026事業年度までに新型車3車種を投入し、約10万台を輸出する計画だ。オセアニアでは、日産は、1トンピックアップを販売し、そしてCクロスオーバーEVを投入し、同社はアフリカでは2026事業年度までに新型SUV2車種の投入とAセグメントICEの拡大を計画している。
見通しと影響
日産は、オールバッテリー駆動の 「リーフ」 でEV分野のパイオニアだったが、米国のテスラや中国のBYDなどのライバルとの競争が激しく、苦戦を強いられている。日産は最近、本田技研工業との間で自動車の電動化とインテリジェンス分野における戦略的提携の実現可能性調査を開始するための合意事項の覚書 (MOU) を締結した。実現可能性調査は、自動車用ソフトウェアプラットフォーム、EVに不可欠な部品、および補助製品を対象とする (日本:2024年3月18日ホンダと日産、自動車の電動化とインテリジェンス分野での提携を検討する合意事項の覚書を締結参照)。
Nissan's Ambition 2030計画 の先駆けを経て(日本:2023年2月27日日産、2030年と日本のEV目標を引き上げ2021年11月29日日産、EVを中心とした 「Ambition 2030」 計画を発表参照) 、電気自動車の発売を主に重要視し、the Arc計画では最先端の生産技術を備えた生産工場の近代化を中心にEV生産に対応している。計画によると、国内外の工場で日産インテリジェントファクトリーのコンセプトを採用する予定だ。2026事業年度から2030事業年度にかけて、日本の追浜工場と日産自動車九州工場、英国のサンダーランド工場、米国のキャントン工場とスマーナ工場で着手する予定だ。併せて、2025事業年度から2028事業年度にかけて、サンダーランド工場から米国のキャントン、デカード、スマーナ工場、日本の栃木、九州工場などにEV36Zero生産方式を拡大する。
日産の内田誠社長は、「the Arc計画は未来への道筋を示している。それは、当社の継続的な進歩と、変化する市場環境をナビゲートする能力を示している。この計画により、当社は価値と競争力をさらに速く推進することができる。市場の激しい変動に直面した日産は、持続的な成長と収益性を確保するために、新たな計画に基づいて断固とした行動をとっている。」 と述べた。
この計画を支援し、将来に備えるために、日産は安定した設備投資と研究開発投資の比率を維持し、電池設備投資を除いた純収益を7%から8%の間にする計画だ。同社はまた、ルノーや三菱などとの提携を活用して、技術的な相乗効果をもたらすことも計画している(日本:フランス:2023年12月7日日産自動車と三菱自動車、ルノーのアンペールへの投資計画を確認参照) 。
また、NCMリチウムイオンバッテリーの大幅な改良を行い、アリアと比較して急速充電時間を50%短縮し、エネルギー密度を50%向上させることを目指す。日産はLFP電池を日本で開発・生産し、軽自動車EV 「サクラ」 に搭載されている電池に比べて30%の低価格化を目指す。同社は、2028事業年度には、これらの強化バッテリーを搭載した新型EVの発売を予定している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、2030年までに新本社を開設へ
2024年3月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析 ー日本
Ian Fletcher, Principal Analyst
トヨタは、2030事業年度(FY)中に日本の東京に新本社を開設することで合意したと発表した。発表によると、同自動車メーカーは京浜急行電鉄との間で、品川駅西口地区の土地の一部を譲渡するとともに、 「都市開発を促進するための計画ビルの共同建設及び運営に関する」協定を締結した。同社は、モビリティサービスを中心としたトヨタの取り組みをリードする重要な拠点になると述べた。そのため、同社は「ソフトウェア開発機能やデモンストレーションに必要な設備を備え、多様なパートナーが集う協創の場として機能する」。
重要性: 新本社は、現在の文京区にある市の既存の本社に代わるものとみられる。今回の協定は、2020年に京浜急行電鉄と品川駅西口地区の開発の共同事業者として締結したことに続くものだ。現場の開発に伴う変化には、東京の品川駅と名古屋駅を40分で結び、最終的には大阪駅を67分で結ぶと予測される新しいリニア中央新幹線の開業が含まれる。新本社への投資は、日本の資本におけるトヨタの重要な拠点をこの重要な投資に近づけることになる。トヨタは「自分のモバイル端末の持ち込みを可能にするなど、多様な人材が集い、創造性を発揮できる環境を整備する」と考えている。また、 同社は「新しい働き方が実現できるよう、福祉や他の制度やインフラの導入を検討する」 としている。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
三菱商事、日本の自動運転スタートアップ 「ティアフォー」 に出資へ
2024年3月15日-自動車モビリティ|ヘッドライン分析–日本
Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst
三菱商事は、オープンソースの自動運転車(AV)技術を開発するティアフォーに第三者割当増資を実施した。同社の声明によると、この投資は、AV技術を使って地域のモビリティサービスを変革するための共同作業を促進することを目的としている。
重要性: 三菱商事は、日本の地方における輸送効率と利便性の向上を目指す 「地域モビリティのデジタルトランスフォーメーション」 に積極的に取り組んでいる。これには、交通問題に対処するためのAIを搭載したオンデマンドバスやタクシーサービスへの取り組みも含まれている。自動運転技術の可能性に着目した三菱商事は、2022年に福岡空港で自動運転バスの実証実験に参加した。一方、日本を拠点とするスタートアップ、ティアフォーは、AV操作のためのオールインワンソフトウェアスタックであるAutowareを開発した。同社によると、同社のオープンソースソリューションは、自動車メーカーや政府機関、その他のAVスタートアップを含む世界200社以上で利用されているという。最近、いすゞはティアフォーに60億円 (約4,000万米ドル) を投資する計画を発表した(日本:2024年3月6日: いすゞはティアフォーと共同でAVシステムの開発を行っている参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
マルチ・スズキ、2月の自動車生産台数が急増;インド初の工場内鉄道サイディング、グジャラート工場で共用開始
2024年3月15日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド
Jamal Amir, Research Analyst
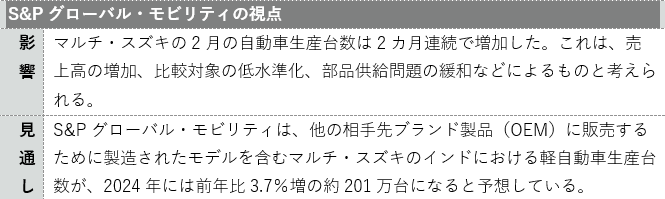
同社のプレスリリースによると、マルチ・スズキの2月の自動車生産台数は前年比11.5%増加した。同社の乗用車と小型商業車 (LCV) を合わせた総生産台数は先月178,261台で、2023年2月の159,873台から増加した。このうち乗用車、実用車、バンを合わせた乗用車の生産台数は174,543台で、前年比11.6%増となった。マルチ・スズキの 「アルト」 や 「Sプレッソ」 などのミニセグメント車の先月の生産台数は、前年比31.6%減の13,891台だった。「バレーノ」 、 「セレリオ」 、 「ディザイア」 、 「イグニス」 、 「スイフト」 、 「ワゴンR」 などのほか、他のOEMに販売するために製造されたモデルを含む自動車メーカーのコンパクトセグメントの生産台数は、先月の前月比8.4%減の89,097台だった。ミッドサイズセグメントでは、先月のシアズの生産台数は合計で1,465台となり、2023年2月の785台から前年比86.6%増加した。「ブレッツァ」 、 「エルティガ」 、 「フロンックス」 、 「ジムニー」 、 「XL 6」 などや、他のOEM向に販売するために製造されたモデルの実用車の生産台数は56,872台 (前年比113.4%増) 、 「エコバン」 は合計で13,218台 (前年比15.6%増) となった。LCVセグメントでは、 「スーパーキャリイ」 が3,718台 (前年比8.2%増) となった。
これとは別に、同社のプレリリースによると、インドのナレンドラ・モディ首相によって、マルチ・スズキ・インディア(MSIL)の完全子会社であるスズキ・モーター・グジャラート (SMG) において、インド初の自動車工場内の鉄道サイディングが落成された。この重要な進展は、物流の効率化を目的とした政府の戦略的イニシアティブである 「ガティ・シャクティ」 プログラムの一部である。ハンサルプールにある工場内の鉄道サイディングは、物流部門のカーボンフットプリントを削減し、化石燃料消費を削減し、道路渋滞を緩和するように設計されている。グジャラート州の鉄道サイディング施設が完全に稼働すれば、インド全土の15の目的地に年間30万台の車両を出荷する予定だ。このプロジェクトは、グジャラート州政府とインド鉄道、グジャラート州産業開発公社(GIDC)とOSIL間のパートナーシップであるグジャラート鉄道インフラストラクチャー・デベロップメント (G-RIDE) との共同作業である。プロジェクトの主な目玉は、年間1,650トンの炭素排出量を相殺し、5万回のトラック輸送を廃止し、3,500万リットルの化石燃料を節約することだ。これらの数字は、環境の持続可能性と効率的な物流へのプロジェクトのコミットメントを示している。「私たちは、物流の効率化を促進する首相の野心的なガティ・シャクティ・プログラムに参加できることを光栄に思う。当社がインドの自動車会社として初めて鉄道サイディング設備を製造工場内に設置したことは、大きな節目となる、」 とMSIL常務取締役兼CEOの竹内寿志氏は述べ、付け加えた、「2030~31年までに、当社の生産能力を現在の年間200万台から400万台に倍増させることを目指しており、鉄道からの車両出荷も数倍に増加するだろう。この工場内の鉄道施設は、持続可能なモビリティへの当社のコミットメントを強化する。」
見通しと影響
マルチ・スズキの2月の自動車生産台数は2カ月連続で増加した。これは、売上高の増加、比較対象の低水準化、部品供給問題の緩和などによるものと考えられる。
同自動車メーカーは2023年に発表した新戦略 「マルチ・スズキ3.0」 で野心的な目標を掲げている。同社は、2030~31年度までに生産能力をほぼ倍増して年間400万台とし、インドからの輸出を3倍にする計画だ。現在、インドのハリヤーナ州のマネサール工場とグルグラム工場で年間約130万台を生産している。一方、SMG工場は年間約75万台の生産能力を有している。また、本事業計画の終了までに、マルチ・スズキは製品ラインアップの車種数を17車種から28車種に拡大する予定だ。製品ラインアップの28年モデルでは、圧縮天然ガス (CNG) 、バイオガス、エタノール混合燃料、フレックス燃料などの、燃費効率の高い内燃機関 (ICE) を搭載し、全体の60%を占める見込みだ;ハイブリッド電気自動車が25%を占める;および電気自動車 (EV) が15%を占める (インド:2023年8月8日:マルチ・スズキは生産能力を倍増し、インドで6台のBEVを発売する計画およびインド:2024年2月7日:マルチ・スズキによると、1月の生産台数は急増し、今後数年間で8つの新型車を投入する計画参照)。
マルチ・スズキは最近、スズキ株式会社からSMG工場の株式100%を取得する提案に98%の株主が賛成したと発表した(SMC) 。SMG工場の買収は、自動車業界における同自動車の地位をさらに強化し、成長戦略に貢献する。SMG工場の買収する決定は、成長する市場の需要に対応するための自動車生産の効率化とカーボンニュートラルを達成するため であった(インド:2023年11月20日:マルチ・スズキ、スズキ・モーター・グジャラート買収承認参照) 。同自動車メーカーは2024年1月、インドのグジャラート州に3,820億ルピー (46億1000万米ドル) を投じて新工場を建設し、同州の既存施設に新たな生産ラインを追加する計画を発表した。そのうち同自動車メーカーは、3,500億ルピーを投資して年間生産能力100万台の新工場を建設し、残りの320億ルピーはSMGのEV生産施設に年産能力25万台の新生産ラインを増設する。生産ラインの増設は2027年度、新工場の稼働は約2年後を予定している。新たに発表されたグジャラート工場と新生産ラインに加えて、同自動車メーカーはインドのハリヤナ州カルコダでも新工場の建設を開始した。工場での最初のラインは、生産能力は年間25万台で、2025年前半に生産を開始する予定である。その後、毎年新しいラインが追加され、年間100万ユニットの生産能力に達する (インド:2024年1月10日:この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、ホンダとEV分野で提携検討
2024年3月14日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
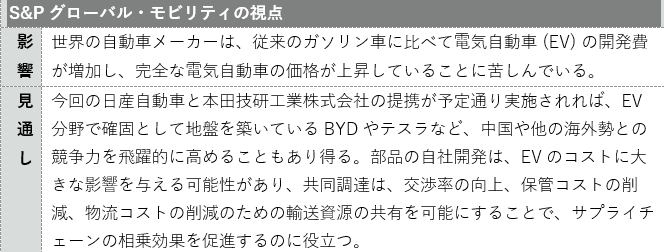
Nikkei Asiaが日産関係者の話として報じたところによると、日産はホンダとEV分野での提携を検討しており、共同調達や共同開発も視野に入れている。日産は、両自動車メーカーが協力して調達を進めるユニバーサルEVパワートレインの採用や、相互のEVプラットフォームの設計・開発を検討している。報告書は、日産内での議論はまだ予備段階であり、提携の可能性に関するホンダの立場はまだ明確になっていないことを示している。複数の関係者によると、将来的に両自動車メーカーはバッテリーの共同調達や車両開発も検討する。
匿名の情報筋を引用して、日産の取締役会がホンダとの提携の可能性を検討することを決定したと述べたとのテレビ東京の報道を受けて、日産の広報担当者は、この報道に関するロイターへのコメントを拒否し、3月12日に同社の取締役会が開催されたかどうかは分からないと述べた。ホンダの広報担当者は、同社はこの報道について言えることは何もないと述べた。さらに、日産の長年のパートナーであるルノーの広報担当者は、 「アライアンスの新たな枠組み合意の下で、提携企業は共同プロジェクト以外の戦略的決定を自由に行うことができる。」 と述べた
見通しと影響
世界の自動車メーカーは、従来のガソリン車に比べてEVの開発に伴う費用が増加し、その結果、完全な電気自動車の価格が上昇していることに苦しんでいる。
今回の提携が予定通り実施されれば、EV業界で確固とした地盤を築いているBYDやテスラといった海外勢に対して日産とホンダ両社の競争力を飛躍的に高めることもあり得る。部品を自社開発することで、自動車メーカーが生産工程を直接コントロールできるようになり、生産工程の合理化によるオペレーションの最適化やコスト削減、廃棄物の削減、生産各段階ごとのコスト削減などが可能になり、EVのコストに大きな影響を与える可能性がある。共同調達は、交渉率の向上、保管コストの削減、物流コストの削減のための輸送資源の共有を可能にすることにより、サプライチェーンの相乗効果を促進するのに役立つ。コストを削減し、効率性を向上させることで、自動車メーカーはより競争力のある価格とより良い価値を消費者に提供することができ、この競争の激しい市場で目立つことができる。
日産はルノーと長年の協力関係を築いており、最近のアライアンスの変更にもかかわらず、ルノーのアンペール事業部門との協力関係はある程度継続される (日-仏:2023年12月7日:日産自動車と三菱自動車、ルノーのアンペールへの投資計画を確認参照) 。日産はまた、提携企業の三菱自動車と共同でバッテリー式電気自動車 (BEV) プロジェクトに取り組んでいる(日本:2023年2月27日:日産、2030年のEV目標を引き上げ参照) 。
これまで提携に消極的だったホンダは、ソニーグループ株式会社とジェネラル・モータズ社は共同でEVを開発することで、この流れを断ち切った(米国:2023年1月5日:ソニー・ホンダモビリティは、2026年にアフィーラブランドで最初の車を発売予定参照)これらの協力により、ホンダがエレクトロニクスとエンターテインメントのソニーと自動車製造のGMの技術力を活用して、消費者の変化する要求に応える革新的で魅了的なEVを開発することができた。ホンダは2022年4月、研究開発(R&D)に10年間で約8兆円 (540億米ドル) を投じる計画を明らかにした。このうち約5兆円を電動化やソフトウェア技術などに充てる。電動化の目標達成に向け、同自動車メーカーは全固体電池を含む電池技術の革新に注力し、よりコスト競争力のある高効率なEVの開発を進めるとともに、シナジー効果を発揮するための事業再編を進めていく。(日本:2022年4月12日:ホンダ、今後10年間の研究で640億米ドル出資へ参照) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、 「軽BEV」 の自社生産を可能に-報道
2024年3月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析 -日本
Ian Fletcher, Principal Analyst
事情に詳しい関係者5人がロイターに語ったところによると、日産はその年代の終わりころから軽バッテリー式電気自動車の生産を内製化する可能性がある。日産は2028年4月に始まる会計年度から、これらの車の生産を三菱から日本の九州にある日産の工場に移す可能性があると、二人の匿名の情報筋が通信社に語った。関係者によると、日産は軽BEVのサイズと主な用途である小旅行で人気が高まることを期待しており、生産を自社内に持ち込むことで 「生産効率を高め、コストを削減する」 ことを期待しているという。しかし、関係者は、日産と三菱自動車は今後もNMKV 50:50合弁会社 (JV) を通じて小型BEVの企画・開発に協力していくともいう。関係者によると、日本の三菱自動車水島工場は、BEV以外の軽自動車の生産を継続する。
重要性: 記事によると、日産は現在、三菱自動車の水島工場で生産されている同社初の軽バッテリー式電気自動車 「さくら」 の需要に後押しされたようだ。S&Pグローバル・モビリティのデータによると、同自動車メーカーは2023年の初年度に日本で37,500台を登録し、2024年には40,400台に増加する見込みだ。しかし、報道されている動きは、日産がすでにこの種の製品の数を増やしている施設から軽バッテリー式電気自動車の生産をシフトすることを意味する。実際、日産の 「さくら」 は、 「三菱ミニキャブバン」 や 「eKクロスEV」 の電気バージョンと並んで製造されている。また、水島工場では、2027年中に日産と三菱自動車の両方のブランドのための新しい軽バッテリ-式電気多目的車 (MPV) を追加する予定だ。関係者の1人によると、日産は、2024年の稼働率は約80%とされる九州工場の稼働率も、今回の変更によって向上すると記事は付け加えていう。しかし、そのためには、エクストレイルをベースにした北米ローグの生産は-スペースを確保するために敷地の別の場所に移動することになる。モビリティの予測によると、ローグとエクストレイルは2026年に更新される予定で、日産が2027年に軽自動車を九州に移転する計画を進めている場合は、この時期が好都合となる可能性が高い。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタとステランティス、ブラジル向け新規製造投資を発表
2024年3月7日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-ブラジル
Stephanie Brinley, Associate Director
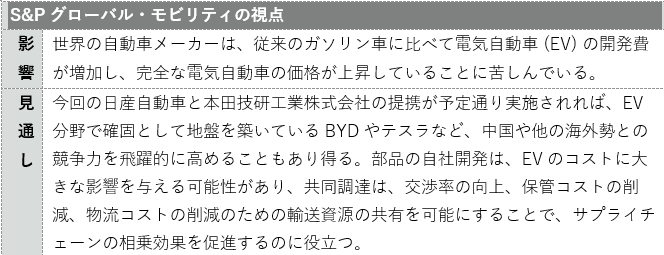
トヨタは2030年までに20億米ドル (110億レアル) をブラジル市場向け車とフレックス燃料ハイブリッド車に投資する。ステランティスは300億レアルの投資を決定した。いずれの場合も、これらは長期的な投資であり、各自動車メーカーは計画の概要のみを共有している。
トヨタ
報道によると、トヨタは2026年までに50億レアルを投資し、2026年から2030年までに残りの60億レアルを消費する計画だ。トヨタはブラジルに対する今後の投資計画をあまり発表しておらず、これらの計画の詳細はすべて明らかになっていない。しかし、トヨタはブラジルに特化したモデルと、新しいフレックス燃料ハイブリッド車を追加することを決定した。2番目の車の時期は明らかにしていないが、同社はフレックス燃料ハイブリッド技術も提供すると述べている。フレックス燃料ハイブリッドラインが最初に稼働し、2025年に生産を開始する。トヨタは、投資期間を通じて生産能力を拡大し、2,000人の新規雇用を創出することを目指すとしているが、新型車の時期については明らかにしていない。製品計画の詳細は明らかにされていないが、地元の記者によると、自動車とスポーツ用多目的車 (SUV) が開発中だという。
この投資は、トヨタのソロカバの施設で行われ、トヨタによると、この施設はすでにフル稼働しているという。また、トヨタはこの投資の一環として、ソロカバ工場の施設を拡張し、事業をインダイアトゥバからソロカバに移転する。トヨタは2025年に移転を開始し、2026年末までに完了する予定だ。インダイアトゥバの従業員には、車で約1時間の距離にあると伝えられているソロカバ工場への異動の機会が与えられる。トヨタはインダイアトゥバ工場の今後の計画について明らかにしていない。トヨタはまた、製造拠点をソロカバに統合することで500人の雇用が増えると予想されており、インダイアトゥバからの雇用の100%は移転するものの維持されると述べた。トヨタは2026年半ばに新施設での業務のための雇用を開始し、2030年までに雇用の増加を見込んでいる。2025年、ポルト・フェリースでハイブリッド・システム・エンジンの組み立てが始まる。続いて、2026年以降はソロカバでバッテリーの組み立てが追加される。
トヨタはまた、この投資が他のサプライヤーの投資を促進し、他のコンポーネントの現地化をさらに促進し、現地調達率を上げることが期待されると述べている。トヨタはブラジルでの計画について、 「現地の状況や顧客のニーズに合わせた新しい電動化技術によって脱炭素化を推進することが主な焦点だ」 と述べた。 トヨタはまた、この投資が他のラテンアメリカ諸国での支援のプレゼンス向上に役立つと期待している。
ステランティス
ステランティスは今回の発表で詳細を明らかにしなかったが、投資額は南米地域で過去最高額だとしている。ステランティスの投資期間は2025年から2030年までで、40以上の新製品の発売が含まれる。これは、既存の製品ラインへの新しいパワートレインの可用性の拡大を新製品として寛大にカウントすると考えられている。ステランティスはまた、バイオハイブリッド技術、 「自動車サプライチェーン全体にわたる革新的な脱炭素技術、戦略的な新しいビジネス機会」 にも取り組む。ステランティスの最高経営責任者Carlos Tavaresは声明で、 「今回の発表は、南米自動車産業の将来に対する当社の信頼とコミットメントを確固たるものにするものであり、当地の良好なビジネス環境に応えるものです。「第三のエンジン」 成長戦略の重要な部分として、南米は、従業員、サプライチェーン・ネットワーク、パートナーとともに、モビリティの脱炭素化を加速するために主導的な役割を果たします。業界をリードするカーボンニュートラルの野望を一緒に達成できるよう、投資戦略の策定と実行を支援してくれた各チームメンバーに感謝します」。
ステランティスは、今回の投資により、バイオ燃料 (ブラジルでは通常はエタノール) を動力源とするハイブリッド車の世界的な専門センターとしてのベチン施設の地位が向上すると述べた。ステランティスによると、同社の技術は電動化とバイオ燃料を動力源とするハイブリッドエンジンを3つの異なるレベルで組み合わせるという。これには、バイオハイブリッド、バイオハイブリッド電動デュアルクラッチ (eDCT) トランスミッション、およびバイオハイブリッドプラグインが含まれる。ステランティスは、BEVの生産も最終的にはブラジルでの生産に加わる予定だとも述べた。ステランティスによると、このバイオハイブリッド技術はブラジルで製造されたさまざまなモデルに組み込むことができ、この地域のすべての生産ラインに対応しているという。新しいハイブリッド技術の最初のものは、2024年末までに提供される予定だが、ステランティスはどの車両が最初にオプションを提供するかを明らかにしなかった。
見通しと影響
両社ともプログラムの導入に関する詳細は明らかにしていないが、S&P Global Mobilityの2024年2月の生産予測には、トヨタとステランティスの電動化生産追加への期待が反映されている。これらの発表は、フォルクスワーゲン (VW) 、ゼネラルモーターズ (GM) 、現代自動車 の最近数カ月のニュースにも続いたものでもある。S&P Global Mobilityの軽自動車生産アナリスト、カルロス・ダ・シルバは、こうした歴史的に高水準の投資は、自動車メーカーがブラジルやより広範な南米地域に将来性をまだ見出していることを示していると指摘する。さらに、自動車メーカーは、戦略がEVに100%焦点を当てていない地域としてこの地域を見ている可能性がある。関心の高まりは、地域戦略の再考を示唆しているかもしれない。2024年2月の予測はこれらの発表の前に確定したが、発表されたアクションのいくつかはすでに予測に組み込まれている。しかし、今後の予測ラウンドでは、トヨタのインディアトゥバとソコラバの統合決定など、必要な変更をすべて反映するための調整が行われる。
これらの企業のこれまでの投資サイクルは、おおよそ2021年から2023年の間に終了した。COVID-19と関連する障害により、計画は中止または延期された。その結果、ここ数カ月に発表された投資の中には、以前の計画を反映したものもある。しかし、変化したように見えるのは、電化を重視するようになったことである。
トヨタはすでに、インディアツバ工場ではカローラハイブリッドをガソリン車とフレックス燃料車の両方を、ソロカバ工場ではカローラクロスのガソリン車とフレックス燃料車の両方を生産している (参考、ブラジル:2023年9月22日:トヨタ、新型カローラをブラジルで発売) 。今回の発表は、今後の予測ラウンドを洗練させる情報をさらにもたらす可能性があるが、トヨタはすでにブラジルでフレックス燃料ハイブリッド車を生産しており、同技術のパイオニアでもある。トヨタは2024年後半にソロカバでフレックス燃料ハイブリッド機能を備えた新型ヤリスクロスを投入し、2026年にはカローラクロスの小型ピックアップトラックを投入する可能性がある (参考、ブラジル:7月21日:2021年:トヨタ、ブラジル向けフレックス燃料ハイブリッドB-CUVを計画およびブラジル:2023年4月20日:トヨタ、フレックスハイブリッドコンパクトSUVの開発に向け、ブラジルに3億3400万米ドル投資)。ブラジルにおけるトヨタのハイブリッド車の生産台数は、ガソリン車とフレックス燃料車を合わせて、2023年の約45,500台から2027年には108,000台に達する見込みである。フレックス燃料の選択肢はブラジルにとって重要であるが、一部の製品はエタノールの普及率が低いラテンアメリカの他の地域に輸出されている。2027年には、トヨタのブラジルでの生産が、主に非電化のICEから完全なハイブリッド車へと変化すると考えられる。当社の予測では、2027年には、ICEおよびICEのストップ&スタートパワートレインの設置台数が、前年の約139,000台から約77,000台に減少すると見ている。トヨタは2018年にフレックス燃料ハイブリッドのプロトタイプを初めて発表し、ブラジル向けに最初にこのオプションを追加した (参考、ブラジル:2018年3月21日:トヨタ、ブラジル向けフレキシブル燃料ハイブリッドのプロトタイプを公開) 。
トヨタと同様に、ステランティスがエタノール、フレックス燃料ハイブリッド車の生産を目指していることは以前にも報じられており、同社は以前に大きな発表があることを示唆していた (参考、ブラジル:2023年8月2日:ステランティス、2024年までにブラジルでエタノールハイブリッド車を導入する計画) 。今回の発表に先立ち確定していた2024年2月の軽自動車エンジン搭載車の生産予測では、ステランティスは、マイルドハイブリッドとフルハイブリッドソリューションと共に、2026年にもブラジルでBEV生産を追加する可能性があると予測している。しかし、現時点では、この10年のステランティスのPHEV生産を反映していない。2024年2月の予測では、2030年までにステランティスのブラジルEV生産台数は約6万台に達し、フルハイブリッド車の生産台数は308,000台に達すると予測している。ステランティスのブラジルにおける製造拠点は世界最大規模の複合施設の一つであり、2030年には約864,000台をブラジルで生産すると予測されている。
他の企業のこれまでの発表には、GMが70億レアル、現代が11億米ドルを投資するというものがある (参考、ブラジル:2024年2月26日:現代自動車グループ、2032年までにブラジルに11億米ドルを投資およびブラジル:2024年1月26日:GM、ブラジルに70億レアルの投資を発表) 。GMの投資は、ICEや電動化製品を含む次世代の自動車を支えている。現代の発表は製品の方向性を明確にしておらず、11億米ドルにはパートナー投資も含まれていると報じられているが、同社はフレックス燃料ハイブリッド・パワートレインなどのグリーン技術に投資する計画だ。VWはまた、ブラジルでフレックス燃料ハイブリッド車を生産することも明らかにした(参考、ブラジル:2023年11月15日:VW、ブラジル工場でフレックス燃料ハイブリッドエンジン生産への投資を計画-報道およびブラジル:2023年7月12日:VW、南米事業強化に10億ユーロ投資) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、サンダーランドでリーフの生産終了、JLRは欧州のICEスポーツカー、セダンの生産を6月に終了と報道
2024年5月5日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-英国
Ian Fletcher, Principal Analyst
日産は先週、サンダーランド工場で現行のバッテリー電気自動車 (BEV) リーフの生産を終了したと報じられている、とAutocarは報じている。同自動車会社の広報担当者は、「世界初の100%電気自動車 (EV) である現世代の日産リーフは、欧州でのライフサイクルを終えようとしています。市場の在庫状況にもよりますが、欧州のお客様は車両の在庫がなくなるまで注文することができます」 。 しかし、 「日産はすでに、持続可能性と電動化への取り組みの一環として、サンダーランド工場で生産する欧州市場向けの100%電気自動車の新ラインアップを発表している」 と代表者は付け加えた。 これとは別に、JLRは英国のキャッスル・ブロムウィッチ工場での内燃機関 (ICE) 車、ジャガーのセダンとスポーツカーの生産を6月末までに終了する計画だという。Road & Trackによると、JLRの北米社長兼CEOであるJoe Eberhardtは、「当社の製品の大半は6月に生産を終了しますが、販売期間はずっと長くなります。」と述べた。 彼はさらに、 「新車が来るまで、車両を継続的に供給できるような生産スケジュールを組むつもりだ...新製品の発売までに十分な量を確保し、綺麗に引継げるよう、タイミングを計ろうとしている」 と付け加えた。 上級幹部は続けて、 「それが完璧に計画されたものになるかどうかは、いずれ分かります-もっと早く完売するかもしれませんし、現在の在庫で販売するにはもう少し時間がかかるかもしれません。しかし計画では、現在の製品ラインを終えてから、新しい製品を投入することになっている」 。
重要性: サンダーランド工場は、第2世代日産リーフの生産を段階的に廃止する最初の工場となり、これはS&P Global Mobilityの生産予測の通りである。当社の予測では、日本の追浜工場での生産は2024年末に終了し、最終的に米国のスマーナ工場が2025年半ばに終了する予定だ。当社の現在の予測では、この生産終了により、今後数年間で多くの新しいBEVの生産が促進される見込みである。その第1弾は、コンパクトクロスオーバーになると予想されているリーフの後継機になると予想されている。Mobilityの予測によると、このモデルの生産は2025年第二四半期に開始される。続いて、2026年第二四半期と2027年第四四半期に登場すると予測されている次世代のバッテリー電気自動車JukeとQashqaiが登場する。JLRのジャガーの生産計画については、私たちの予測で述べたキャッスル・ブロムウィッチでのXE、XF、Fタイプの生産終了は、ブランドがBEVオンリーへの移行を開始する際にEberhardtが述べたことと概ね一致している。しかし、Mobilityの予測によると、ジャガーのセダン製品の一部は、中国の常熟にあるCherry Jaguar Land Rover (CJLR) 工場で引き続き生産される。欧州では、JLRは、この移行の一環として、マグナのグラーツ (オーストリア) 工場のE-PACEの生産を2024年末に、I-PACEの生産を2025年第二四半期に終了し、また、F-PACEは2026年第三四半期末にソリハル工場での生産を終了する。Mobilityの予測によると、Jaguarの最初の新世代BEVは、新しいJEAプラットフォームを使用したXJで、2025年末にソリハルで生産が開始され、2026年の第四四半期に同じ場所で新しい大容量バッテリーの電気クロスオーバーの生産が開始される。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
トヨタ、3月4日に国内工場で生産再開へ
2月16日2月28日2024年-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析--日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
トヨタ自動車は、いなべ工場生産ライン1と岐阜車体工業生産ライン1を豊田自動織機(TICO)製エンジンで3月4日に再稼働する。これにより、トヨタの国内全工場で生産を再開し、国内出荷を再開する。この決定は、昨日(2月27日)、日本の国土交通省がTICOが生産するディーゼルエンジンの出荷停止を解除すると発表したことを受けたものである。
重要性: トヨタ自動車がディーゼルエンジンの開発を委託しているTICOが、ディーゼルエンジンモデル3種の認証に矛盾があると報告したことを受け、1月29日から運転を停止している。これらの矛盾の影響を受けるエンジンモデルは、1GD、2GD、F33Aであり、関係する車両は、ランドクルーザープラド、ハイエース、グランエース、ハイラックス、フォーチュナー、イノーバ、LX500d、ランドクルーザー300である。日本の国土交通省は先週、TICOに対し、エンジンデータの不正操作事件を受けてコンプライアンス対策を強化するよう指示した(参考、日本:2024年2月22日:日本国土交通省、豊田自動織機に是正命令) 。対象車種の生産と販売が再開されれば、別の傘下企業であるダイハツも安全性に関するスキャンダルに巻き込まれているトヨタグループにとっては待望の救済措置となる。トヨタグループの1月の生産台数は、この2カ月間の子会社の生産停止により大幅に減少した。トヨタグループは本日、先月の世界生産台数が前年比3.8%減の788,670台となったことを発表した。このうち、トヨタブランド (レクサスを含む) は前年比7.4%増の740,332台、ダイハツは同67.8%減の37,434台、日野は同24.2%減の10,904台となった(参考、日本:2024年2月28日: トヨタグループの2024年1月の世界生産は3.8%減、売上高は4.4%増) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
日産、自社開発のレぺル4 AVモビリティサービスを国内で実用化へ
2024年2月4日~2024年2月28日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
日産自動車は、自社開発のレベル4自動運転車 (AV) モビリティサービスを日本市場に投入する計画を明らかにした。日産は、2024年度中に横浜みなとみらい地区で、ミニバン 「セレナ」 をモデルにしたAVの走行試験を開始すると発表した。今後、2025年度から2026年度にかけて、横浜市内のみなとみらい、桜木町、関内などで運転手付き車両20台によるサービス実証実験を実施します。2027年度に予定されている最終段階では、地方を含む三、四の自治体で数十台規模のサービスを開始します。同社は現在、この計画について複数の自治体と協議している。日産によると、この取り組みは経済産業省や国土交通省などの中央省庁と緊密に連携して進めていくという。これらの省庁はまた、新しいレベル4のAVモビリティサービスを立ち上げる取り組みを支援する。
重要性: 日産は、2017年から国内外でモビリティサービスのビジネスモデルを検討してきたとしている。これには横浜みなとみらい地区や福島県浪江町などの地域が含まれ、浪江町では2021年から 「なみえスマートモビリティ」 と呼ばれる有人モビリティサービスが稼働している。日本以外でも、日産自動車は英国政府の支援を受け、ロンドンなどでAVモビリティサービスの実証実験を行っている (参考、英国:2023年2月17日: 日産が支援する自動運転モビリティプロジェクト 「サーブシティ」 が試験完了) 。高齢化が進む日本では、運転手が不足する可能性が高い。これらのモビリティプロジェクトは、そのような状況を回避するのに役立つ。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
M&MはVWと提携し、BEV部品やセルを供給
2024年2月16日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-ドイツ-インド
Tim Urquhar, Principal Analyst
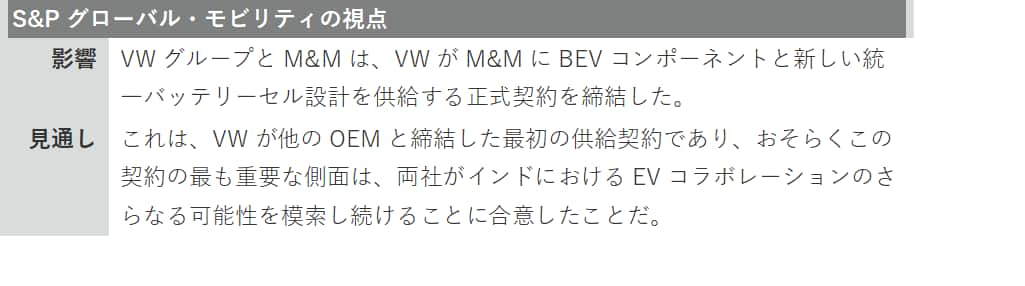
企業の声明によると、フォルクスワーゲン (VW) グループとマヒンドラ&マヒンドラ (M&M) は供給契約を締結し、VWがM&Mにバッテリー電気自動車 (BEV) 部品と新型統一バッテリーセルを供給することとなった。VWがMEB電気自動車 (EV) アーキテクチャの部品を供給する契約を結んだのは初めてであり、同社の新しい統一バッテリーセルを別のOEMに供給する契約を結んだのも初めてであるため、両社にとって重要な取引となる。しかし、今回の買収の最も重要な側面は、M&Mの自動車電動化プログラムを支援するために、さらに徹底した協力関係を築くことができるという点だろう。両社は2022年に提携契約とタームシートにより開始された、当初の提携意志を固めた。
今回の新規契約の主な内容は、M&MがVWの今後のバッテリー戦略の中核である統一セルコンセプトを使用する初の外部パートナーとなることである。供給契約は数年にわたり継続され (ただし、当初のプレスリリースでは正確な契約期間は明らかにされていない) 、契約全体での総容量は約50 GWhとなる。これらのバッテリーとコンポーネントは、M&M独自のカスタムメイドのINGLO BEVアーキテクチャで構築された車両をサポートするために使用される。2024年12月にインド市場向けにこのアーキテクチャに基づいた最初のモデルの生産が予定されており、最終的にはそれに基づいた5台の車両の発売を目指している。このプラットフォームは、長さ4,368 mmから4,735 mmのスポーツ多目的車 (SUV) をサポートします。プラットフォームのホイールベースは、わずか13 mmではあるが、2,762 mmから2,775 mmまで調整可能だ。前面と背面のオーバーハングは87 mmから293 mmの範囲で、主にこれがモデル間の違いを産んでいる。
見通しと影響
今回の発表は、M&Mのインド市場向けBEVプログラムに関する、VWグループとM&Mの拡大し深化する協力の以前の詳細に追加されたものである。M&Mは、INGLOアーキテクチャのローンチを発表した際に、このアーキテクチャは、リーンモジュールと標準化されたCell-to-Pack技術を用いた共通のバッテリーパック設計を使用しており、(BYD独自のセルで使用されている) ブレードとプリズムという2つの異なるセル構造が利用されていると述べた。しかし、VW統一セルはプリズム型であるため、その意図は、根本的に異なる2つのセル設計をINGLOアーキテクチャで使用することであると思われる。M&Mは以前、INGLOアーキテクチャにVWの最新後輪駆動モーターAPP 550を採用するとも発表していた。これは、昨年VW ID .7フラッグシップBEVでデビューした同社の最新かつ最も効率的な電気モーター設計であり、共有され、INGLOアーキテクチャに適用可能となるMEBコンポーネントの範囲が、今回の最新の合意により拡大されるようだ。
M&Mは以前、新しいEVシリーズを既存のXUVブランドと、まったく新しい電気専用ブランドBE の2つのサブブランドで構成すると発表した。両ブランドは、電気SUV 「XUV.e 8」 「XUV.e 9」 「BE .05」 「BE .07」 「BE .09」 の5車種をラインアップする。M&MのBEV攻撃の最初のモデルは、今年12月に発売予定のXUV.e 8だ。この車は基本的に、M&Mの現在のフラッグシップSUVであるXUV 700に対応する電気自動車だ。同じ基本レイアウト、同じシルエット、同じ3列シートを前面に押し出している。全輪駆動システムと80 kWhのバッテリーパックが特徴で、230 bhpから350 bhpの範囲の出力を提供すると言われている。VWとM&Mの提携拡大におけるこの最新の一歩は、インドの乗用車市場全体に占める割合がまだ非常に小さいものの、これまでタタが独占してきた新生インドのBEV市場に大きな影響を与える可能性がある。しかし、マヒンドラは、タタの現在のラインアップよりもハイエンドのBEVをラインナップし、本格的な競争を提供する大きな計画を持っている。現時点では、これらの車をできるだけ手頃な価格にすることで、インドでのBEVの認知度と受け入れ、BEVの成長を支えるために必要なインフラを高めることに焦点を当てている。しかし、S&Pグローバル・モビリティは、マヒンドラのBEV展開は緩やかに増加し、同社が製造するすべての電気軽自動車の生産台数は、現在の10年代末までに157,000台にとどまると予測している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
Infineon Technologiesとホンダ、自動車向け半導体分野で協業
2024年2月4日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析 -日本
Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive
Infineon Technologiesは、自動車半導体分野におけるホンダとの戦略的パートナーシップを明らかにした。日刊自動車新聞が報じたところによると、両社は自動車用半導体の安定供給について協議するとともに、将来の半導体製品や技術のロードマップを交換する。今回の協業の目的は、ホンダの次世代自動車向け半導体技術の市場導入を促進することである。インフィニオンは、パワー半導体、先進運転支援システム (ADAS) 、電気/電子 (E/E) アーキテクチャの専門知識でホンダを支援し、先進的で競争力のある自動車の開発を目指す。
重要性: 自動車用半導体の需要は、電気自動車 (EV) やADAS、自動運転システムへの急速な移行を背景に、近年急速に拡大している。ホンダは、半導体をはじめとする部品の供給不足に対応するため、主要部品のデュアルソーシングや代替部品の開発などの対策を行っています。また、TSMCをはじめとする半導体メーカーとも戦略的な提携を行い、半導体の安定供給に努めています。この日本の自動車会社は2022年、10年間で総額約8兆円 (530億米ドル) を研究開発費に充てる計画を発表した。このうち約5兆円は、電動化とソフトウェア技術に使用される予定だ (参考、日本:2022年4月12日: ホンダ、今後10年間の研究に640億ドル投資) 。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
GMとホンダ、新型水素燃料電池システムの生産を開始
2024年1月26日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-日米-米国
Stephanie Brinley, Associate Director
両社の共同声明によると、ゼネラル・モーターズ (GM) とホンダの水素燃料電池システムの合弁企業 (JV) が、商業生産を開始した。燃料電池システム製造 (FCSM) と呼ばれるJVは2017年1月に設立されたが、エンジニアリング研究開発における両社の協力は2013年に開始された (米国参照:2013年7月2日: ホンダとGM、燃料電池技術と米国で協力へ:2017年1月31日: 850万ドルを投資し、2020年に生産を計画) 。両社は新工場で燃料電池システムを生産してきたが、最新の発表は規模拡大と商業化の次の段階を示している。FCSMによると、新しいシステムは従来のシステムに比べて性能が向上し、耐久性が二倍になり、製造コストが削減されるという。企業の発表によると、ホンダの2019年型セダン「クラリティ」 の燃料電池システムのコストと比較すると、新システムは1/3安い。FCSMは、膜電極の製造と燃料電池スタックの組み立てを自動化する、これまでにない方法を導入しているという。
重要性:両社は燃料電池システムを展開するための明確なビジネスプランを提示している。ホンダは、このシステムを燃料電池電気自動車 (まもなく発売予定のCR-V FCEVを含む) 、商用車、定置型発電所、建設機械 (中国 (本土) -米国-日本参照:2023年4月26日: ホンダは、ビジネス変革と電動化計画を以下のように説明している、カナダ-米国-日本:2023年2月3日: ホンダ、水素への注力を拡大するため、2024年に日本と北米および中国 (本土) -米国-日本で新型FCEVを導入:2022年12月1日: ホンダ、米国の燃料電池CR-V、ハンズオフ運転支援技術計画を発表) 。ホンダはまた、いすゞと共同で進めている燃料電池商用車を開発するプロジェクトを2027年に開始する予定であることも明らかにした(日本参照:2020年1月15日: ホンダといすゞ、燃料電池を動力源とする大型トラックの共同研究を実施) 。また、ホンダはクラス8の水素燃料電池トラックの開発を進めており、掘削機やホイールローダーなどの建設機械への適用を目指している。ホンダはまた、カリフォルニア州トーランスにある同社の米国データセンターでも、燃料電池スタックを定置型発電所に使用している。ホンダの水素利用開発支援は、ホンダクラリティが2016年に発売される以前から行われており、日本と米国でのプロジェクトも含まれている (日本参照:2016年10月25日: ホンダ、日本で新しい水素ステーションのテストを開始-レポートおよび日本:2017年10月25日: ホンダ、2020年までに全国100カ所に水素ステーションを設置) 。GMは商用車、定置型蓄電ソリューション、船舶や鉄道への応用の可能性など、多数の燃料電池プロジェクトを発表している。今のところ、CR-Vを除けば、両社の計画は主に非市販車ソリューションに焦点を当てている。GMは燃料電池システムを使用した製品を 「ハイドロテック」 ブランドで販売する。プロジェクトには、マイニングトラックや商用車メーカーのオートカー (米国参照:2023年12月14日: GM、コマツと共同で燃料電池を動力源とするマイニングトラックを開発 、米国:2023年12月8日: GM、商用車メーカーオートカーに燃料電池ソリューションを提供、米国:2022年1月20日: GMはハイドロテック燃料電池パワーキューブ事業の拡大を目指す、米国:2021年6月16日:GM、ワブテック、鉄道業界向けにアルティアムバッテリおよび燃料電池ソリューションを開発および米国: 2021年1月28日:ナビスターは水素トラックのエコシステムを計画、GMは燃料電池電力キューブを供給) 。 米国では、小売用燃料電池車の所有者を支援するためのインフラが初期段階にある;しかしながら、商用車のデューティ比は、そのような利用をサポートするための燃料供給ネットワークの比較的迅速な確立を可能にするかもしれない。数十年の視点で見ると、商用利用は最終的には小売車両の燃料供給ネットワークのサポートにつながる可能性がある。しかし、COVID-19のパンデミックとその後のサプライチェーンの問題、および市場がまだ発展しているという事実のために、燃料電池ソリューションの開発と商業展開はある程度減速しているようだ。しかし、2024年には、特定の用途のために、水素溶液への関心がある程度の牽引力を得ていることを示すメッセージが増加している。この関心は、当初の計画通りに2020年にシステムが稼働した場合よりも、市場との整合性が取れている可能性がある。GM-ホンダ JVが技術開発を進めており、両社は市場における競合関係にあるため、両社が異なるアプローチで製品化・展開することが期待されていた。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
GAC、日野との株式譲渡契約でJVの株式を取得
2024年1月26日-オートインテリジェンス|ヘッドライン分析-中国 (本土)
Abby Chun Tu, Principal Research Analyst
日野自動車と広州汽車集団 (GAC) は、GAC日野合弁会社 (JV) の主要株主となる株式譲渡契約を締結した。日野自動車は、GAC日野の株式50%のうち39.72%をGACに、GAC日野の株式50%のうち5.45%を高州青雲新エネルギー技術 (青雲) に譲渡する。日野自動車は、今回の株式譲渡で得た約34百万元の資金を全額、中国JVの増資に充てる。これにより、日野自動車のGAC日野に対する持分は4.83%に減少する。「日野自動車は、引き続きGAC日野を少数株主として支援し、中国市場に日野ブランドの車両とアフターサービスを提供していく。」と同社の日本自動車メーカーは声明で述べた。
重要性:GAC日野は、商用車の生産を行う50:50JVとして2007年に設立された。この取引により、GAC日野の製品ラインをより多くの新エネルギー車(NEV)に移行する計画を進めることができる。株式譲渡契約の一環として、GAC、青雲、日野自動車はGAC日野に7億元を共同出資し、新製品開発を支援する。GAC日野の大型トラック販売台数は、2025年までに5,000台に達する見込みだ。同社はまた、JVの小型商用車の販売台数が今後数年間で大幅に増加すると予想しており、同社は新しいバッテリー式電気ライトバンと水素燃料電池バンを含む製品ラインを電動化する。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
いすゞ、平塚市で自動運転車の普及促進に関する連携協定を締結
2024年1月22日-自動車モビリティ|ヘッドライン分析–日本
Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst
いすゞ自動車は、平塚市、神奈川中央交通、三菱商事、アイサンテクノロジー、およびA-Driveと、公共交通のデジタルトランスフォーメーションに向けた協業に関する協定を締結した。同社の声明によると、この協定は平塚市での自動運転モビリティサービスの導入を目的としている。6の署名者は、また、国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業の計画の一環として、平塚市で自動運転実証バス (PoC) を発表した。この協定は、便利で利用しやすく、持続可能な公共交通サービスを提供することにより、日本の地域社会を活性化することを目的としている。
重要性:いすゞは、デジタルトランスフォーメーションと自動運転車 (AV) ソリューションを通じて、社会や物流業界の課題解決に取り組むことを目指している。この進展は、日本政府が進めている、交通の再構築によるスマートシティの実現と軌を一にしている。日本では2023年4月に改正道路交通法が施行され、一定の条件の下でレベル4のAVが公道で走行できるようになった (日本参照:2023年4月3日: 日本は道路交通法を改正してレベル4の自動運転を認める) 。日本政府は、2025年までに40の地域で、2030年までに100以上の地域でレベル4のAVを特徴としたモビリティサービスを提供することを目指している。
この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com
マツダ、米国での取引価格上昇で営業利益過去最高、出荷は課題に直面-レポート
16 May 2023 - AutoIntelligence | ヘッドライン分析
Matsuda Motor Americaが5月12日に最新の決算発表を行い、日本生産車を米国に輸送する業者の確保に苦戦している状況が続いている点にも言及した。Automotive News は、次期CEOである毛籠勝弘氏の米国市場に対する期待と、同市場での価格改善がマツダ全体の業績に与える影響についてのコメントを報じている。毛籠氏によると、マツダは今年度の卸売販売台数が前年比13%増の約14万台になると予想しており、そのうち約半数が日本からの輸出になる見込みだという。マツダでは複数の問題によって物流に問題が生じていると報じられている。パンデミックの影響で多くの船会社が高燃費船舶への入れ替えを決定、新造船の建造にともない船腹が不足する事態が発生しているという。また、中国からの自動車輸出の増加によって船腹の空きスペースが奪われているとのことだ。毛籠氏は「そのため、船舶の獲得競争が激化している。当社では日本からの船舶の確保に取り組んでおり、船会社と相談しながら、できるだけ出荷スケジュールを標準化するよう努めている」と述べている。毛籠氏はさらに、CX-90によって米国需要の拡大が予想されること、アラバマ州のCX-50工場が7月に第2シフトを稼働することにも言及している。同工場はマツダ向けが年間15万台、トヨタ向けも同程度の生産能力を持つが、立ち上がりは遅く、第2シフトはまだ追加されていない。マツダはまた、米国での平均取引価格が2018年から7,000米ドル上昇して2022年には33,700米ドルに到達、この変化により、世界販売台数が2018年の156万台から111万台に減少したにもかかわらず、2022年度は過去最高の年間収益となったと述べている。マツダではCX-90が米国価格をさらに押し上げると予想している。CX-90は40,000米ドル強でのスタートとなるが、トップトリムレベルでは61,000米ドルに達することもあり得る。CX-50も増産で貢献するだろう。マツダでは今年度の北米販売台数を前年比22%増の496,000台と予想している。 重要ポイント:マツダの全体決算の概要についてはすでに紹介した通りだ(「日本:2023年5月15日:マツダ、2022-23年の親会社株主に帰属する当期純利益が前年比75.1%増に」参照)。マツダはユーティリティ車ラインナップを強化するなど、ブランド力の向上と価格設定に取り組んできた。このプロセスはまだ完了しておらず、欧州では今年CX-80が発売され、米国でもCX-90のほか、まだ公開されていないCX-70も発売予定である(「英国: 2022年10月26日:マツダ、2023年に欧州でSUV CX- 80を導入」「米国-カナダ:2023年2月1日:マツダ、新型CUV CX-90を発表、プラグイン・ハイブリッド・パワートレイン搭載」参照)。CX-60は2022年に日本で初めて販売された(「日本:2022年4月7日:マツダ、日本仕様のCX-60を発表」参照)。マツダの価格競争力は向上しているが、その要因として、米国での新車販売に加え、2021年と2022年にほぼすべての自動車メーカーが恩恵を享受した、在庫の少なさによる強力な価格環境が挙げられる。これは概ね2022年の業界全体に一貫したストーリーであったが、マツダの価格力強化の道筋はパンデミック以前に始まっており、2021年に発表されたユーティリティ車のレンジ拡大決定も確実に貢献している。
担当アナリスト:Stephanie Brinley
Teslaの再値下げでドイツ系OEMの国内市場競争が激化
2023年5月16日 - AutoIntelligence | ヘッドライン分析
影響: Teslaはこれまでにドイツでさらに積極的な値下げを発表しているが、それと同時にドイツ市場には中国のプレミアムBEVも多数投入されつつある。
展望: Teslaの値下げと中国から到来する優れた新型BEVの数々は、伝統的に国内市場を支配してきたドイツのプレミアム自動車メーカーにとって懸念材料であり、Teslaの積極的な値下げは特に、戦略面で悩みの種になるかもしれない。
ドイツ系プレミアム自動車メーカー各社が、国内市場のバッテリー電気自動車(BEV)分野で熾烈の度を増す競争に直面している。Teslaが新たに値下げを発表した一方で、多くの中国系OEMが魅力的な新商品をこれまでに発表、あるいはこれから発表しようとしている。Teslaは1月、欧州、米国、中国の主要市場すべてで相次いで値下げを開始した。最初の値下げは1月に発表され、ドイツでModel 3とModel Yの定価が車両構成によって最大17%下げられた。Teslaは4月にはModel 3とModel Yについて4.5%から9.8%のさらなる値下げを発表した。こうした積極的な値下げにより、これまでModel 3やModel Yを購入候補として考えていなかった消費者にも手が届くようになった。Teslaはまた、フリートおよびビジネス顧客向けの割引を拡大、2,250ユーロ(2,450米ドル)の追加割引を実施した。これにより、現在のドイツ政府のBEV環境ボーナス、メーカーおよび政府補助金は、Model 3では最大9,750ユーロになり、車両購入価格の30%、Model Yでは最大25%を占めることになる。
また、多くの中国系OEMが非常に魅力的なプレミアムBEVをこれまでに数多く発売済み、あるいは発売予定である。Geelyの欧州CEOであるSpiros Fotinos氏は同社のプレミアムBEVの新ブランド、Zeekrの新製品がドイツ系OEMに真っ向から対抗していることを認めている。同氏は「ドイツではプレミアムメーカーが市場の60〜75パーセントを占めており、そこを征服できなければ、成長はあまり望めないだろう」と述べている。ただし、Zeekrのドイツ進出は数年後であり、一方ですでに進出を始めている中国系OEMも存在する。プレミアムブランドという位置付けではないものの、Shanghai AutomotiveのMGはここ数ヵ月、ドイツで最も急成長しているブランドのひとつである。今年に入ってからの4ヵ月間でMGの販売台数は前年比104.7%増の5,000台弱に達している。GeelyのLynk & Coは市場で徐々に存在感を示しつつあり、Lucidも販売を開始している。しかし、ドイツ系OEMメーカーが最も気にしていると思われるのがBYDだ。Warren Buffetの支援を受けたこの会社は、現在中国で最も急成長している自動車メーカーであり、ドイツでの販売台数は少ないものの、BYDは深刻な市場破壊者となる可能性を秘めている。ドイツではスポーツ用多目的車(SUV)のAtto3とTang、セダンのTangが販売されており、これらの車はいずれも優れたスタイリング、構造品質、航続距離を備え、手頃な価格で購入できる。BYDが現時点で持っていない唯一のものは、ドイツにおける総合的な販売・流通チャネルである。同社はドイツ市場に大きく進出しており、ドイツのハイヤー会社であるSixtがAtto 3を10万台発注、2028年までの間にその注文に対応というニュースも伝えられている。
展望と影響
ドイツのビジネスおよびフリート市場におけるTeslaの今回の値下げにより、Model 3と現地製造のModel Yの競争力はさらに高まり、魅力的な提案となるだろう。Model Yは2022年9月にすでにドイツのベストセラーリストで総合首位を獲得しており、この車はそれ以降、同社のGrünheide工場の生産が軌道に乗ってベストセラーリストTOP10の上位半分の常連になっている。ドイツ系OEMはBEVの新シリーズ展開に向け、激化するTeslaとの競争に直面している。たとえば、ベーシックなTesla Model 3のドイツでの販売価格は41,990ユーロからスタート、これはドイツ政府が現在実施している6,750ユーロのBEV補助金全額対象であることを意味する。今回発表された法人向けインセンティブは、ベーシックなModel 3が33,000ユーロ弱で購入できる可能性を示唆する。これをBMW i4のベース価格である59,200ユーロと比較してみる。BMWがi4はModel 3よりもはるかにプレミアムな製品であると主張するのは間違いないが、どちらも名目上はプレミアムなDカー・セグメントのBEVである。これに加えて、中国系OEMとの競争もが激化しており、ドイツ系メーカーはやがて、半導体不足によって車両生産と納車が制限された比較的混乱していた時期を懐かしく振り返ることになるかもしれない。少なくとも、そのおかげで車両供給はタイトに保たれ、その結果、車両価格と構成は好調だった。ドイツ系メーカーが一番避けたいのは自国の領土で価格競争に巻き込まれることであり、それは中長期的に営業利益を損なうだけである。
担当アナリスト:Tim Urquhart
BMW、早ければ2025年に初の量産水素FCV導入
2022年8月15日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
BMWが早ければ2025年にも初の量産型水素燃料電池車を市場に投入する予定であることを報じられた。同社は2022年末までにiX5の小規模生産開始し、2025年までにフル生産への拡張を目指す。
重要ポイント: BMWでは、大量生産開始は2025年以降になるものの、水素燃料モデルでX5 SUVのラインナップを拡大する予定だ。X5 水素FCVの量産予定については、水素充電インフラの準備状況に関する BMWの検討も反映されている。個人の自動車購入者への水素FCV普及拡大を目指す自動車メーカー各社の取り組みにおいて、充電インフラが最大の障害である状況が続いている。X5ベースの水素駆動SUVにはトヨタが開発した技術が搭載される可能性が高い。トヨタは FCV部門をリードする企業であり、2013 年に初の大衆市場向け FCV、Miraiを市場に投入した。第2世代のMiraiは2020年末に発売されている。
Baidu、中国本土で完全自動運転ロボットタクシー運行の商業許可を取得
2022年8月8日 | ニュース | 企業動向
Baiduが中国本土で初めて無人ロボットタクシーの運行許可を取得したことを発表した。Baidu は同社の商用完全無人ロボットタクシー サービスであるApollo Goを公道で一般提供し、このサービスはChongqingとWuhanの両都市で利用可能になる。「公道で有償ライドを提供する完全自動運転車は、業界が待ち望んでいた瞬間だ。ついに完全自動運転サービスを大規模展開できる転換点に向けた重要なマイルストーンになる」とBaiduのインテリジェント運転グループのVP兼最高安全運行責任者であるWei Dong氏は述べている。
重要ポイント: このサービスはWuhanでは午前9時から午後5時まで、Chongqingでは午前9時30分から午後4時30分まで指定エリアで利用でき、各都市で第5世代Apolloロボットタクシー5台が運行される。Wuhanでは13㎢超、ChongqingのYongchuan地区では30㎢のエリアでサービスが利用可能になる。BaiduとPony.aiはBeijingでロボットタクシーのテストを実施しており、Beijing 経済技術開発区中心の60㎢エリアに30台の自動運転車を配備している。
Kodiak Roboticsが自動運転トラック「フォールバック」システムを実証
2022年5月13日 - Automotive Mobility | Headline Analysis
Kodiak Roboticsは、重大なシステム障害が発生した場合に自動運転トラックを車の流れから離れるよう誘導する「フォールバック(縮退運転)」システムを実証した。同社の自動運転システムであるKodiak Driverは、安全性が最重視される1,000以上のプロセスの性能を毎秒10回評価する。Kodiakの創業者兼最高経営責任者であるDon Burnette氏は次のように述べている。「人間のドライバーを乗車させない自動運転車を導入するには、トラックや自動運転システムの不具合時にその車両が他の車のドライバー達を危険な目に遭わせないようにしなければならない。フォールバックシステムの実装は、安全性を達成するための基本的必要条件である。当社は公道でこの機能を実証した最初の自動運転トラック企業として」、当初からフォールバック技術をKodiak Driverのアーキテクチャに組み込んできた。この機能を後から追加するのは非常に難しいだろう」
重要ポイント:自動運転には、緊急事態に迅速に対応するためのフォールバック技術が不可欠だ。Kodiak Roboticsは長距離トラック輸送のための自動運転技術開発に重点を置いており、同社の自動運転機能用に大陸横断ネットワークを構築する予定である。Kodiakは昨年、LuminarのIris LiDAR、Hesaiの360度スキャンLiDAR、ZFのフルレンジレーダーを搭載した第4世代自動運転トラックを発表した。2021年11月、KodiakはシリーズB資金調達ラウンドで1億2,500万ドルを調達、これまでに調達した資本は合計1億6,500万ドルになる。
VolvoがDHLと提携、ハブ間自動運転輸送ソリューションを試験的に導入
2022年5月9日 - Automotive Mobility | Headline Analysis
Volvo Autonomous Solutionsが声明で、北米の4つの主要顧客セグメントにサービスを提供する新たなハブ間自動運転輸送ソリューションを提供すると発表した。各ソリューションは、荷送人、運送業者、物流サービスプロバイダー、貨物仲介業者に分類される4セグメントのビジネスニーズに合わせて構成される。同社はDHL Supply Chainが「物流サービスプロバイダー」セグメントを代表する最初の主要顧客になり、ハブ間ソリューションを試験的に導入することを発表した。「貨物需要の高まりは能力を上回るレベルにあり、これは自動運転トラックを超えるものだ。排出量を削減して安全性を高めるために最適化されたオペレーションによって、輸送エコシステム全体に価値をもたらすと当社は確信している」
重要ポイント:Volvo Groupは2020年1月に自動運転輸送ソリューション関連の独立した事業ユニットを設立した。Volvo Autonomous Solutionsは、オンロードおよびオフロードセグメント向けの自動運転ソリューションの開発、商品化、販売を加速することを目的としている。このユニットの設立は、ノルウェーのBrønnøy Kalk鉱山やスウェーデンのGothenburg港へのサービス提供のためにVolvo Groupが多くのソリューションを投入した後に実施された。同社は最近、北米でのレベル4・クラス8トラックの開発と商品化を目的としたプロジェクトに向けてAuroraと提携した。
ホンダ、GMのUltiumプラットフォーム採用の初EV を先行公開
2022年5月19日 | ニュース | 新製品
ホンダが次世代PUV(Pure Electric Sport Utility Vehicle)のPrologueを先行公開した。2024年版ホンダ Prologue 電動SUVは、General MotorのUltiumパワートレインとバッテリーアーキテクチャを使用し共同開発された。注目すべきは、電気自動車(EV)プラットフォームであるこのUltiumが、GMC Hummer EV、Silverado EV、そして高級車Cadillac Lyriqにも使用されている点である。Prologue SUVは、ホンダが米国のGMと提携して構築する予定の2台のEVのうち1台目に当たる。Prologueは2024年に米国発売予定で、2030年までに同社が市場投入予定のハイブリッド車、バッテリー式電気自動車、燃料電池車の始まりを告げるものになる。
重要ポイント:米国市場向けEV戦略の一部であるホンダ Prologueは、独自のBEV専用プラットフォームであるe-Architectureの準備が整うまでGMのUltiumプラットフォームを使用する。ホンダのe-ArchitectureをベースにしたEVは2026年から生産を開始する予定だ。同アーキテクチャはGMが米国市場向けに一連の手頃な価格の電気自動車を生産する際にも使用される。ホンダがGMのUltiumプラットフォームをベースにEVを展開し、その後e-Architectureで展開する計画では、2030年までに北米で50万台のEVを販売することになる。The Vergeが2022年5月18日に発表した記事によると、ホンダはPrologue SUV を米国で2024年に6万台、2025年に7万台、2026年には北米市場で30万台を販売する予定だという。ホンダの北米向けEVロードマップでは、販売台数の40%をBEVとFCEVによるものとし、以降そのシェアを2035年までに80%とし、2040年には100%への到達を目指す。
Maruti Suzuki、V2X実証でIIT-Hyderabadと協力
2022年5月13日 | ニュース | 戦略提携
Maruti SuzukiがスズキとIIT-Hyderabadとともに、V2X(Vehicle-to-Everything)通信の研究デモを共同で実施したことが報じられた。紹介されたユースケースシナリオに含まれていたのは、救急車警報システム、誤進入ドライバー警報システム、歩行者警報システム、オートバイ警報システム、道路状況警報システムなどである。
重要ポイント:インドの自動車産業ではコネクティビティエコシステムの開発が徐々に進んでおり、AirtelやVodafoneなどの通信会社が自動車企業とパートナーシップを締結している。アプリケーションとしては、例えば救急車警報システムを使用すると、緊急車両への接近とその経路について車のドライバーにV2X通信を介して警告を発することができる。警報システムでは、車両間の距離などの詳細もリアルタイムで共有される。誤進入ドライバー警報システムでは、別のドライバーが道路を逆走してきた場合、ドライバーに事前警告が通知される。
WeRide、極端な気候環境で自動運転車をテスト
2022年4月19日 | ニュース | 技術トレンド
WeRideが極端な気候環境下でのロボットバスとロボットタクシーの自動運転テストを無事完了したことを発表した。同社の自動運転車は、中国・Heiheで-25℃、Abu Dhabiで45℃でテストされた。前者は地球上で非常に寒く、後者は非常に暑い場所にある。同社は極端な気候だけでなく、複雑な道路状況や、ソフトウェアとハードウェアの重要課題にも取り組んできた。車載コンピュータープラットフォームを特別設計し、効率的な熱回収と冷熱放出制御を可能にして過剰な熱の問題への対処を行う。
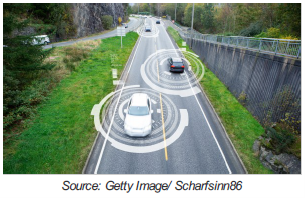
重要ポイント:WeRideはLIDAR、GPS、ホイールスピードメーター、慣性航法などのマルチセンサーフュージョン方式を採用しており、これによってリアルタイムで車両位置を特定し、ステアリング、加速、ブレーキを正確に制御する。極端な気候と高温は自動運転車の電子部品と機械部品に大きな影響を与える。
日産がNASAと協力、EV用全固体電池を開発
2022年4月11日 | ニュース | 生産統計&予測
日産自動車が米国立航空宇宙局(NASA)と共同で、電気自動車に現在使用されているリチウムイオン(Li-ion)よりも急速な充電が可能で安全な全固体電池を開発していることが報じられた。
報道によると、この全固体電池技術は2028年にリチウムイオン電池を置き換えることになるという。日産は2024年の全固体電池の試験工場立ち上げの計画も認めている。

日産の副社長である土井三浩氏のコメントが引用されており、この日産とNASA、University of California San Diegoとのコラボレーションでは、EVバッテリー開発に使用される各種材料のテストも含まれるという。「NASAと日産の双方が同じタイプのバッテリーを必要としている」と土井氏は言う。このバッテリーはペースメーカーへの使用に十分な安定性を備えており、サイズは現在のバッテリーの約半分で、わずか15分で完全充電可能であると同氏は語っている。
日産とNASAはコンピュータ制御型データベースである「オリジナル・マテリアルズ・インフォマティクス・プラットフォーム」を使用してさまざまな組み合わせをテストし数十万の材料の中で最も効果的なものの確認を進めている。目標は高価で希少な材料の使用を避けることだ、とも土井氏は述べている。
重要ポイント:日産は2010年にリーフEVを発売、最初に電気自動車を導入したメーカーのうちの1社である。将来のEVラインナップに全固体電池技術を検討している自動車メーカーは多い。EVに全固体電池採用を計画している自動車メーカーは、トヨタ、Volkswagen、Ford、General Motors、ホンダなどである。日産は先週、日本で積層全固体電池セルのプロトタイプ生産施設を発表した。このプロトタイプ施設は神奈川県の日産総合研究所内にあり、全固体電池技術のさらなる開発の促進を目的としている。日産は2024年度に横浜工場にパイロット生産ラインを設置する計画で、プロトタイプ生産施設ではプロトタイプ生産用の材料、設計、製造工程を研究することを明らかにした。同社の推計によると、全固体電池のコストは2028年度までに1 kWhあたり75ドル、以降は1 kWhあたり65ドルに削減でき、EVコストはガソリン駆動車と同等になるという。
トヨタとENEOSが水素の燃料利用促進で合意
2022年3月23日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
トヨタとENEOSが、ウーブン・シティで燃料としての水素の生産と使用に共同で取り組む合意書に署名した。トヨタの声明によると、両社は2021年にすでに基本合意書に署名しており、ENEOSがウーブン・シティ近傍に水素燃料補給ステーションを設置・運営し、シティ内に設立されるデモンストレーションハブで水素供給に関する最先端の共同研究を実施するという側面が含まれている。これにより静岡県のウーブン・シティに隣接して水素燃料補給ステーションが設置され、そこに電解槽を設置し、再生可能エネルギーで発電した電力を利用して二酸化炭素を含まない水素を生成する。生成された水素はウーブン・シティで使用される乗用車から商用車までのさまざまな燃料電池電気自動車(FCEV)に供給される。また停電に備えて、水素燃料補給ステーションに固定式の燃料電池発電機が設置される。
重要ポイント:トヨタがウーブン・シティと名付けたこの都市は、自動運転、ロボット工学、パーソナルモビリティ、スマートホーム、人工知能(AI)など、トヨタが開発しているさまざまな技術を「実世界」環境でテストするフルタイムの住民と研究者のホームの役割を果たす。ウーブン・シティでは水素発電を主要電力源とすることになっており、域内の幹線道路では完全自動運転のゼロエミッション車のみを使用し、トヨタのeパレットを輸送と配送、さらに用途に応じて変えられる移動販売車として使用する。日本は炭素排出量削減をサポートするため、2030年頃までに商用水素燃料サプライチェーンの確立を目指している。FCEVの現在の市場シェアは小さいものの、ホンダやトヨタなどの日本企業は電気自動車に加えてFCEVにも取り組んでいる。
Geely、中国北部で初のメタノールハイブリッドセダンをテスト
2022年3月18日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
Geely Autoが、初のメタノールハイブリッド車の極低温性能を中国北部のHeilongjiangでテストを実施している。第4世代Geely EmgrandセダンをベースにしたEmgrandメタノールハイブリッドは、Geelyの最新世代のメタノールパワートレインと同社のLishenハイブリッド技術を搭載している。このセダンには97kWの出力と175Nmの最大トルクを提供する1.8リッターの自然吸気メタノールエンジンと、100kWの出力と320Nmのトルクを生成する電気モーターが搭載されている。エンジンと電気モーターは3速ハイブリッド専用トランスミッション(DHT)に接続されており、純粋な電力で車両を推進することで、低速での効率を向上させている。Emgrandのメタノールエンジンは、低速ではレンジエクステンダーとして機能し、高速でのみ車輪に動力を送る。Geelyは、メタノール燃料のEmgrandは停車状態から時速100 kmまで加速するのに8.8秒かかり、同モデルは9リットルのメタノールで100km走行可能だという。
重要ポイント:Geelyは中国でメタノール燃料車を生産している大手企業の1つである。その親会社であるZhejiang Geely Holding Groupは、これまで17年間にわたり30億元(4億7,100万米ドル)以上をメタノール車とグリーンメタノール技術の開発に投資してきた。Geelyによると、再生可能資源由来のクリーンなメタノールは、排出量削減とカーボンニュートラル達成のための最も現実的で効果的な方法だという。同社はまた、中国のメタノール燃料の価格がガソリンよりもはるかに安いため、メタノールを動力源とする自動車はガソリンを動力源とするモデルよりもコスト面で有利であると考えている。ただし前述の利点にもかかわらず、自動車メーカー各社はメタノール燃料車への投資に関心を持っていない。メタノール自動車を宣伝する側の課題として、燃料補給所の不足やメタノール車に対する消費者の認知度の低さも挙げられる。
BMW、低炭素鋼使用を拡大
2022年2月8日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
BMWが、製造拠点における炭素排出量削減に向けて低炭素鋼の使用を増やしていることを報告している。同社はSalzgitter AGとのあいだでBMWドイツ工場にて使用する低炭素鋼の2026年からの納入契約を締結した。
重要ポイント:BMW Groupは低炭素鋼供給を拡大しており、昨年スウェーデンのスタートアップ企業であるH2 Green Steelと契約済みだ。同社はCO2排出量を最大95%削減し、石炭などの化石資源を必要としない鉄鋼の製造を計画している。H2 Green Steelは水素を使用し、石炭火力発電所からの電力など炭素集約型エネルギー源ではなく再生可能エネルギーによる電力のみを鉄鋼生産に使用する計画で、この鉄鋼は2025年に供給が始まる。両社の合意により、BMWの欧州工場で必要な鉄鋼の40%以上が供給され、年間約40万トンのCO2排出量が削減されることになる。
Renault-Nissan-Mitsubishiアライアンス、2025年までに初の完全ソフトウェア定義車発売へ
2022年2月1日 | ニュース | 企業動向
Renault-Nissan-Mitsubishiアライアンスが、2025年までに初の完全ソフトウェア定義車を発売すると発表した。ライフサイクル全体を通じた自動車オーバー・ジ・エア(OTA)性能の向上を目指し、アライアンス各社はプラットフォームと電子機器の共有によって2026年までに自動運転システム搭載車45モデル、1,000万台以上が路上を走行すると予想し、年間500万以上のクラウドシステム導入を見込んでいる。
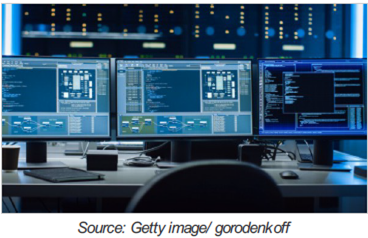
重要ポイント:Renaultは電子機器ハードウェアとソフトウェア・アプリケーションを組み合わせ、共通の集中型電気電子アーキテクチャ開発でアライアンスを主導していく。自動車メーカーの大半は自社内でソフトウェア開発に取り組んでいる。12月にStellantisは、ソフトウェア主導型収益に重点を置く10年間のソフトウェア戦略を打ち出した。オランダを拠点とする同社は、ソフトウェア対応製品とサブスクリプションによる年間収益が2026年に約40億ユーロ(45億米ドル)、2030年に200億ユーロに達すると予測している。
Baidu出資のJiDU、NVIDIAチップ搭載のレベル4自動運転車を来年導入
2022年1月7日 - Automotive Mobility | Headline Analysis
Baiduが設立したスマート電気自動車(EV)企業のJiDU Autoが、レベル4自動運転車(AV)にSoC(システム・オン・チップ)のNVIDIA DRIVE Orinを搭載すると発表した。NVIDIA DRIVE Orinは250 TOPS(1秒あたり1兆回の処理)を超える演算能力を備えており、自動操作やインフォテインメントなどの機能をサポートする。JiDUインテリジェントドライビングシステムはNVIDIA DRIVE Orinを使用したBaiduのAVコンピューティングプラットフォームを搭載している。
重要ポイント:JiDU Autoはスマートカー開発の加速を目指して2020年4月に設立されたBaiduとGeelyの合弁会社(JV)である。同JVのCEOには自転車シェアリング企業 Mobikeの共同創業者であるXia Yiping氏が任命された。同JVが計画しているEVは、Geelyが他の自動車メーカーや自動車製造セクター以外の企業と共有を検討している専用EVプラットフォームで、Geelyのサステナブル体験アーキテクチャ(SEA)に基づいている。AVプラットフォーム、高精細マップ、クラウド技術といったBaiduのスマートカー技術は、スマートEV開発に本当に必要な技術的優位性をGeelyにもたらすと考えられる。
トヨタ、2025年までに独自OSを導入
2022年1月4日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
トヨタが2025年までに独自のオペレーティングシステムであるAreneを車両に導入することを計画している。このソフトウェアは、自動運転車(AV)の運転などの操作を処理し、Volkswagen(VW)の「VW.OS」ソフトウェアや「Mercedes-Benz Operating System」など今後リリースされるライバル製品と競合する。2025年までに自社車両にこのOSを導入し、その後、Subaruなどの関連会社に、おそらくその後はAVに取り組む企業などにも利用可能にする予定であるという。
重要ポイント:ウーブン・プラネット・グループは2021年4月、AV用オペレーティングシステム構築でソフトウェアシステム開発企業のApex.AIと提携した。このパートナーシップの下、同グループはApex.AIが開発したソフトウェア開発キットであるApex.OSをAreneと統合する。2021年9月、ウーブン・プラネットは米国のソフトウェア会社 Renovo Motorsを買収したことを発表した。ウーブン・プラネットの声明によると、この買収により同社の車両開発用オープンプラットフォームであるAreneが深化され、完全なソフトウェア定義型車両インフラスタックのエンジニア陣との強化チームによって複数の自動車メーカーのプラットフォームで機能することが可能になるという。
Volkswagen、ディーゼル車全モデルに低排出パラフィン燃料を採用
2021年12月15日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
Volkswagen(VW)Groupがディーゼルエンジン開発も継続しており、最新のパワートレイン群では新開発のパラフィン系ディーゼルを採用していると報じられた。新開発の燃料には、従来のディーゼル燃料に比べCO2排出量を最大95%削減できるバイオコンポーネントが含まれているという。4気筒TDIディーゼルパワートレインを使用するVWのディーゼルモデルでは、6月以降納入分はすべて、この新燃料が使用可能である。同社の広報担当は「電気モビリティ分野への対応と同時に既存の内燃機関製品群の開発も進めている。さまざまな顧客ニーズに対応すると同時に、国際的に変化するドライブシステムの嗜好と各領域の全般的状況を考慮に入れている」と述べている。
重要ポイント:パラフィン系燃料は水素化植物油(HVO)などのバイオマス廃棄物から製造される。水素と反応させることで炭化水素に変換され、任意の量でディーゼル燃料に添加できる。英国市場では現在、V-PowerディーゼルとHVOが利用可能な選択肢であり、供給は限られているものの、今後10年以内に道路交通輸送における化石燃料市場での最大20〜30%のシェアを獲得する可能性がある。
GenesisのG90、直感的インテリア技術搭載
2021年12月15日 | ニュース | 新製品

Source: Getty Images/algre
Genesisが新たなフラッグシップモデル、G90を発表した。乗員の移動に付加価値を与えるさまざまな技術により、上質な移動体験と車内体験を提供する。
重要ポイント:G90のフロントにはブランドのエンブレムを象徴するよう設計された2ラインヘッドランプを含んだ新たなクレストグリルが装備されており、これは3D効果を生むよう2つのGマトリックスパターンを重ねて構成されている。ヘッドランプは、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)のレンズと方向指示器、ハイビーム、マイクロ・レンズ・アレイ(MLA)テクノロジー活用のロービームとを交差させることで実現されている。ロービームは1モジュールあたり約200のマイクロ光学レンズと超精密技術を組み合わせることで従来のプロジェクションランプよりも小さいレンズを実現し同水準の光強度を提供、G90の先進的イメージをさらに高めている。次世代インフォテインメントシステムであるコネクティッドカー統合コックピット(ccIC)を搭載、クラスターとナビゲーションをパノラマディスプレイに収容し、ハイテクな外観を強化し、センターコンソールに使用のガラス素材とアルミ素材が高級感を演出している。運転席のヘッドレストにはスピーカーが装備されており、ドライバーだけが聞くことができる案内/警告音を発することで、後部座席の乗員に不要な音が聞こえないようになっている。後部座席の座席は別々にリクライニング可能で、暖房/換気(吸気システム)機能対応のレッグサポートとフットレストが新たに追加され、乗員は快適な人間工学的ポジションで休むことができる。合わせガラスやクォーターガラスなど、不要なキャビンノイズを吸収しスムーズなドライブを実現するさまざまな消音材を搭載している。タッチタイプの統合操作機能を備えた2列目中央のアームレストに配置の8インチのアームレスト・タッチ・スクリーン(ATS)を装備しており、乗員はATSを使用して空調モード、座席位置、マッサージ設定、カーテン位置、照明などを調整できる。全体に抗菌素材を使用、UV光滅菌済みアームレストボックスを装備し、抗菌フィルターと光触媒モジュールを備えた空気清浄モードで乗員に安全でクリーンなインテリアを提供する。
INFINITI、2022年型にワイヤレスApple CarPlayとProPILOTアシストを標準装備
2021年12月10日 | ニュース | 新製品
INFINITIが全グレードでワイヤレスApple CarPlayに対応しProPILOTアシスト技術を標準装備した2022年型INFINITI QX50の発売を発表した。後部座席用Type-C USB充電ポート、後部ドアでも作動するインテリジェントキーエントリー、後部ドアハンドルのLEDウェルカムライト、自動防眩バックミラーなどの機能も全グレードに装備する。

Source: INFINITI
重要ポイント:このSUVは、トリムに応じて8インチディスプレイと7インチのディスプレイを備えたデュアルタッチスクリーンのINFINITI InTouchインフォテインメントシステムを搭載している。Wi-Fiホットスポットは最大7台のデバイスが接続可能で、INFINITI InTouchサービスは自動衝突通知と緊急通報サービスを提供する。QX50には先進ProPILOTアシスト技術が搭載されており、高速道路での単一車線走行中、ドライバーをサポートする。ProPILOTアシストの使用によって、ドライバーは車線の中央に留まり、ブレーキをかけたり加速したりできる。死角警告と運転介入、車線逸脱の警告と防止、歩行者検知を含む前方緊急ブレーキ、予測前方衝突警告、後方自動ブレーキ、後方交差交通警報の各機能がQX50の全グレードに標準装備されている。
Volvo Car、英国の全モデルにVodafone Automotive VTSS5追跡装置を装備
2021年12月10日 | ニュース | 新製品
Volvo Carが、英国の全モデルに新たなVodafone Automotive VTS S5追跡装置を装備する予定であることを発表した。全国の地元警察、欧州44ヵ国の地元警察と協力し、Vodafoneのオペレーティングセンター経由で車両の追跡と回収を実施する。
重要ポイント:この追跡装置はVodafoneとTrinsic Connected Carが共同開発したIoT(モノのインターネット)技術を活用している。同機能は一年中24時間休み無く稼働し、車両位置を10mまで特定できる。ドライバーは車両位置をリアルタイムで監視、移動に関するデータを確認、さらに車両への道順を知ることも可能だ。
マツダ、緊急時に車両を安全な場所に誘導する技術を開発
2021年12月8日 - AutoIntelligence | Headline Analysis
マツダが、ドライバーの体調に突然の変化が検知された際に車両を安全な場所に誘導し停止させる自動運転車技術を発表したと報じられた。「Mazda Co-Pilot」というこのシステムは2022年から段階的に車両に導入される。第一段階では、高速道路走行時に車両を路肩へ自動操縦するシステムを組み込み、2025年からは自動操縦による車線変更技術の導入を目指す。報道によると、同社はすでに東京の路上でこの技術を使った試験を実施しているという。試験車両ではドライバーが緊急ボタンを押してハンドルから手を離した後、減速を開始するとともに警告音とハザードライトで危険を表示することができた。
重要ポイント:ドライバーの症状や飲酒状態によって車両が突然制御不能になったことが原因の自動車事故が毎年多数発生している。こうした事故を回避し、人命の損失を防ぐ取り組みに飛躍的な進歩をもたらす可能性がある。
